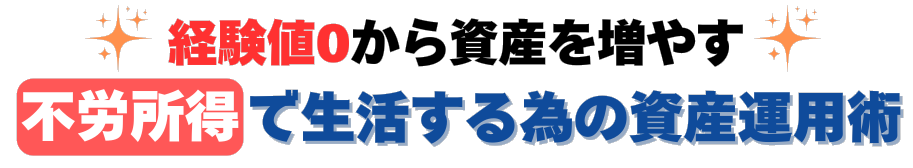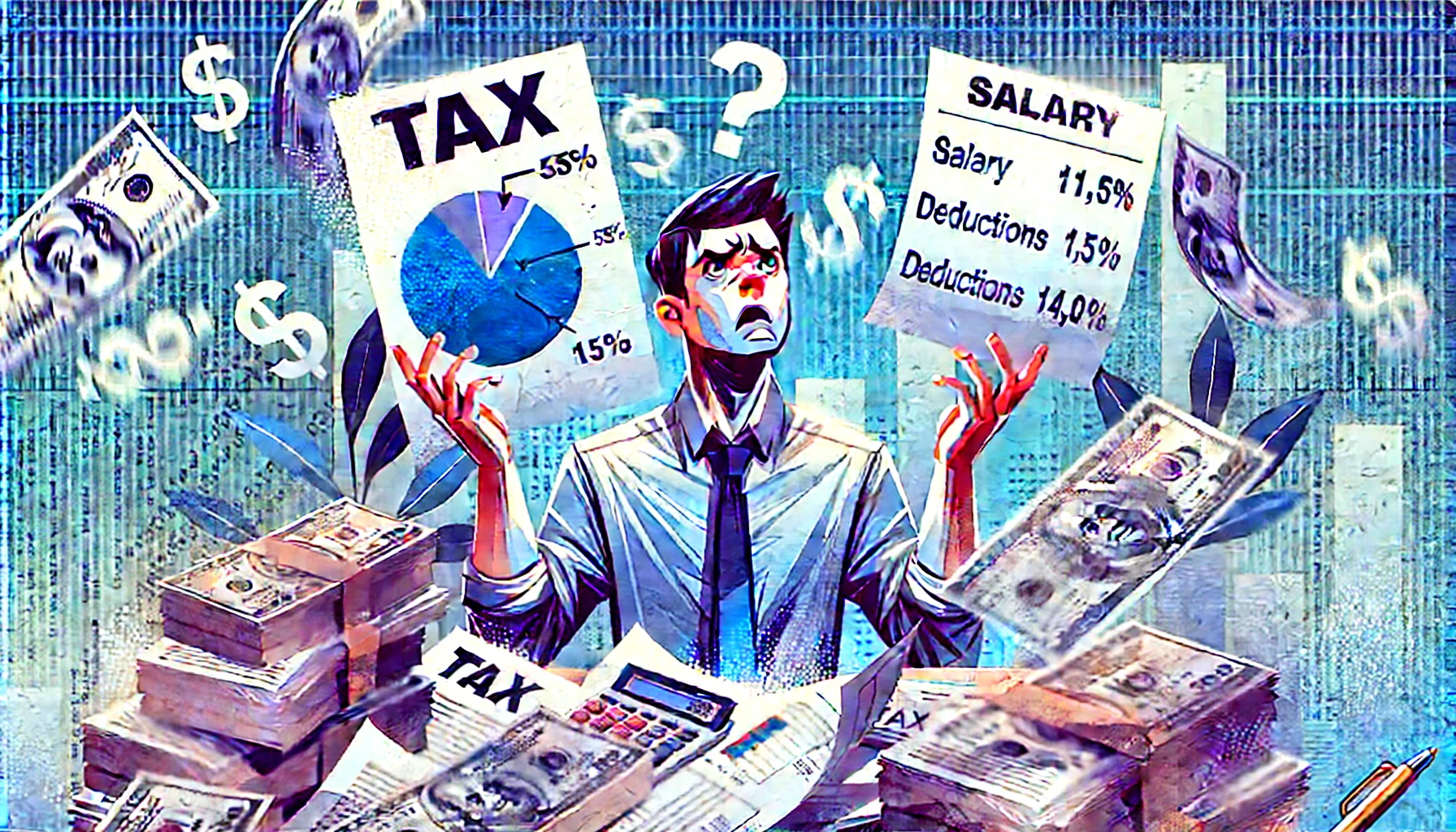
年に数回の特別な収入であるボーナス。しかし、支給明細を見て「税金が高すぎる」「ボーナス控除が多すぎ」と驚いた経験を持つ方は少なくないでしょう。
中には、所得税が倍になったように感じたり、「そもそもボーナスに税金がかからないと思っていたのに…」と疑問に思ったりする方もいるかもしれません。
また、ボーナスへの課税はいつから始まった制度なのか、自分の手取り額はいくらになるのか、簡単な税金シミュレーションで確認したいという需要も考えられます。
この記事では、ボーナスの所得税が高いのはなぜかという根本的な理由から、天引きされる税金や社会保険料の仕組みまで、あなたの抱える不満や疑問に一つひとつ丁寧にお答えします。この記事を読み終える頃には、漠然とした怒りや不満が、制度への深い納得に変わっているはずです。
- ボーナスから天引きされる税金や社会保険料の種類
- 所得税が「高い」「倍になった」と感じる具体的な理由
- 金額別の手取り額がわかる税金シミュレーション
- ボーナスと税金に関するよくある疑問への回答
ボーナス税金がおかしい、むかつく!その理由を解説

- ボーナスの税金が高すぎると感じる仕組みとは
- 所得税が倍になったように見えるのはなぜ?
- ボーナス控除が多すぎ?天引きされるものの内訳
- 所得税の計算方法と引かれる割合
- 健康保険・厚生年金保険料の計算方法
- 雇用保険料もボーナスから引かれる
- 結局ボーナスの所得税が高いのはなぜ?
ボーナスの税金が高すぎると感じる仕組みとは

ボーナスの手取り額が予想より少ないと感じる主な理由は、ボーナスが給与所得の一部として扱われ、法律に基づいて税金や社会保険料が差し引かれる仕組みになっているからです。これは、会社から従業員へ支払われる労働の対価であることに変わりはないためです。
多くの人がボーナスを「特別なご褒美」と捉えているため、給与と同じように様々な項目が控除されることにギャップを感じ、結果として「税金が高すぎる」という不満に繋がっていると考えられます。
実際に、ボーナスの額面が50万円であっても、所得税や社会保険料が合計で約10万円引かれ、手取り額が40万円前後になることは珍しくありません。この約2割にも及ぶ控除額が、手取り額が少ないと感じる直接的な原因と言えます。
所得税が倍になったように見えるのはなぜ?
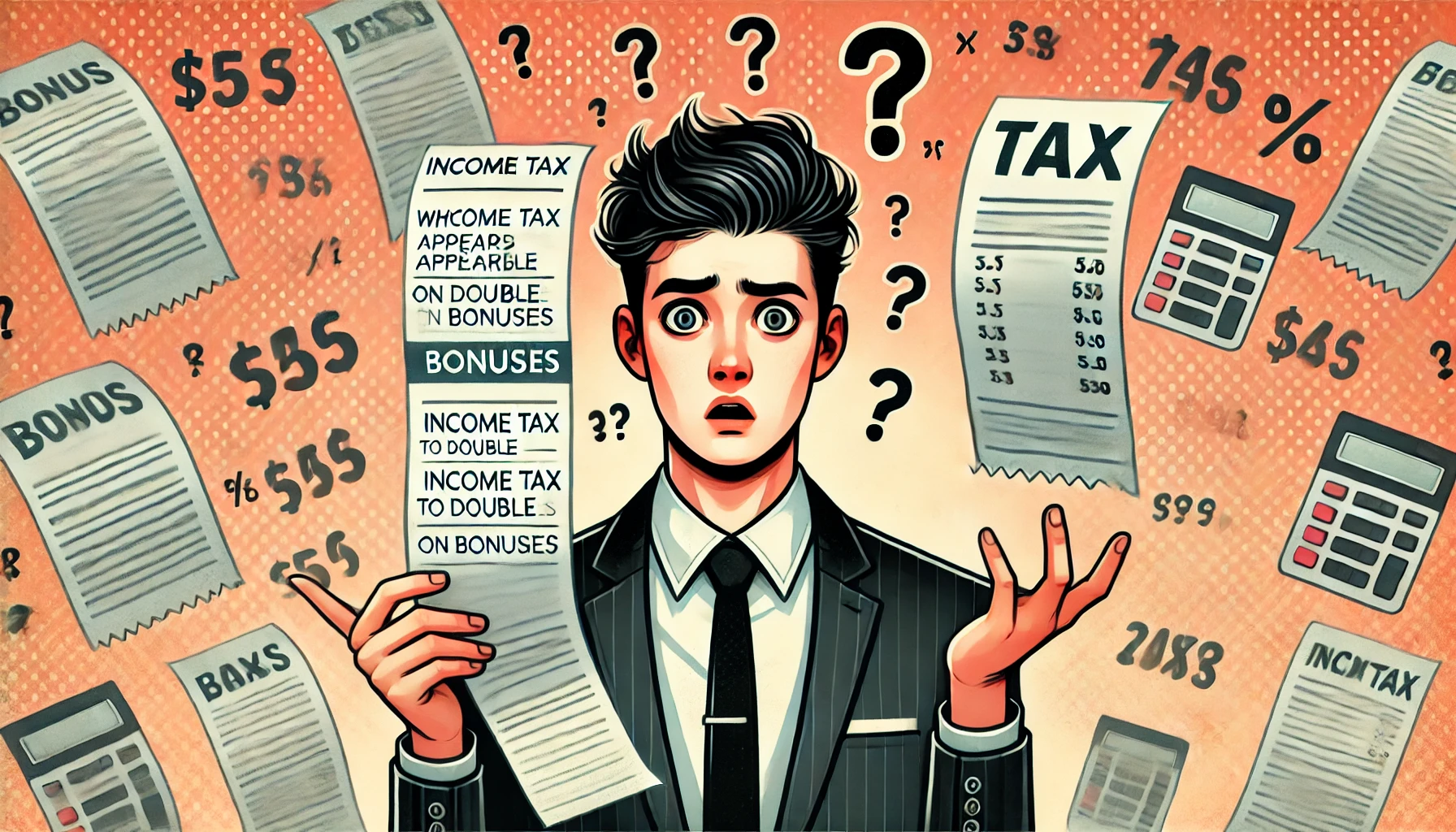
ボーナスの所得税が月給と比べて「倍になった」ように感じることがありますが、これはボーナス特有の所得税計算方法に起因します。月々の給与とは異なり、ボーナスの所得税率は「前月の給与額」を基準にして決定されます。
具体的には、「前月の社会保険料控除後の給与額」と「扶養親族の数」を、国税庁が定める「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率を求めます。このため、例えば前月に残業が多く給与が高かった場合、ボーナスに適用される所得税率も高くなる傾向があります。
したがって、月給の所得税率とボーナスの所得税率を単純に比較すると、後者の方が高く見えるケースが発生します。これが「所得税が倍になった」と感じるカラクリであり、実際の所得に対して不当に高い税金が課されているわけではありません。
ボーナス控除が多すぎ?天引きされるものの内訳
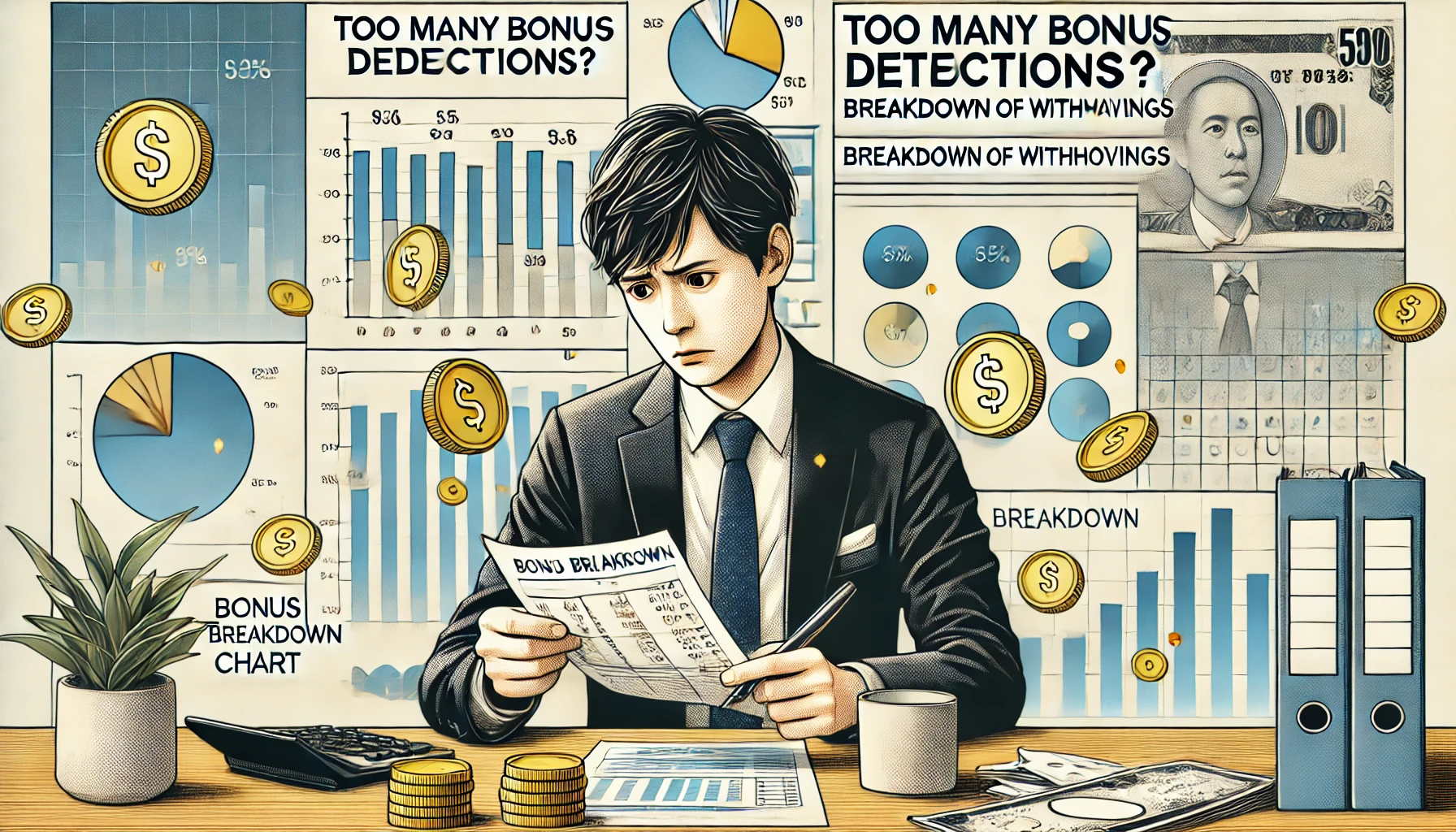
ボーナスから控除される項目は、大きく分けて「所得税」と「社会保険料」の2種類です。社会保険料はさらに3つに分類されるため、合計で4つの項目が天引きされています。これらは法律で定められた義務であり、会社が自動的に計算し、支給額から差し引いています。
「ボーナス控除が多すぎ」と感じる背景には、これらの複数の項目が合算されて引かれていることがあります。それぞれの項目が何のためにあり、どのような役割を果たしているのかを理解することが、納得への第一歩となります。
所得税
所得税は、個人の所得に対して課される国税です。ボーナスから天引きされる所得税は「源泉徴収」という形で、会社が事前に国へ納める仕組みになっています。年間の正確な税額は年末調整で確定し、過不足があれば精算(還付または追徴)されます。
社会保険料(健康保険・厚生年金)
社会保険料には、健康保険料と厚生年金保険料が含まれます。健康保険は、病気やケガをした際の医療費負担を軽減するための制度です。厚生年金は、老後の生活を支える年金制度の財源となります。これらは将来の安心のための費用であり、保険料は会社と従業員で半分ずつ負担しています。
社会保険料(雇用保険)
雇用保険は、失業した際の失業手当や、育児・介護休業中の給付金の財源となる保険です。また、在職中のスキルアップ支援(教育訓練給付)などにも活用されます。万が一の時のセーフティーネットとして、非常に重要な役割を担っています。
所得税の計算方法と引かれる割合

前述の通り、ボーナスの所得税額は「(ボーナス支給額 − 社会保険料の合計額)× 所得税率」という式で算出されます。この計算で鍵となるのが「所得税率」です。
所得税率は一律ではなく、国税庁が毎年公表する「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」によって定められています。この表は、「前月の社会保険料控除後の給与額」と「扶養親族の数」という2つの要素で構成されています。
例えば、前月の給与額が同じでも、扶養している家族がいる場合はいない場合に比べて低い税率が適用され、結果として手取り額が多くなります。また、前月の給与が高ければ高いほど、適用される税率も高くなる累進的な構造を持っているのが特徴です。そのため、自分の正確な税率を知るには、前月の給与明細と家族構成を確認する必要があります。
健康保険・厚生年金保険料の計算方法
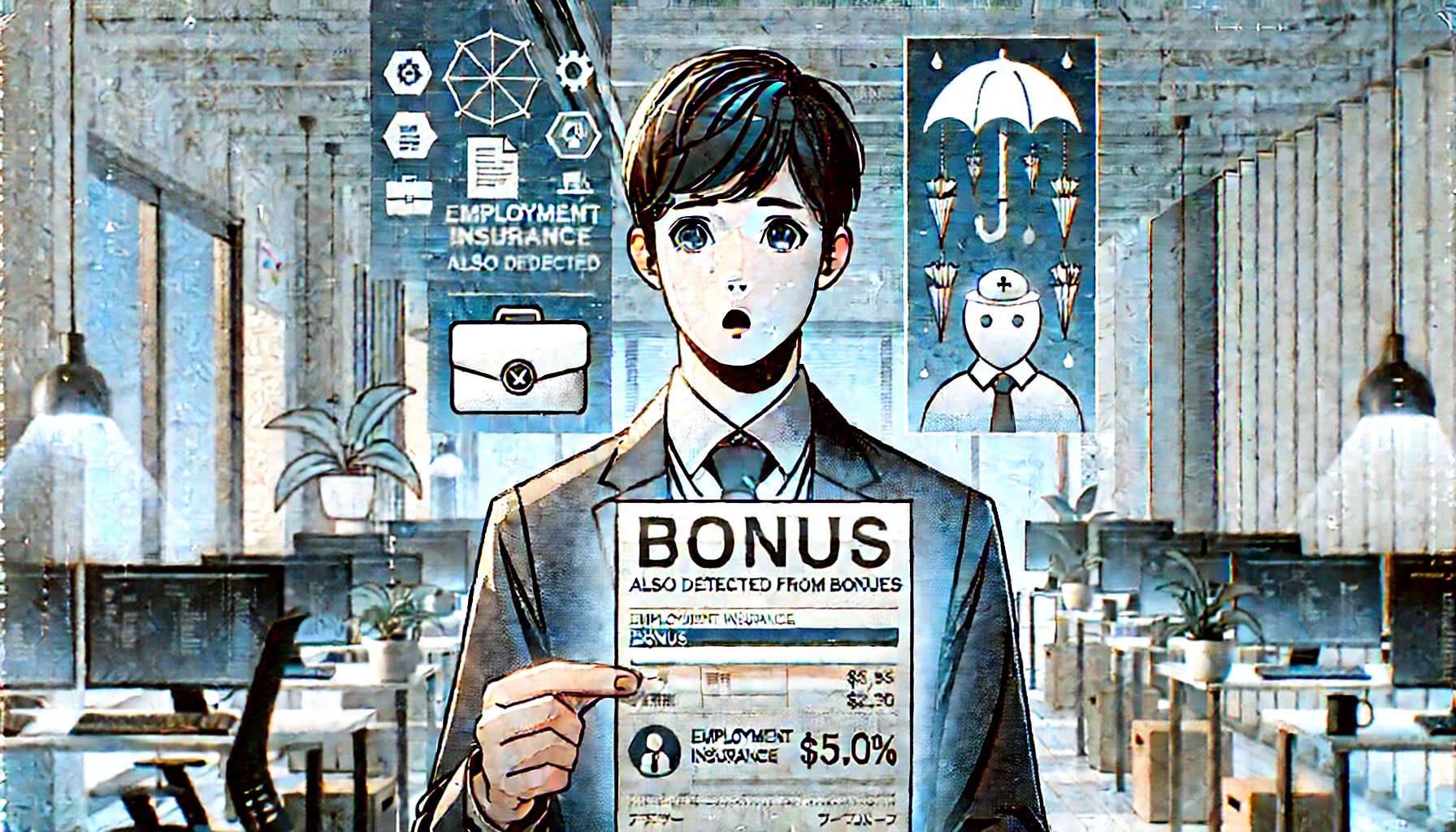
健康保険料と厚生年金保険料は、ボーナス支給額そのものではなく、「標準賞与額」を基準に計算されます。標準賞与額とは、ボーナスの額面から1,000円未満を切り捨てた金額のことです。
計算式は以下の通りです。
- 健康保険料 = 標準賞与額 × 健康保険料率
- 厚生年金保険料 = 標準賞与額 × 厚生年金保険料率
健康保険料率は、加入している健康保険組合や、勤務先の都道府県(協会けんぽの場合)によって異なりますが、おおむね10%前後です。一方、厚生年金保険料率は全国一律で18.3%と定められています。
重要な点として、これらの保険料は全額を個人が負担するわけではありません。法律により、会社と従業員が半分ずつ負担する「労使折半」が義務付けられています。つまり、実際にボーナスから引かれるのは、上記の計算で算出された金額の半分です。例えば厚生年金であれば、9.15%分が個人の負担となります。
雇用保険料もボーナスから引かれる
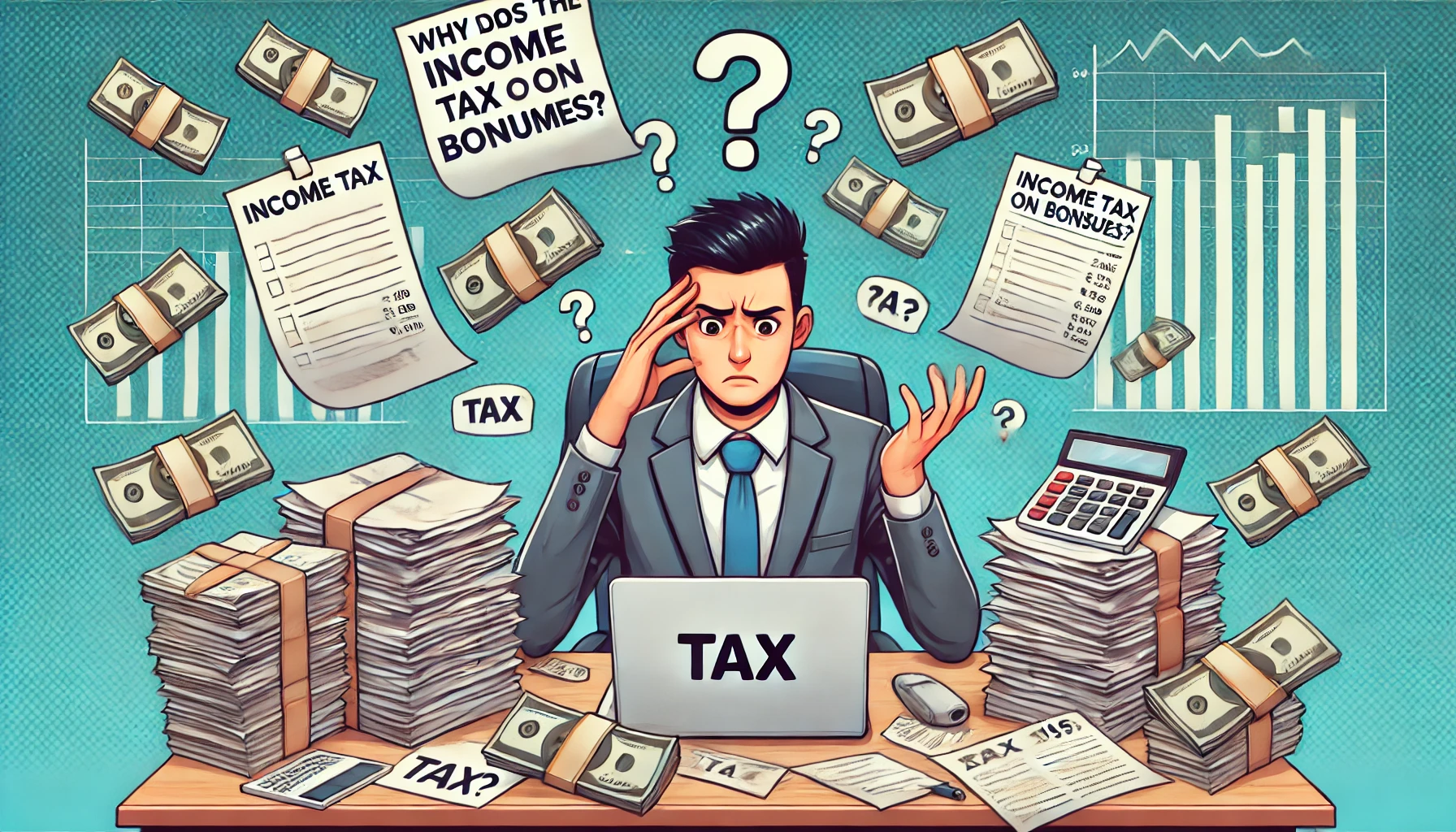
雇用保険料は、健康保険や厚生年金とは異なり、「標準賞여額」ではなく、ボーナスの総支給額(額面)に直接、雇用保険料率を掛けて計算されます。
計算式は非常にシンプルです。
- 雇用保険料 = ボーナス支給額 × 雇用保険料率(労働者負担分)
雇用保険料率も会社と労働者で負担割合が異なりますが、労使折半ではありません。料率は事業の種類によって定められており、例えば一般的な事務職などが含まれる「一般の事業」の場合、令和6年度の労働者負担分の料率は0.6%です。
例えば、50万円のボーナスが支給された場合、労働者が負担する雇用保険料は「500,000円 × 0.6% = 3,000円」となります。他の社会保険料に比べると金額は小さいですが、これも手取り額を構成する重要な要素の一つです。
結局ボーナスの所得税が高いのはなぜ?

ボーナスの所得税が高いと感じる根本的な理由は、主に2つ考えられます。
一つ目は、ボーナスが月給よりも高額であるため、同じ税率でも差し引かれる金額の絶対値が大きくなる点です。例えば、税率が10%だとしても、30万円の給与からは3万円ですが、100万円のボーナスからは10万円が引かれるため、心理的なインパクトが大きくなります。
二つ目は、前述の通り、所得税率の決まり方が累進的であることです。ボーナス自体の金額ではなく「前月の給与」が高いほど税率が上がる仕組みになっています。日本の所得税制度は、所得が高い人ほどより多くの税金を負担するという考え方に基づいているため、ボーナスについてもこの原則が適用されます。
これらのことから、ボーナスは金額の大きさと税制度の仕組みが相まって、どうしても税金の負担感が大きくなりやすいと言えます。
ボーナス税金がおかしい、むかつくと感じる場合に知っておく知識
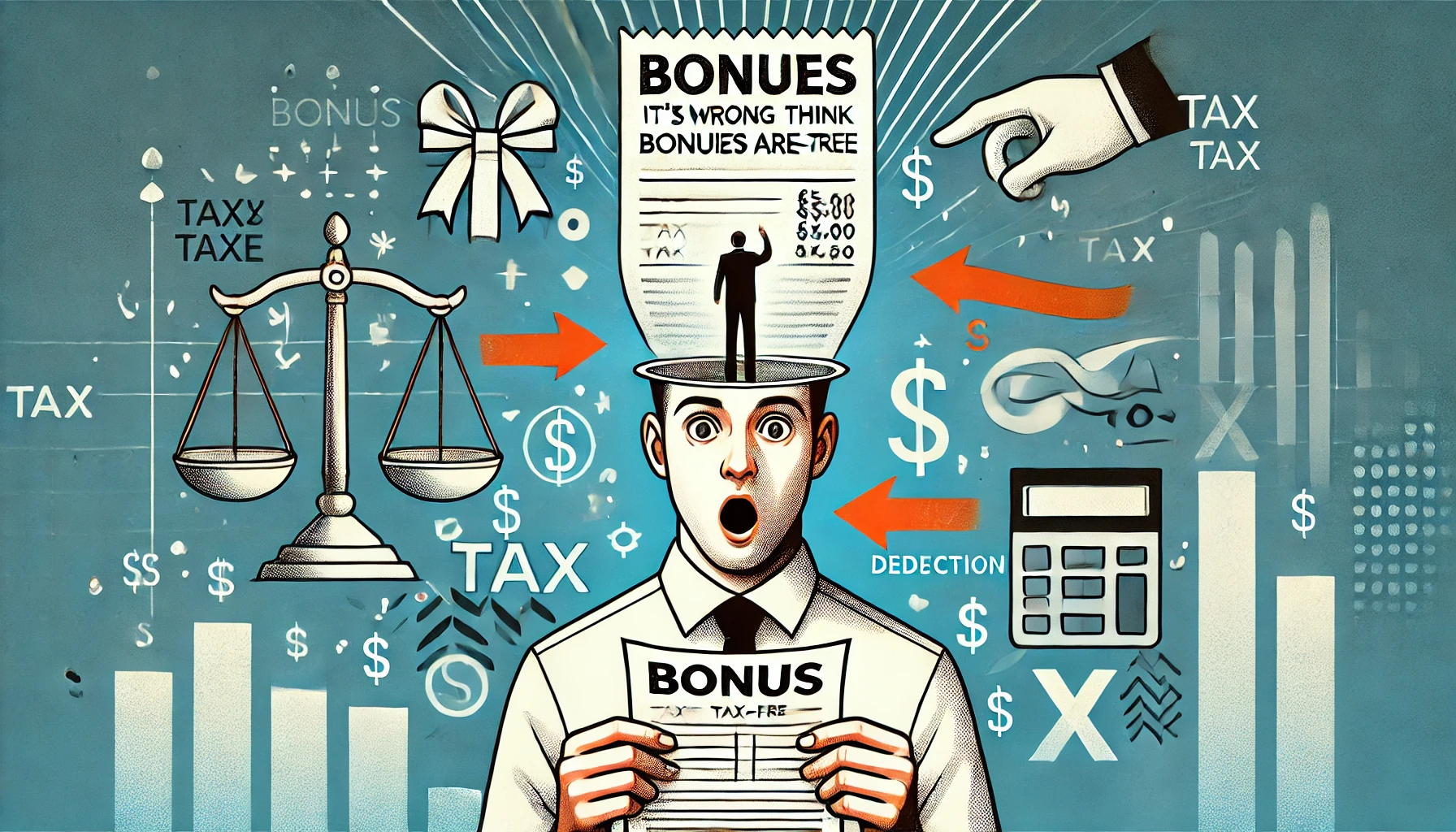
- ボーナスに税金がかからないのは間違い?
- ボーナスへの税金はいつから始まった制度か
- 金額別に見るボーナスの税金シミュレーション
- 住民税がボーナスから天引きされない理由
- ボーナス税金がおかしい、むかつくと感じた方へ
ボーナスに税金がかからないのは間違い?

「ボーナスは特別な報酬だから税金はかからない」という考えは、残念ながら間違いです。法律上、ボーナス(賞与)は定期的な給与と同じ「給与所得」として明確に位置づけられています。
会社から従業員へ、労働の対価として支払われる金銭である以上、所得税や社会保険料の対象となります。支給の名称が「賞与」「期末手当」「インセンティブ」など、どのようなものであっても、この扱いは変わりません。
多くの人が抱く「ご褒美」というイメージと、税法上の「給与」という扱いの間にギャップがあることが、この誤解を生む一因と考えられます。したがって、ボーナスを受け取る際は、必ず一定額が控除されることを前提に資金計画を立てることが大切です。
ボーナスへの税金はいつから始まった制度か
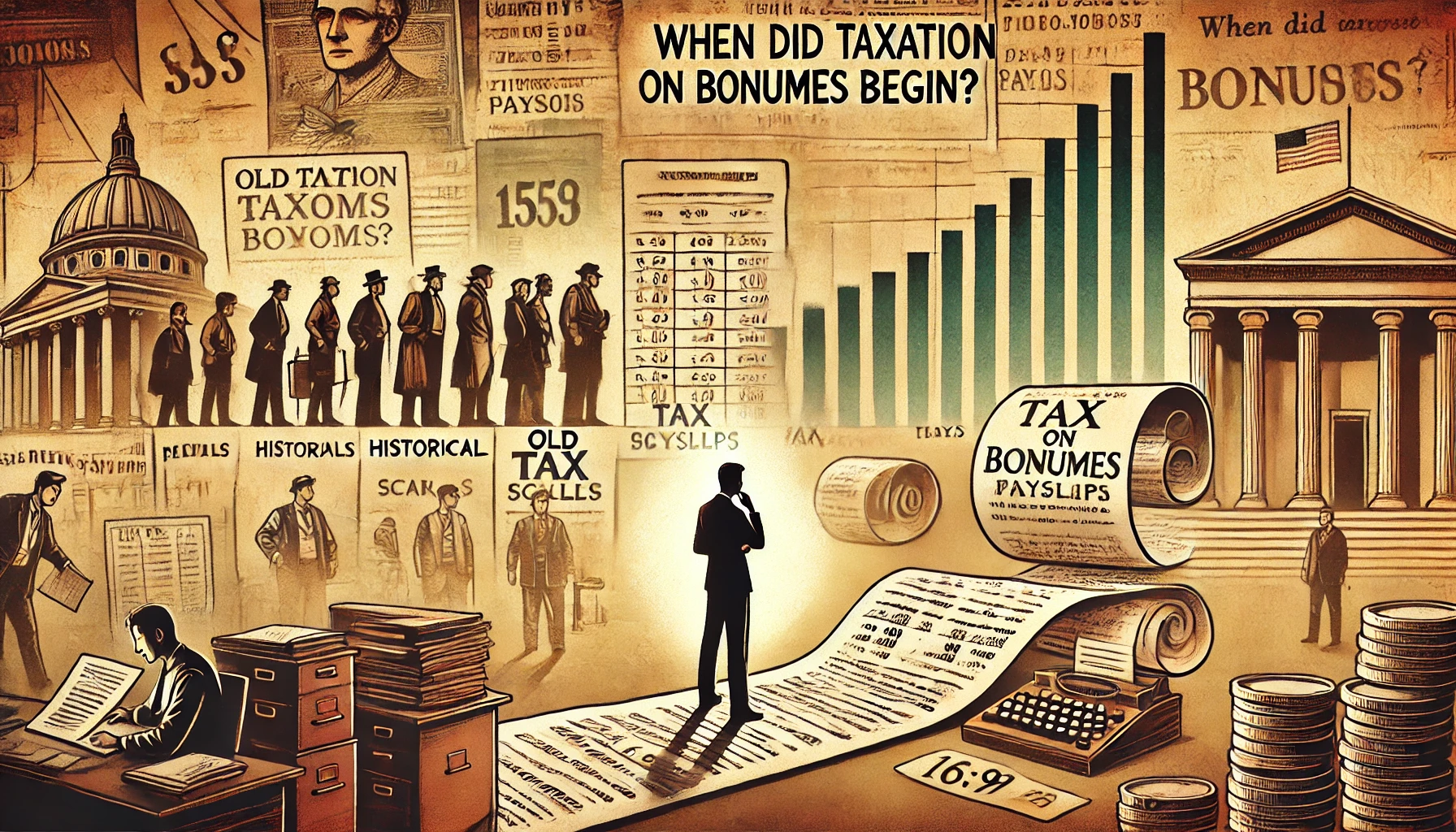
現在のように、ボーナスへ一律に税金がかかるようになったのは、戦後の税制改革がきっかけです。具体的には、1947年(昭和22年)に所得税法が大きく改正され、それまで曖昧だった給与所得の範囲が明確化されました。
この法改正により、ボーナスや賞与といった名称で支払われる一時金も、定期的な給与と同じ給与所得に分類され、課税対象となることが定められました。
それ以前は、ボーナスへの課税は企業ごとの判断に委ねられるなど、統一されたルールが存在しませんでした。税の公平性や透明性を確保する観点から、すべての給与所得に対して等しく課税するという現代の税制度の基礎が、この時に築かれたわけです。
金額別に見るボーナスの税金シミュレーション
実際にボーナスの額面金額から、どれくらいの税金や社会保険料が引かれ、手取り額はいくらになるのでしょうか。ここでは、具体的な金額を例にシミュレーションしてみましょう。
| 商品名 | 30万円の場合 | 50万円の場合 | 100万円の場合 | 200万円の場合 |
| 支給額(額面) | 300,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 | 2,000,000円 |
| 健康保険料 | 14,970円 | 24,950円 | 49,900円 | 99,800円 |
| 厚生年金保険料 | 27,450円 | 45,750円 | 91,500円 | 183,000円 |
| 雇用保険料 | 1,800円 | 3,000円 | 6,000円 | 12,000円 |
| 社会保険料 合計 | 44,220円 | 73,700円 | 147,400円 | 294,800円 |
| 課税対象額 | 255,780円 | 426,300円 | 852,600円 | 1,705,200円 |
| 所得税 | 10,447円 | 17,411円 | 87,034円 | 315,316円 |
| 控除額 合計 | 54,667円 | 91,111円 | 234,434円 | 610,116円 |
| 手取り額 | 245,333円 | 408,889円 | 765,566円 | 1,389,884円 |
※前提条件:東京都勤務、40歳未満、扶養親族なし、協会けんぽ加入、前月の社会保険料控除後給与35万円(令和6年度の保険料率・税率で計算)。あくまで概算であり、実際の手取り額とは異なる場合があります。
このように、支給額が大きくなるにつれて控除される金額も増え、特に100万円を超えると所得税の負担が大きくなることが分かります。
住民税がボーナスから天引きされない理由
ボーナスの明細を見て、「所得税は引かれているのに、住民税が引かれていない」と不思議に思った方もいるかもしれません。これは、住民税の徴収方法が所得税とは異なるためです。
住民税は、前年1年間(1月~12月)の所得を基に年間の税額が計算され、その総額を12分割した金額が、翌年の6月から翌々年の5月までの毎月の給与から天引きされる「特別徴収」という方法が採られています。
つまり、年間の税額がすでに確定しており、それを月々均等に支払っている形です。支給が不定期であるボーナスは、この月々の均等払いの対象にはなっていないため、原則としてボーナスから住民税が直接引かれることはありません。ただし、住民税の負担が免除されているわけではなく、年間の所得の一部として計算された上で、月給からきちんと納付しているという点を理解しておく必要があります。
ボーナス税金がおかしい、むかつくと感じた方へ
この記事では、ボーナスの税金に関する様々な疑問について解説してきました。最後に、今回の重要なポイントをまとめます。
- ボーナスは給与所得の一部であり法律で課税対象と定められている
- 天引きされるのは所得税と社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)
- 手取り額の目安は額面のおおよそ7割から8割程度
- ボーナスの所得税計算は「前月の給与額」が基準となる
- 前月の給与が高いとボーナスに適用される税率も高くなる
- 扶養家族の人数によっても所得税率は変動する
- 健康保険料は所属する組合や都道府県によって料率が違う
- 厚生年金保険料は将来の年金のための積立でもある
- 雇用保険料は失業時や育休・介護休業時の生活を支える
- ボーナスの種類(定期賞与や決算賞与など)で税の扱いは変わらない
- 住民税は前年の所得を基に計算されるためボーナスからは引かれない
- 住民税は毎月の給与から12分割で天引きされている
- ボーナスへの課税は1947年の所得税法改正から始まった
- 税金の仕組みを正しく理解することが漠然とした不満の解消に繋がる
- より詳しい内訳や計算根拠は必ず給与明細で確認できる