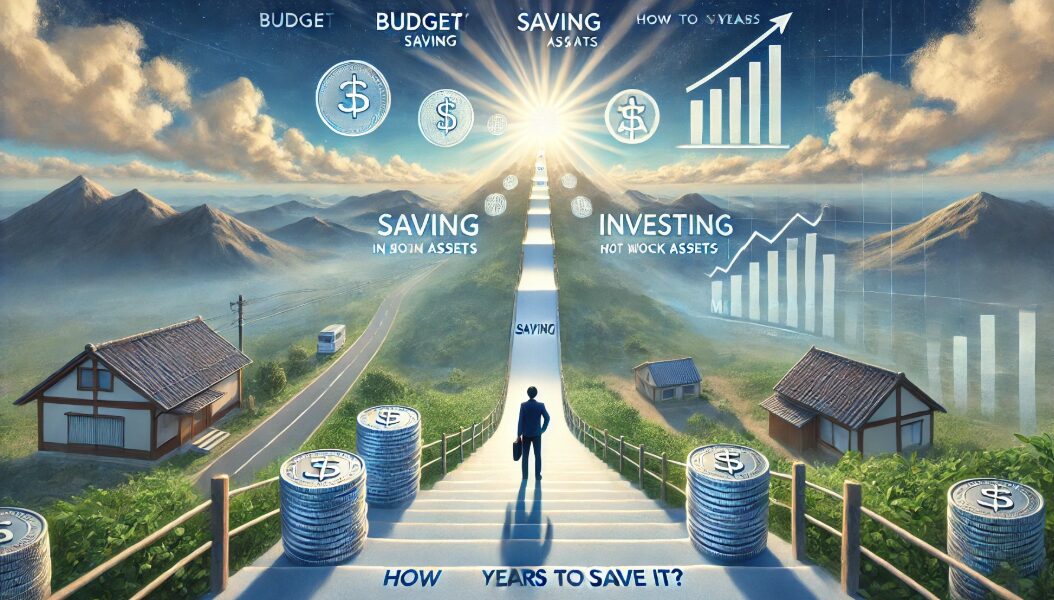
こんにちは、「ぼちぼち大家」です。
当ブログ「不労所得で生活する為の資産運用術」へようこそ。
資産3000万円 精神的余裕、というキーワードでこの記事にたどり着いたあなたは、今、資産形成の大きな節目にいるのかもしれません。
5年・10年で3000万貯めるにはどうすれば良いのか、そもそも、3000万貯めるには何年かかるのか?
そして資産3000万円で精神的余裕は本当に手に入るのか、多くの方が具体的な道筋を探しています。
3000万円で人生変わると言われますが、資産3000万は上位何%にあたり、特に40代の割合はどのくらいなのでしょうか。
また、貯金3000万超えたら、次のステージをどう考えるべきかという課題も出てきます。
NISAや株式投資(セミリタイア)という選択肢の現実と、なぜ私が「不動産投資」を最強のゴールと断言するのか。
その理由に触れつつ、不動産投資をゴールにした「二階建て資産形成術」について、この記事で詳しく解説します。
この記事のポイント
- 資産3000万円の客観的価値(アッパーマス層、中央値との比較)
- 3000万円で得られる「精神的余裕」と「リアルな生活レベル」
- 5年・10年で3000万円を貯めるための具体的シミュレーション
- 【競合分析を反映】3000万円で「セミリタイア」は可能か?現実的なシミュレーション
- 【競合分析を反映】資産達成後に消えない「3つの不安」と「5つの鉄則」
- 不動産投資を最終ゴールに設定する戦略的な理由
「3000万円」は素晴らしい中間目標ですが、それだけでは「不安」が消えないのも事実です。
当ブログでは、NISAなどの金融投資を「滑走路」とし、不動産投資で「本当の精神的余裕」というゴールを目指す、会社員だからこそ可能な最強のロードマップを体系的に解説しています。
先に結論となる「戦略の全貌」を知りたい方は、まずはこちらの旗艦記事からご覧ください。
『二階建て資産形成術』の全貌を詳しく見る
資産3000万円で得られる「精神的余裕」と「生活」のリアル

まず、資産3000万円という金額が持つ「客観的な価値」と、それが私たちの「精神や生活」にどんな影響を与えるのか、リアルなところを見ていきましょう。
この金額の「立ち位置」を知ることは、目標を立てる上でとても重要ですからね。
資産3000万円の客観的価値|アッパーマス層の割合と立ち位置
「資産3000万円」と聞いても、ピンとこないかもしれません。
これが日本全体でどのくらいの位置なのか、客観的なデータで確認してみましょう。
「アッパーマス層」への到達
まず知っておきたいのは、「資産3,000万円」がどの階層に位置するのかということです。
野村総合研究所(NRI)の推計によれば、世帯の預貯金・株式・投資信託などの金融資産から負債(住宅ローンなど)を差し引いた「純金融資産」が3,000万円以上5,000万円未満の層を「アッパーマス層」と定義しています。
これは、全世帯の大多数を占める「マス層(3,000万円未満)」から一歩抜け出し、上位層へと足を踏み入れたグループといえます。
アッパーマス層の割合と立ち位置
2023年時点の野村総合研究所の最新推計では、アッパーマス層は全国で約576.5万世帯にのぼります。
日本の全世帯数(総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」では約5,621万5千世帯)と比較すると、全体の約10.3%を占めることになります。
つまり、純金融資産3,000万円を達成するということは、日本全体で上位約1割に入る水準に到達したことを意味します。
この層は、可処分所得や投資余力が増すことで、将来への備えや資産運用の選択肢が広がる段階といえるでしょう。
(出典:野村総合研究所「純金融資産保有額別世帯数推計(2023年)」/総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」)
中央値から見た「資産3,000万円」のインパクト
「平均値」では一部の高額資産保有者が全体を押し上げるため、生活実感に近いのは「中央値」です。
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」によると、二人以上世帯の金融資産保有額の中央値は約500万円前後、単身世帯では100万円台にとどまっています。
この数値と比較すると、純金融資産3,000万円というのは中央値の6倍以上に相当し、国内では相当な蓄えを持つ層といえます。
この層に到達することで、資産運用や生活防衛の幅が大きく広がることがわかります。
(出典:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[令和5年]」)
年代別に見た到達難易度
年代別に見ると、金融資産3,000万円以上を保有している割合は、年齢が上がるにつれて増加します。
公的調査の集計では、50代以降になると全体の1〜2割程度がこの水準に達しており、退職金や長期積立などによって資産を形成している世帯が多いことがわかります。
一方で、40代以下で3,000万円を達成している世帯は少なく、実際には全体の数%にとどまると見られています。
つまり、40代でこのラインに到達している人は、計画的な貯蓄・投資を継続してきた少数の層といえます。
この年代での達成は簡単ではないものの、決して不可能ではなく、資産形成を戦略的に行うことで現実的な目標になり得ます。
資産3,000万円で得られる「3つの精神的余裕」の正体

さて、資産3000万円という数字は、単なる金額以上の、大きな「精神的余裕」をもたらすと私は考えています。
その正体を3つに分解してみます。
1. 「老後の生活不安」からの解放(守りの余裕)
第一に、多くの日本人が抱える「老後の生活不安」というストレスからの解放です。
「老後2000万円問題」なんて言葉もありましたが、それを超える3000万円という資産がある事実は、「いざという時も大丈夫」という強力な安心材料になります。
不測の事態が起きても、すぐにお金に困ることはない。
この事実は、日々のストレスを劇的に軽減してくれます。
2. 働き方における「選択の自由」(攻めの余裕)
第二に、仕事に対する考え方が変わる「選択の自由」です。
会社からの給与収入への依存度が下がるため、「嫌な仕事を辞める」という選択肢が現実味を帯びてきます。
これは本当に大きいです。
生活のために我慢して働くのではなく、「やりたい仕事を選ぶ」「働く時間を減らす」といった、自分軸でのキャリアを選択できる余裕が生まれます。
3. 銀行からの「信用力」の獲得(次のステージへの余裕)
第三に、これが当ブログで最も重要視している点ですが、銀行からの「信用力(クレジット)」の獲得です。
3000万円の純資産があれば、銀行は「この人には返済能力がある」と判断し、融資審査の評価が劇的に向上します。
NISAや株式投資だけを見ていると、この「信用力」という視点は見落としがちです。
しかし、この「信用力」こそが、次のステージである「レバレッジ(てこの原理)を効かせた資産形成」…つまり不動産投資への強力なパスポートとなるのです。
資産3000万円で変わる「生活レベル」と「消える不安」
「精神的余裕」と言っても、具体的に生活はどう変わるの?と疑問に思うかもしれません。
競合となる他の記事や、資産を築いた人たちの思考パターンを見ても、共通するリアルな生活の変化があります。
贅沢はできないが「我慢」は無くなる
まず、3000万円で「高級車を乗り回す」とか「毎日高級ディナー」みたいな、派手な贅沢ができるわけではありません。
むしろ、そういうことをすると資産はあっという間に底をつきます。
そうではなく、生活の中での「小さな我慢」が無くなる、というイメージが近いですね。
例えば、「スーパーで値札を見ずにカゴに入れる」「ランチで一番食べたいものを選ぶ」といった、日々の小さなストレスから解放される感覚です。
この「我慢しなくて良い」という感覚が、日々の満足度を大きく上げてくれるんです。
「人間関係のストレス」からの解放
「働き方の自由」とも繋がりますが、人間関係のストレスも大きく減るようです。
「この会社に依存しなくても大丈夫」という余裕が、結果として「嫌な上司や取引先との仕事を断る」「気の乗らない飲み会に行かない」という選択を可能にします。
生活の質(QOL)は、お金そのものよりも、こうした「人間関係のストレスフリー」によって決まる部分も大きいのではないでしょうか。
陥るな!「ライフスタイル・インフレ」の罠
ただし、ここで注意点があります。
資産を達成した人たちが共通して気をつけているのが、「生活レベルを上げない」ことです。
資産が3000万円に達したからといって、急に支出を増やすことを「ライフスタイル・インフレ」と言います。
これをやってしまうと、せっかく築いた資産がすぐに目減りし、結局は元の不安な生活に逆戻りです。
むしろ、達成した人ほど「節約志向が強い」「無駄な支出を抑える」という堅実なマインドを持っていることが多いですね。
資産3000万円を「達成」し「本当の余裕」を得るための全戦略
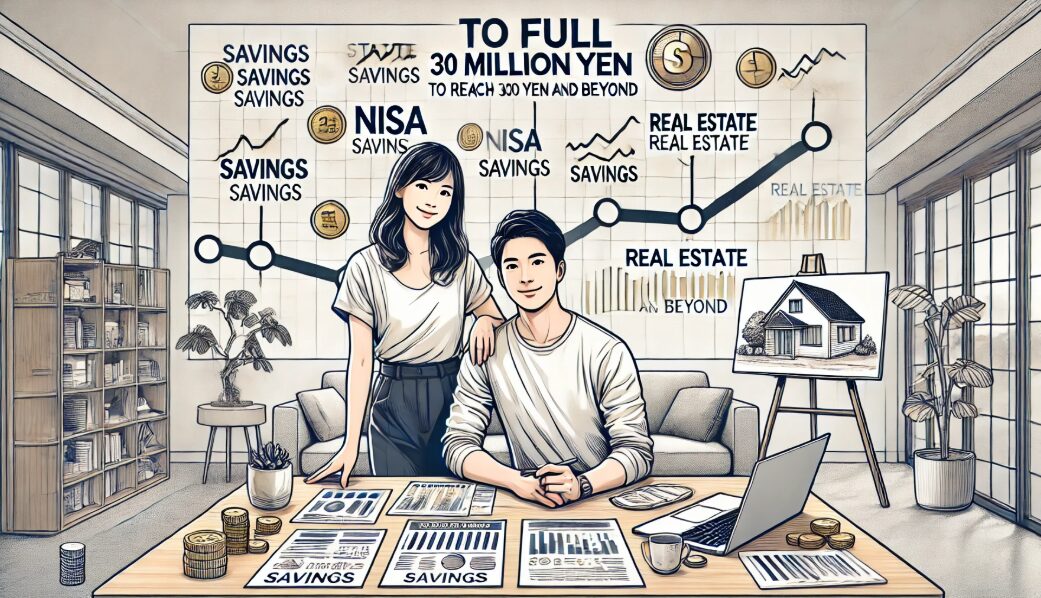
では、その「アッパーマス層」に到達するために、具体的にどう行動すればいいのか。
そして、達成した後に「本当の余裕」を得るために、私たちはどう戦略を立てるべきか。
ここからは、資産を「貯める」戦略と、その資産を「活かす」戦略について、詳しく解説していきます。
資産3000万円を「10年」で貯めるには? 3つのモデルケース
まず、「3000万貯めるには何年必要?」という疑問にお答えします。
これは当然、年収、生活費、そして投資の有無によって大きく変わります。
ここでは、元記事でも使った具体的なモデルケース3つで、「貯金だけ」で貯めた場合のシミュレーションを見てみましょう。
ケース1:独身・手取り25万円の会社員
比較的若い世代や、キャリアの初期段階にある方を想定したモデルケースです。
| 項目 | 金額 | 内訳・備考 |
| 手取り月収 | 25万円 | |
| ボーナス(手取り) | 60万円 | 年2回・合計 |
| 年間の手取り収入 | 360万円 | (25万円 × 12ヶ月) + 60万円 |
| 月々の支出 | 18万円 | 家賃: 7万円、食費: 4万円、他 |
| 年間の貯金額 | 124万円 | 月々7万円 + ボーナス40万円 |
貯金だけで貯める場合に必要な年数
3000万円 ÷ 124万円/年 = 約24.2年
ケース2:独身・手取り35万円の会社員
収入が上がり、生活にも少し余裕が出てきた中堅社員を想定したモデルケースです。
| 項目 | 金額 | 内訳・備考 |
| 手取り月収 | 35万円 | |
| ボーナス(手取り) | 100万円 | 年2回・合計 |
| 年間の手取り収入 | 520万円 | (35万円 × 12ヶ月) + 100万円 |
| 月々の支出 | 22万円 | 家賃: 9万円、食費: 5万円、他 |
| 年間の貯金額 | 236万円 | 月々13万円 + ボーナス80万円 |
貯金だけで貯める場合に必要な年数
3000万円 ÷ 236万円/年 = 約12.7年
ケース3:共働き夫婦(子供なし)・世帯手取り50万円
夫婦で協力して貯蓄を進める、パワーカップルを想定したモデルケースです。
| 項目 | 金額 | 内訳・備考 |
| 世帯の手取り月収 | 50万円 | 夫30万円、妻20万円など |
| 世帯のボーナス(手取り) | 150万円 | 年2回・合計 |
| 年間の世帯手取り収入 | 750万円 | (50万円 × 12ヶ月) + 150万円 |
| 月々の支出 | 30万円 | 家賃: 13万円、食費: 7万円、他 |
| 年間の貯金額 | 360万円 | 月々20万円 + ボーナス120万円 |
貯金だけで貯める場合に必要な年数
3000万円 ÷ 360万円/年 = 約8.3年
ケース3なら10年切りが見えてきますが、それでもかなり節約を頑張った前提のシミュレーションです。
「そんなに筋書き通りに貯蓄出来たら苦労しないよ…」という声も聞こえてきそうですね。
たしかに急な出費などを計算に入れていませんし、しっかり節約しないとこの筋書き通りにいかない事が多いです。
だからこそ、ただ貯蓄するだけでなく、より効率的な方法を考える必要があります。
※上記シミュレーションはあくまで一例です。
税金や社会保険料の変動、突発的な支出は考慮していないため、目安としてご覧ください。
貯蓄ペースを上げるための「3つの現実的なポイント」

シミュレーション結果からも分かる通り、目標達成の期間を短縮するには、結局のところ以下の3つが重要です。
これは、他の多くの金融メディアや資産形成を達成した人たちが口を揃えて言うことでもありますね。
1. 収入を増やす
まずはシンプルに「入金力」を上げること。
本業での昇進や転職、あるいは副業を始めるなど、収入源を増やす努力はやはり基本です。
ただ、これは時間や体力も必要ですし、誰もがすぐに実行できるとは限らないのが難しいところです。
2. 支出を減らす(最優先は「固定費」の見直し)
そこで、より現実的かつ即効性があるのが「支出を減らす」ことです。
特に見直すべきは「固定費」ですね。
食費や趣味代といった「変動費」を切り詰めるのはストレスがかかりますが、固定費は一度見直せば効果がずっと続きます。
固定費見直しの例
- 家賃:より安い物件に引っ越す、住宅ローンを見直す
- 通信費:格安SIMに乗り換える、不要なオプションを解約する
- 保険料:本当に必要な保障か見直す、掛け捨て型にする
- サブスク:使っていないサブスクリプションサービスを解約する
こうした見直しで月1万円でも支出が減れば、年間12万円。
これは貯蓄ペースに大きく影響します。
3. 資産運用(NISAは「滑走路」として必須)
そして、貯金だけでは時間がかかりすぎる(ケース1だと24年も!)という現実を解決するのが「資産運用」です。
「投資は怖い」と考える方もいるかもしれませんが、インフレが進む現代において、「投資をしない」こと自体が、現金の価値が目減りしていくリスクを負っていることになります。
特に、2024年から始まった新NISAは、運用益が非課税になる強力な制度です。
当ブログ(二階建て資産形成術)では、このNISAなどの金融投資を、最終ゴールへの「滑走路」として必須のステップと位置づけています。
資産3000万円の「次のステージ」と「現実」

さて、こうした努力で「資産3000万円」を達成した、あるいは目前にしている方の最大の関心事は、その「使い道」でしょう。
特に「セミリタイア(サイドFIRE)」は可能か、という点は最も気になるところです。
ここでは、多くの競合記事でも触れられている「セミリタイアの現実」と、達成後に直面する「新たな不安」について、データを踏まえて解説します。
資産3000万円の使い道:セミリタイア(サイドFIRE)は可能か?
結論から言えば、3000万円で「完全なリタイア(フルFIRE)」は困難ですが、「セミリタイア(サイドFIRE)」は現実的な選択肢となります。
「完全リタイア(フルFIRE)」が難しい理由(4%ルール)
FIREの一般的な指標に「4%ルール」があります。
これは「年間の生活費を、資産の4%以内で賄えば、資産が枯渇しにくい」という理論です。
これを3000万円に当てはめてみましょう。
3,000万円 × 4% = 年間120万円(月額 10万円)
つまり、月10万円の生活費で暮らしていかない限り、資産は理論上減っていくことになります。
独身であっても、月10万円で生涯を過ごすのはかなり厳しいですよね。
現実的な選択肢「セミリタイア(サイドFIRE)」とは
そこで現実的なのが「セミリタイア(サイドFIRE)」という働き方です。
これは、「資産運用益」+「好きな仕事での労働収入」で生活を組み立てるスタイルです。
例えば、月25万円の生活費が必要な場合、以下のように分担します。
- 資産運用益:月10万円(3000万円を4%で運用)
- 労働収入:月15万円(週3日の好きな仕事などで稼ぐ)
フルタイムで働く必要がなくなり、前述した「精神的余裕」や「選択の自由」を具体的に手に入れることができます。
「3000万円」という資産は、完全なリタイアは難しくても、このように働き方の自由度を格段に上げる強力な武器となりますね。
では、2000万円台から3000万円の資産でサイドFIREを実現するには、具体的にどのようなステップを踏めばよいのでしょうか?
世帯別のシミュレーションや失敗例を含めた現実的な道筋を、以下の記事で詳しく解説しています。
貯金3000万超えたら?「不安が消えない」3つの理由
しかし、3000万円を達成し、セミリタイアという選択肢が見えてきても、新たな不安が生まれます。
これは多くの資産達成者が共通して抱える悩みでもあります。
- インフレで資産価値が目減りする不安
円預金で持つことは、資産価値を毎年失うのと同じです。年2%のインフレが続けば、3000万円の価値は10年後には約2460万円の価値にまで目減りしてしまいます。 - 資産を「食いつぶす」不安
セミリタイア戦略(4%ルール)は、資産の「取り崩し」を前提とします。市場が好調な時は良いですが、暴落が起きた際に資産が減っていく恐怖の中で生活するのは、新たな精神的ストレスとなります。 - 予想外の支出(突発的なリスク)への不安
病気や怪我での医療費、親の介護費用、家の修繕費など、まとまった支出が起きた際に、資産が大きく減るリスクです。
資産3000万円で人生を後悔しないための5つの鉄則
これらの不安から資産を守り、人生の選択肢を広げ続けるために、資産を持った後の行動規範として「5つの鉄則」をまとめます。
これは多くの競合記事や専門家が共通して指摘している点でもありますね。
資産3000万円で守るべき5つの鉄則
- 生活レベルを上げない(ライフスタイル・インフレの防止)
これが最も重要です。支出が増えれば、セミリタイアのハードルが上がるだけです。 - SNSの「儲け話」には絶対に乗らない
まとまった資産を持つと、高利回りを謳う投資詐欺の誘惑が増えます。投資の基本は「長期・積立・分散」です。 - 資産を「消費」ではなく「投資(種銭)」と考える
3000万円は高級車を買うための「消費」資金ではなく、さらなる収入を生むための「種銭」です。 - 家族とお金の使い方や将来について話し合う
セミリタイアや大きな投資判断は、家族の理解が不可欠です。資産の継承なども含め、共通の目標を持つことが重要です。 - お金の専門家(FPなど)にセカンドオピニオンを求める
自分の戦略が正しいか、税制面で見落としがないか、客観的な視点を活用しましょう。(競合データからは「健康維持に投資する」という視点もありました。体が資本ですから、これも大事な鉄則ですね!)
これらの鉄則を守ることで、資産を「守る」ことはできるかもしれません。
しかし、インフレや「資産の食いつぶし」といった根本的な不安から逃れるには、資産を「守る」だけではなく、「安定的に資産を生み出し続ける仕組み」を作る必要があります。
NISAや株(守り)と、不動産(攻め)を組み合わせる当ブログの核心戦略こそが、その不安を解消する答えになります。
NISAと不動産を組み合わせる「二階建て資産形成術」とは?
資産3000万円の「最強のゴール」とは

さて、セミリタイアの現実と、資産を守る鉄則を見てきました。
NISAや株式投資を活用したセミリタイア戦略は、確かに「働き方の自由」を与えてくれます。
しかし、それは「資産の取り崩し」を前提とした、前述の『不安』が常につきまとう「守り」の戦略とも言えます。
では、その不安を根本から解消し、さらに上のステージを目指す「攻め」の戦略とは何か。
それが、私が「最強のゴール」として推奨する不動産投資です。
なぜNISAや株式投資(セミリタイア戦略)だけでは「不十分」なのか
NISAや株式投資(インデックスファンド)だけで生活しようとすると、生活費を全て賄うには莫大な元手が必要になります。
仮に年間300万円(月25万円)の生活費を、前述の「4%ルール」で賄おうとすると、元本は7500万円も必要になります。
3000万円では、月10万円の「お小遣い」にしかならず、生活の基盤とするには不十分です。
そして何より、「資産の取り崩し」という行為そのものが、本当の「精神的余裕」を奪う可能性があります。
口座残高が減っていく恐怖と常に隣り合わせの生活は、本当の「精神的余裕」とは言えないのではないでしょうか?
NISAや株式投資は、あくまで資産を「増やす」ための強力なツール(滑走路)であり、生活の全てを支える「基盤(ゴール)」とするには、多くの人にとって再現性が低いと私は考えています。
「インデックス投資こそが最適解だと思っていたのに…」と驚かれたかもしれません。
もちろんインデックス投資は素晴らしい手法ですが、なぜ一部で「インデックス投資はカモ」とまで言われてしまうのか、その理由と、カモにならず賢く活用するための対策を以下の記事で解説しています。
あわせて読みたい
なぜ不動産投資がゴールとして最適なのか
セミリタイア戦略が「資産の維持・取り崩し」という「守り」の戦略であるのに対し、不動産投資は、3000万円で得た「信用力」を活かして資産規模そのものを拡大する「攻め」の戦略だからです。
不動産投資は、単なる金融商品の売買ではありません。
物件という実物資産を所有し、入居者に住まいというサービスを提供し、その対価として家賃収入を得るという、非常に分かりやすい「事業」です。
あなたは、投資家であると同時に、アパートやマンションの「経営者」になるのです。
不動産投資を最強のゴールと断言する4つの理由
不動産投資が、なぜ会社員の資産形成における「最強のゴール」なのか。
その理由を、4つの具体的なメリットに分解して解説します。
- 1. レバレッジ効果
これが最大の武器です。会社員としての安定収入と「3000万円の純資産」という実績を担保に、銀行から融資を受けることで、自己資金の何倍もの価格の物件を購入できます。これにより、資産形成のスピードを劇的に加速させることが可能です。 - 2. 安定した家賃収入
入居者がいる限り、毎月安定したキャッシュフローを生み出してくれます。株価のように日々変動せず、「家賃」という契約に基づく安定収益が毎月入ることは、計り知れない安心感につながります。 - 3. インフレへの耐性
物価が上昇するインフレ局面では、現金の価値は目減りします。しかし、不動産という「現物資産」は、物価と共にその価値や家賃も上昇する傾向にあります。 - 4. 税制上の優位性
不動産所得の計算上、「減価償却費」という実際には支出していない費用を経費として計上できます。(※詳細は複雑なので専門家への相談が必須ですが、こうした税務上のメリットが期待できる場合がある、という点も魅力です。)
免責事項
不動産投資は大きなリターンが期待できる一方、「空室リスク」「金利上昇リスク」「災害リスク」など、多くのリスクを伴います。
また、税制上の優位性についても個人の状況や物件によって異なり、必ずしも節税になるとは限りません。
投資の実行は、ご自身の責任において、十分な情報収集と専門家(不動産会社、税理士など)への相談の上、慎重に判断してください。
不動産投資をゴールにした「二階建て資産形成術」とは
不動産投資が最強のゴールであるからといって、いきなり不動産に飛びつくのは得策ではありません。
そこで重要になるのが、金融投資と不動産投資を組み合わせた「二階建て資産形成術」です。
これが、当ブログが推奨する戦略の核心部分にあたります。
まず、NISAなどの金融投資(一階部分)を通じて、投資の基礎知識、リスク管理、市場との向き合い方といった「経験値」を安全に蓄積します。
同時に、着実に資産を増やし、不動産を購入するための「頭金」や「信用力」を作り出します。
これが「滑走路」です。
そして、十分な「滑走路」ができた段階で、不動産投資(二階部分)にステップアップし、レバレッジをかけて一気に資産規模を拡大し、安定した家賃収入というゴールを目指します。
このハイブリッドなアプローチこそが、会社員が「取り崩しの不安」から解放され、「本当の精神的余裕」を手に入れるための、最も合理的で再現性の高い戦略だと私は信じています。
「貯金だけでは、私たちの未来はあまりに厳しい」
この残酷な現実を直視し、「じゃあ、どうすればいいんだ!」と本気で思ったあなたへ。
この状況を打開し、資産形成を劇的に加速させるための具体的な設計図が、次の記事で解説する『二階建て資産形成術』です。
※この記事で「なぜ不動産がゴールなのか?」について、さらに深く知りたい方は、以下の記事もおすすめです。
資産3000万円の精神的余裕へ(まとめ)
この記事を読んで、資産3000万円という金額が「ゴール」ではなく、「本当の精神的余裕」を手に入れるための強力な「スタートライン」であることが伝われば幸いです。
NISAやインデックス投資によるセミリタイア(サイドFIRE)も、確かに魅力的な選択肢ですよね。
ただ、資産を取り崩しながら生活することへの不安が残る可能性も、私たちは同時に考える必要があるかと思います。
私が「二階建て資産形成術」をおすすめするのは、金融投資で築いたその「信用力」を使い、不動産という「安定収入を生む事業」を手に入れることで、その不安から解放される未来を目指せると信じているからです。
もちろん、これが唯一の正解ではありません。
大切なのは、ご自身の目標とリスク許容度に合わせて、あなた自身が納得のいく戦略を持つことです。
この記事が、あなたの未来を切り開く「最強のゴール」を見つける、なにかのきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
最後に、この記事の要点をまとめます。
- 資産3000万円は「アッパーマス層」と呼ばれ、全世帯の上位約1割の中間目標です。
- 達成すれば「老後の安心」「働き方の自由」「銀行の信用力」という3つの精神的余裕が生まれます。
- 生活レベルは「贅沢」にはなりませんが、「我慢」が減るというリアルな変化が期待できます。
- 3000万円で「完全リタイア」は困難ですが、「セミリタイア(サイドFIRE)」は現実的な選択肢となります。
- しかし、セミリタイアには「資産の食いつぶし」や「突発的な支出」といった不安が残ります。
- 資産を守るには「生活レベルを上げない」などの鉄則を守ることが重要です。
- NISAや株式投資(守り)だけでは「取り崩しの不安」の解消は難しいかもしれません。
- 不動産投資は「信用力(レバレッジ)」を活用し、資産規模を拡大する「攻め」の戦略です。
- 金融投資(滑走路)と不動産投資(ゴール)を組み合わせる「二階建て資産形成術」が、本当の精神的余裕への道だと、私は考えています。
