
「アパート経営はやめたほうがいい」と考えているあなたは、賃貸経営のリスクや失敗事例を耳にして不安を感じているのではないでしょうか?
確かに、アパート経営には空室リスクや修繕費の増加、ローン返済の負担など、慎重に検討すべき点が多く存在します。
一方で、正しい知識を持ち、しっかりとした準備を行えば、家賃収入を得ながら資産を築くことも可能です。
この記事では、アパート経営のメリット・デメリットをはじめ、賃貸経営が儲からない理由や、10年後・30年後に待ち受ける現実について詳しく解説します。
また、「アパート経営は何年で黒字化できるのか?」や「マンションオーナーの年収はどのくらい?」といった具体的な疑問にも答えていきます。
さらに、「家賃収入500万の手取りはいくらになるのか」「1億円の物件の家賃収入はいくらか」といった気になる収益のシミュレーションや、成功率と失敗率を左右する必要な準備についても詳しく紹介。
不動産投資に向いている人・向いていない人の特徴を押さえた上で、アパート経営のはじめかたと成功させるためのコツを解説していきます。
また、初期費用の目安やアパート1棟を新築する際の価格相場、「建てるのにいくらかかるのか?」といった資金計画に関する情報も網羅。
「アパート経営をやめたほうがいいのか?」それとも「正しく運用すれば成功できるのか?」迷っているあなたにとって、最適な答えを導き出すための情報を詰め込んだ記事です。
ぜひ最後まで読んでアパート経営を成功させてください。
記事のポイント
- アパート経営のメリットとデメリットを理解できる
- 賃貸経営が儲からない理由と収支の実態を把握できる
- 成功するために必要な準備やリスク管理の方法を学べる
- アパート経営の将来性や長期的な収益の見通しを知ることができる
アパート経営はやめたほうがいい?失敗リスクを回避する方法とは

- アパート経営はやめたほうがいい?失敗リスクを回避する方法とは?
- アパート経営のメリット・デメリット
- 賃貸経営儲からない理由とは?
- アパート経営 10年後・30年後の現実
- アパート経営は何年で黒字化できる?
- マンションオーナーは儲からない?年収はいくら?
- 家賃収入500万の手取りはいくらになる?
- 1億円の物件の家賃収入はいくら?
- 成功率と失敗率を左右する必要な準備
- 不動産投資に向いている人・向いていない人
- 初期費用はいくら?
- アパート1棟新築の値段は?建てるのにいくらかかる?
- アパート経営はじめかたと成功させるためのコツ
アパート経営とは?基礎知識と仕組み

アパート経営とは、土地を所有している人や投資家がアパートを建設・購入し、入居者から家賃収入を得る不動産投資の一つです。所有者は大家として、物件の管理や運営を行いながら、長期的な収益を目指します。
アパート経営の仕組みとして、まず物件を取得する方法には「新築」と「中古購入」があります。
新築の場合は土地購入や建築費用がかかり、初期投資が大きくなりますが、最新の設備やデザインを導入できる点が魅力です。
一方で、中古物件は初期費用を抑えられるものの、修繕やリフォームが必要になるケースがあります。
また、アパート経営には「自己管理」と「管理会社への委託」の2種類の運営方法があります。
自己管理の場合はオーナーが入居者対応や修繕を直接行うため、コストを抑えられますが、手間がかかる点がデメリットです。
一方、管理会社に委託すれば運営の負担は減りますが、管理費用が発生します。
収益は家賃収入が主な柱となり、安定した入居率を維持することが重要です。
しかし、空室が続くと収益が減少し、ローン返済や維持費の負担が増える可能性があります。そのため、立地選びや市場調査が成功のカギを握ります。
アパート経営は長期的な資産形成として魅力がありますが、リスク管理も欠かせません。初期費用や空室リスクを考慮し、慎重に計画を立てることが大切です。
「アパート経営はやめたほうがいい」賃貸経営が儲からないと言われる理由とは

アパート経営はやめたほうがいいと言われる理由は以下6つとなります。
理由6つ
- 初期投資が高く借入金が多くなりがち
- 空室リスクがある
- 家賃滞納・管理トラブルの可能性がある
- 建物の老朽化リスクと修繕費用
- 返済比率が甘いと赤字になる
- サブリース契約の落とし穴
理由1:初期投資が高く、借入金が多くなりがち
アパート経営は魅力的な投資の一つですが、「やめたほうがいい」と言われる理由の一つに、初期投資の高さと借入金の多さがあります。
まず、アパートを建設・購入するには多額の資金が必要です。
例えば、新築アパートを建てる場合、土地購入費、建築費、設計費、税金などがかかり、数千万円から1億円を超えることも珍しくありません。
中古アパートを購入する場合でも、物件価格に加え、リフォーム費用や耐震補強費が発生することがあります。
これに伴い、多くのオーナーは金融機関から融資を受けることになります。
日本政策金融公庫のデータによると、不動産投資向けの融資額は年々増加しており、特にサラリーマン投資家が多額の借入をするケースも増えています。
しかし、借入金が多くなると、金利上昇や収益の変動によるリスクが高まります。
さらに、ローン返済期間が長期にわたる点も注意が必要です。
アパートローンは通常20~35年の長期返済が一般的で、途中で収益が悪化すると、返済が困難になる可能性があります。
特に、経済状況の変化や入居率の低下が影響を及ぼすことがあり、計画的な資金管理が求められます。
このように、アパート経営には初期投資が大きく、長期的な借入リスクを抱える点がデメリットとなります。
慎重な資金計画と市場調査を行い、無理のない投資戦略を立てることが重要です。
理由2:空室リスクがある
アパート経営が「やめたほうがいい」と言われるもう一つの理由は、空室リスクが常に存在する点です。
アパート経営の収益は入居者からの家賃収入が主な柱となるため、空室が増えると収益が大きく低下します。
特に、以下のような要因によって空室リスクが高まることがあります。
立地条件の問題
立地によって入居需要は大きく左右されます。駅から遠い、周辺に生活利便施設が少ない、治安が悪い地域などの物件は、入居者が集まりにくい傾向にあります。
国土交通省の調査によると、地方の賃貸住宅市場では空室率が高くなりやすく、特に人口減少地域では空室リスクが深刻化しています。
築年数の影響
新築や築浅のアパートは人気がありますが、築年数が経過すると設備の老朽化やデザインの古さが理由で敬遠されがちです。
築20年以上のアパートでは、定期的なリフォームを行わなければ競争力が低下し、空室が長引く可能性があります。
周辺環境の変化
近隣に新しいマンションやアパートが建設されると、競争が激化し、既存物件の入居率が下がることがあります。
また、企業の撤退や大学の移転などで人口が減少すると、入居希望者が減り、空室が増えることもあります。
家賃設定の問題
周辺相場と比較して家賃が高すぎると、入居希望者が集まりにくくなります。
特に、近隣に似た条件のアパートが多い場合、価格競争に巻き込まれやすくなります。
家賃を下げれば入居率は上がる可能性がありますが、その分収益が減少するため、慎重な価格設定が求められます。
このように、アパート経営は空室リスクを伴うため、事前の市場調査や適切な物件選びが重要です。
入居者のニーズを把握し、立地や設備を工夫することで、リスクを抑える対策を講じる必要があります。
理由3:家賃滞納・管理トラブルの可能性がある
アパート経営では、入居者からの家賃収入が収益の中心となります。
しかし、家賃滞納や管理トラブルが発生すると、オーナーにとって大きな負担となります。
特に、家賃滞納が続けば安定した収益が確保できず、ローン返済や維持管理費の支払いにも影響を及ぼします。
近年、厚生労働省のデータによると、日本の相対的貧困率は約15%とされ、低所得層の増加により家賃滞納のリスクが高まっていると言われています。
また、「住宅市場動向調査」によれば、民間賃貸住宅における滞納率は約3~5%程度と報告されています。
これは100世帯のうち3~5世帯が家賃を期限内に支払っていないことを意味します。
さらに、入居者とのトラブルもアパート経営のリスクの一つです。
例えば、騒音問題、ゴミ出しのルール違反、近隣住民とのトラブルなどが発生すると、他の入居者の退去につながる可能性があります。
特に、トラブルの対応をオーナー自身で行う場合、精神的な負担が大きくなることも懸念されます。
こうしたリスクを回避するためには、家賃保証会社を利用する、管理会社に運営を委託する、入居審査を厳しくするなどの対策が必要です。
理由4:建物の老朽化リスクと修繕費用
アパートは時間の経過とともに老朽化し、定期的な修繕が必要になります。
特に、築20年以上の物件では設備の劣化が進み、修繕費用が増加する傾向にあります。
修繕を怠ると、入居者の快適性が損なわれ、空室リスクが高まるため、維持管理は不可欠です。
国土交通省の「住宅・土地統計調査」によると、日本の賃貸住宅の平均築年数は約30年となっており、築20年以上の物件が全体の約60%を占めています。
このデータからも、老朽化したアパートが市場に多く存在していることがわかります。
また、築年数が古い物件ほど修繕費がかさむ傾向があり、特に外壁塗装、防水工事、給排水設備の交換などは高額になりやすい項目です。
例えば、外壁の塗装工事は1回あたり100~300万円程度、屋上防水工事は50~200万円程度、給排水設備の交換には数百万円かかることもあります。
これらの修繕費用を見越して資金計画を立てないと、想定以上の出費により経営が厳しくなる可能性があります。
さらに、築古アパートは耐震性や断熱性の面でも新築と比べて劣ることが多いため、適切なメンテナンスを怠ると競争力を失い、空室率が高まる可能性があります。
長期的に収益を維持するためには、計画的な修繕とリフォームが必要となるため、資金の確保が重要です。
理由5:返済計画が甘いと赤字になる
アパート経営では、ローンを利用して物件を購入・建築するケースが多いため、適切な返済計画が求められます。
しかし、返済計画が甘いと、家賃収入だけではローン返済ができず、赤字経営に陥るリスクがあります。
金融機関の融資を利用する場合、一般的には20~35年の長期ローンを組むことになります。
しかし、固定金利と変動金利の選択や、金利の上昇リスクを考慮せずに借り入れると、将来的に返済額が増加し、経営を圧迫する可能性があります。
例えば、日本銀行の金融政策による金利引き上げが行われると、変動金利ローンの利息負担が増え、毎月の返済額が大幅に上昇することがあります。
また、空室リスクや修繕費用を考慮せずにローンを組むと、収益が計画通りにいかない場合に赤字になる可能性が高まります。
例えば、想定していた家賃収入が入らず、ローンの返済と管理費用を賄えなくなると、自己資金を切り崩して対応しなければならなくなります。
特に、家賃下落が続くと、収益性が低下し、最悪の場合、物件を売却しなければならない状況に追い込まれることもあります。
このようなリスクを回避するためには、融資を受ける際に返済比率(年間ローン返済額 ÷ 年間家賃収入)が高すぎないかを慎重に検討することが重要です。
一般的に、返済比率は50%以下が望ましいとされていますが、余裕を持って40%程度に抑えることが理想的です。
適切な返済計画を立てるためには、空室や修繕費用を考慮し、余裕を持った資金計画を立てることが必要です。
それでは、次にアパート経営はやめたほうがいいと言われるデメリットに対しての回避方法を解説していきます。
アパート経営のデメリットの回避策

先の章で解説した「アパート経営はやめたほうがいい」と言われるデメリットについて、回避方法を解説していきます。
初期投資が高く、借入金が多くなりがちについての回避策
アパート経営はまとまった資金が必要なため、多くの人が金融機関からの借入れに頼ります。
しかし、無理な融資を受けると返済が負担となり、経営が苦しくなることがあります。
回避策
・自己資金を十分に確保する:借入額を抑えることで、金利負担を軽減できます。自己資金として物件価格の20~30%を用意するのが理想的です。
・収益性の高い物件を選ぶ:物件選びの際、利回りが適正な範囲(一般的に表面利回り5~8%)であるかを確認し、収益が見込める物件を選びましょう。
・補助金や助成金を活用する:自治体によっては、耐震補強や省エネ住宅への助成金制度があります。国土交通省や地方自治体の助成金情報を調べ、活用することで初期コストを抑えられます。
空室リスクがある件についての回避策
空室が続くと家賃収入が得られず、ローン返済が厳しくなる可能性があります。
特に人口減少が進む地域では、賃貸需要の変動に注意が必要です。
回避策
・立地選びを慎重に行う:駅からの距離、周辺の賃貸需要、大学や企業の近くなど、長期的に入居者が見込めるエリアを選びましょう。国土交通省の「住宅・土地統計調査」では、地域ごとの空室率データが公表されていますので参考にできます。
・ターゲットに合わせた物件づくり:単身者向け、ファミリー向け、高齢者向けなど、ターゲット層に応じた間取りや設備を導入すると競争力が高まります。
・リフォームや設備投資を適切に行う:インターネット無料化、防音対策、宅配ボックスの設置など、入居者が求める設備を導入することで選ばれやすくなります。
家賃滞納・管理トラブルの可能性についての回避策
入居者が家賃を滞納した場合、収入が減るだけでなく、督促業務などの管理負担が増えます。
また、近隣住民とのトラブルが発生すると、退去やクレーム対応が必要になります。
回避策
・保証会社の利用を検討する:家賃保証会社を利用すれば、家賃の未払いリスクを軽減できます。最近では、契約時に保証会社の加入を必須とするケースが増えています。
・入居審査を厳格にする:収入や職業、過去の家賃滞納歴などをしっかり確認し、リスクの高い入居者を避けることが重要です。
・管理会社を活用する:賃貸管理会社に委託すると、滞納督促やトラブル対応を代行してくれるため、オーナーの負担が軽減されます。
建物の老朽化リスクと修繕費用についての回避策
アパートは年月が経つにつれて劣化し、大規模な修繕が必要になります。
特に築年数が20年以上経過すると、外壁や給排水設備の交換が必要になり、費用がかさむことがあります。
回避策
・定期的なメンテナンスを行う:小規模な修繕を計画的に実施することで、大規模修繕の負担を軽減できます。例えば、屋根の塗装や給排水管の清掃を定期的に行うことで、修繕費を分散できます。
・修繕積立金を確保する:将来の修繕費用に備えて、毎月一定額を積み立てることが重要です。目安として、年間家賃収入の5~10%を修繕費として確保するとよいでしょう。
・耐久性の高い建材を選ぶ:建築時に耐久性の高い外壁材や屋根材を使用することで、メンテナンスコストを抑えることができます。
返済計画が甘いと赤字になる事についての回避策
アパート経営では、家賃収入とローン返済のバランスを適切に管理しないと、収支が合わず赤字になることがあります。
特に金利変動や予想外の支出には注意が必要です。
回避策
・無理のないローン計画を立てる:金利の低い固定金利型ローンを選ぶ、繰上げ返済の計画を立てるなど、将来のリスクを考慮した借入を行いましょう。
・キャッシュフローを常に確認する:収入と支出のバランスを定期的にチェックし、無駄な支出を削減することが大切です。
・収入源を分散する:家賃収入以外にも、駐車場収入や広告収入などを確保することで、経営の安定性を高めることができます。
サブリース契約の落とし穴についての回避策
サブリース契約は、不動産会社がアパートを一括で借り上げ、家賃を保証する仕組みですが、契約内容によってはオーナーに不利な条件が含まれることがあります。
回避策
・契約内容を慎重に確認する:特に「家賃保証の見直し条項」がある場合、契約後に家賃が減額される可能性があるため、注意が必要です。
・解約条件を確認する:サブリース契約はオーナー側から解約しづらいことが多いため、契約前に解約条件をしっかり確認しておきましょう。
・複数の業者を比較する:サブリースを提供する不動産会社ごとに条件が異なるため、複数の会社の契約条件を比較し、最も有利なものを選ぶことが重要です。
アパート経営にはさまざまなデメリットがありますが、それぞれに対策を講じることでリスクを軽減することが可能です。
資金計画、物件選び、管理の工夫を行うことで、安定した経営につなげることができます。長期的な視点を持ち、リスクを見極めながら取り組むことが成功の鍵となるでしょう。
それでは、次にアパート経営のメリットについて解説していきたいと思います。
アパート経営のメリット4選(安定収入・節税・インフレ対策・生命保険代わり)
.jpg)
アパート経営にはリスクが伴う一方で、長期的に見ればかなり大きなメリットもあります。
特に、安定した収入源となることや、税制上の優遇を受けられる点が魅力です。
また、インフレ対策や生命保険の代わりとしての役割も果たすため、多くの投資家が資産運用の手段として選んでいます。
ここでは、アパート経営の4つのメリットについて詳しく解説します。
1. 安定収入を得られる
アパート経営の最大の魅力は、毎月安定した家賃収入が得られる点です。特に、立地の良い物件を所有している場合、長期間にわたって入居者が確保でき、安定したキャッシュフローを生み出します。
なぜ安定した収入が得られるのか?
・賃貸需要のあるエリアでは、長期的に住み続ける入居者が多く、空室リスクを抑えやすい。
・家賃収入は景気の影響を受けにくく、他の投資商品(株式など)と比べて価格変動が少ない。
・賃貸経営のサポートを行う不動産管理会社を利用することで、手間をかけずに運用できる。
実際のデータ:
国土交通省「住宅市場動向調査」によると、賃貸住宅の平均入居期間は約7~10年とされており、長期にわたって安定した収入が見込めることがわかります。
2. 節税効果がある
アパート経営では、税金の負担を軽減できる仕組みが整っています。不動産を所有することで、所得税や相続税などの軽減が可能になります。
どのような節税効果があるのか?
・所得税の軽減:減価償却費やローン金利、修繕費などを経費として計上できるため、課税所得を圧縮できる。
・固定資産税・都市計画税の軽減:住宅用地には税制上の優遇措置があり、固定資産税が最大1/6まで軽減される。
・相続税対策:現金や有価証券で相続するよりも、不動産として相続した方が評価額が低くなり、税負担を抑えられる。
具体例:
総務省「固定資産税に関する特例」によると、賃貸住宅の土地は、固定資産税評価額が1/6、都市計画税が1/3に軽減される措置が適用されるため、所有するだけでも税負担を軽減できます。
3. インフレ対策になる
インフレ(物価の上昇)が進むと、現金の価値が目減りする一方、不動産の価値や家賃は上昇する傾向があります。
そのため、アパート経営はインフレに強い資産運用の手段となります。
なぜアパート経営はインフレに強いのか?
・物価が上昇すると、建築費や土地価格も上昇し、不動産価値が高まる。
・インフレ時には、家賃も相場に応じて上昇しやすいため、実質的な収入の増加が期待できる。
・他の資産(現金や預金)はインフレによって価値が下がるが、不動産はその影響を受けにくい。
実際のデータ:
総務省の「消費者物価指数(CPI)」によると、日本の物価は長期的に緩やかに上昇しており、特に建築資材や人件費の高騰が続いています。
そのため、賃貸経営を行うことで、資産価値の維持や収入の増加が見込めます。
4. 生命保険代わりになる
アパート経営をする際、多くのオーナーが金融機関からのローンを利用します。
このとき、団体信用生命保険(団信)に加入することで、万が一の場合の保障を得ることができます。
なぜ生命保険代わりになるのか?
・ローン契約時に団信へ加入することで、オーナーが死亡・高度障害になった場合、ローンの残債が免除される。
・家族は無借金のアパートを相続でき、その後の家賃収入を生活資金として活用できる。
・一般的な生命保険と異なり、保険料として支払うのではなく、資産形成をしながら保障を得られる。
具体例:
金融機関の住宅ローンでは、団信の加入が義務付けられていることが多く、万が一の際に家族に負担をかけずに資産を残すことが可能です。
アパート経営は、安定した家賃収入が得られるだけでなく、節税効果やインフレ対策、さらには生命保険代わりとしてのメリットもあります。
しかし、適切な物件選びやリスク管理が重要です。これらのメリットを最大限に活かすためには、長期的な視点を持ち、計画的な経営を心がけることが成功の鍵となるでしょう。
アパート経営は何年で黒字化できる?

アパート経営の成功率は、立地条件や資金計画、管理の方法によって大きく異なりますが、一般的には黒字化までに数年かかると言われています。では、どのような要因が成功率に影響を与えるのでしょうか。
1. 初期投資と回収期間
一般的に、アパート経営では物件価格の回収に15~25年程度かかるとされています。
国土交通省の「不動産投資市場の動向」によると、アパート経営の年間利回り(表面利回り)は4~8%程度が相場とされています。
仮に利回り6%の物件であれば、単純計算で投資回収までに約16~17年かかることになります。
2. 黒字化までの目安
黒字化するまでの期間は、購入価格や家賃収入、ローンの返済額によって異なります。以下のようなケースが考えられます。
・自己資金を多く投入し、借入額を抑えた場合:5~10年
・フルローンで購入し、家賃収入で返済する場合:10~15年
・築古物件をリフォームし、低コストで運営する場合:3~7年
3. 失敗するケース
アパート経営が赤字に陥る主な原因として、以下のような要因があります。
・空室率が高く、想定通りの家賃収入が得られない。
・修繕費用の積立が不足し、予期せぬ出費で経営が苦しくなる。
・金利上昇によりローン返済負担が増える。
成功率を上げるためのポイント
・立地選びを慎重に行い、安定した需要のあるエリアを選ぶ。
・家賃保証や管理会社を活用し、空室リスクを最小限に抑える。
・余裕のある資金計画を立て、急な支出に対応できるよう準備する。
上記のポイントなど、アパート経営を早く黒字化するには色々な準備や工夫が必要となります。
以下よりさらに具体的なアパート経営を黒字化するガイドを見て参考にしてみて下さい。
① 収支計画をしっかり立てる
- 家賃相場を調査
→ 周辺の家賃相場を調べ、競争力のある家賃設定をする。 - 経費を洗い出す
→ 固定費(ローン・税金・保険)+変動費(修繕費・管理費)を把握する。 - 利益のシミュレーション
→ 「収入-支出」が黒字になるような経営計画を作る。
② 空室を減らす工夫をする
- ターゲット層を明確にする
→ 学生・単身者・ファミリー向けなど、地域の需要に合った部屋作りを意識。 - 魅力的な内装にする
→ 築年数が経っていても、壁紙・床・照明を変えるだけで印象がアップ。 - 広告を工夫する
→ 写真や動画付きの賃貸情報をネット掲載し、視覚的にアピール。 - 即入居キャンペーンを実施
→ 「フリーレント(最初の1ヶ月無料)」などの特典をつけて入居者を増やす。
③ コストを削減して利益を増やす
- 管理会社の見直し
→ 管理委託費が高すぎる場合は、他の管理会社と比較して見直す。 - 修繕費の削減
→ 大手業者だけでなく、地元の業者にも見積もりを取り、コストを抑える。 - 共用部分の電気代を節約
→ LED照明を導入することで、電気代を大幅に削減可能。 - 固定資産税の節税を考える
→ 税理士に相談し、節税対策をする(減価償却や固定資産税の見直し)
④ 賃貸トラブルを防ぐ
- 入居審査を厳しくする
→ 家賃滞納のリスクを減らすために、保証会社を利用する。 - 定期的に物件を点検する
→ 早めの修繕で大規模修繕のコストを抑える。 - 契約書を明確にする
→ 敷金・礼金・退去時の原状回復条件をしっかり明記。
⑤ 複数の収益源を作る
- 駐車場・駐輪場を有効活用
→ 余っているスペースを貸し出して収益を増やす。 - コインランドリー設置
→ 入居者向けにコインランドリーを設置し、追加収入を得る。 - 民泊・シェアハウスとして活用
→ 規制を確認したうえで、民泊や短期賃貸を活用する。
黒字化を早めるまとめ
- 収支計画をしっかり立てる(家賃相場・経費の把握)
- 空室を減らす工夫をする(内装改善・広告戦略)
- コスト削減を意識する(管理費・修繕費の見直し)
- 賃貸トラブルを防ぐ(入居審査・契約内容の明確化)
- 複数の収益源を作る(駐車場・コインランドリー・民泊)
初心者でも取り組みやすい方法なので、ぜひ試してみてくださいね!
マンションオーナーは儲からない?年収はいくら?

マンションオーナーの収益は、購入した物件の規模や立地、管理の仕方によって大きく変わります。
一般的に、賃貸マンションの年間家賃収入は数百万円〜数千万円の幅があります。ただし、これがそのまま手元に残る利益とは限りません。
例えば、金融機関のローンを利用している場合、毎月の返済額が家賃収入の多くを占めることになります。
また、固定資産税や管理費、修繕費などの支出も発生します。そのため、実際に手元に残る利益(純利益)は、年間で100万円〜500万円程度のケースが多いですが、中には年間1000万以上家賃収入を得ている方も多数いる現実もあります。
純利益については、運用方法を工夫することで収益を向上させることも可能で、例えば、築年数が古くなると空室率が上がるため、リノベーションを行い家賃を引き上げることで収益を維持できます。
また、管理会社に任せるのではなく、自主管理を行うことで管理コストを削減することも一つの手段です。
このように、マンションオーナーは「儲からない」と一概には言えません。
収支計画をしっかり立てることが成功のカギとなるでしょう。
家賃収入500万の手取りはいくらになる?

家賃収入が年間500万円の場合、実際に手元に残る手取り額は、ローンの返済額、税金、管理費、修繕費などの諸経費を差し引いた金額となります。
一般的に、不動産投資では家賃収入の50〜70%が経費として消えることが多いため、手取り額は~250万円程度になることが一般的です。
例えば、金融機関から借入をして物件を購入した場合、ローン返済額が年間200万円とすると、この時点で家賃収入500万円から200万円が差し引かれます。
加えて、固定資産税や都市計画税、管理費などが発生し、これが年間100万円程度かかると仮定すると、最終的な手取り額は200万円程度になります。
なお、固定資産税の負担額は、物件の評価額によって異なります。
総務省のデータによると、固定資産税率は1.4%(標準税率)となっており、物件の評価額が高いほど税額が増加します。
また、マンションの場合、共用部分の管理費や修繕積立金も考慮する必要があります。
つまり、家賃収入500万円でも、ローンの有無や物件の維持費によって手取り額は大きく変わるのです。支出を最小限に抑える工夫をすることで、より多くの収益を確保することができるでしょう。
1億円の物件の家賃収入はいくら?

1億円の物件から得られる家賃収入は、物件の利回りによって異なります。
一般的な賃貸物件の表面利回りは〜8%程度が目安とされており、この数値を基に計算すると、年間の家賃収入は〜800万円程となります。
例えば、表面利回り5%の物件であれば、1億円× 5% = 年間500万円の家賃収入が見込めます。
ただし、この金額はあくまで総収入であり、ここから管理費や税金、修繕費を引いた後の実質的な利益(実質利回り)は2〜4%程度になることが一般的です。
国土交通省の「不動産投資市場動向調査」によると、東京23区の利回りは平均4〜6%、地方都市では7%を超えるケースもあります。
ただし、利回りが高い物件は空室リスクが高くなる傾向があるため、立地や入居率の安定性を慎重に見極める必要があります。
このように、1億円の物件の家賃収入は利回りによって変動し、運用次第で収益の最大化が可能です。購入時には表面利回りだけでなく、実質的な運用コストや市場動向も考慮することが重要でしょう。
アパート経営はやめたほうがいい?失敗を防ぐための準備とは

- アパート経営はやめたほうがいい?失敗リスクを回避する方法とは?
- アパート経営のメリット・デメリット
- 賃貸経営儲からない理由とは?
- アパート経営 10年後・30年後の現実
- アパート経営は何年で黒字化できる?
- マンションオーナーは儲からない?年収はいくら?
- 家賃収入500万の手取りはいくらになる?
- 1億円の物件の家賃収入はいくら?
- 成功率と失敗率を左右する必要な準備
- 不動産投資に向いている人・向いていない人
- 初期費用はいくら?
- アパート1棟新築の値段は?建てるのにいくらかかる?
- アパート経営はじめかたと成功させるためのコツ
成功率と失敗率を左右する必要な準備
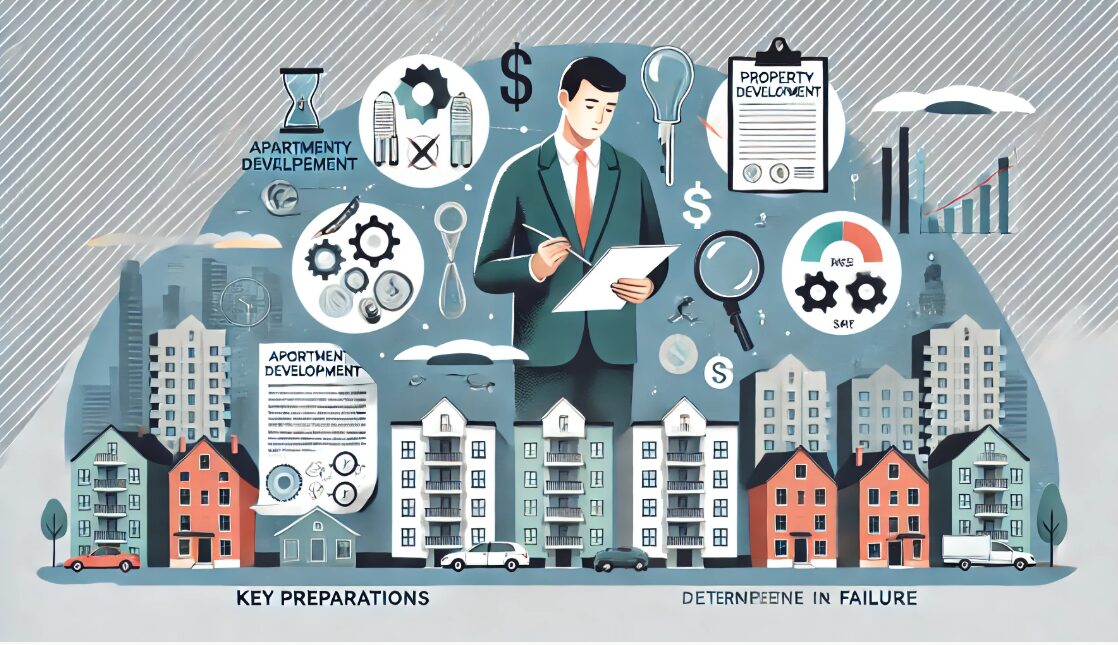
不動産投資で成功するか失敗するかは、事前の準備に大きく左右されると言えます。
特に、物件選びや資金計画、リスク管理を適切に行うことが重要です。
ここでは、成功率を高めるために必要な準備について解説します。
1. 物件の選定基準を明確にする
成功するためには、立地、賃貸需要、建物の状態、利回りなどの要素を慎重に分析する必要があります。
例えば、東京都心部の賃貸需要は高い傾向にありますが、価格が高いため利回りが低くなることもあります。一方、地方では利回りが高めですが、空室リスクが高まることが考えられます。
国土交通省の「住宅市場動向調査」によると、駅徒歩5分以内の物件は長期的に安定した入居率を維持しやすいとされています。
2. 綿密な資金計画を立てる
自己資金と借入のバランスを適切に考え、無理のない返済計画を作成することが求められます。
不動産投資では、ローンの返済額と家賃収入のバランスが成功のカギとなります。
たとえば、ローン返済比率が家賃収入の50%を超える場合、空室や家賃下落の影響を受けやすくなるため、余裕を持った計画が必要です。
3. 想定外のリスクに備える
不動産投資には、空室リスク、修繕費の発生、災害リスクなどさまざまなリスクが存在します。
これをカバーするために、空室率を考慮したキャッシュフロー管理、火災保険・地震保険への加入、修繕積立金の確保などが不可欠です。
例えば、賃貸市場では築年数が古くなるほど空室率が上昇する傾向にあるため、定期的なリフォームの計画も重要となります。
このように、物件選定・資金計画・リスク管理を徹底することが、不動産投資の成功率を高めるために必要な準備となります。
安易な判断で物件を購入するのではなく、長期的な視点で準備を進めることが求められます。
不動産投資に向いている人・向いていない人

不動産投資は誰にでも成功できるわけではなく、向いている人と向いていない人が明確に分かれる投資手法です。
特に、リスクを適切に管理できるかどうかが成功の大きな分かれ目になります。
不動産投資に向いている人
- 長期的な視点で投資ができる人
不動産投資は株式投資と異なり、短期間で大きな利益を得るのは難しいため、長期的に安定した収益を目指せる人が向いています。例えば、築10年以上の中古アパートを購入し、リフォームしながら賃貸経営をすることで、安定した家賃収入を得る戦略があります。 - リスク管理ができる人
予期せぬ空室や家賃の下落に備え、リスクヘッジを考えながら投資できる人が成功しやすい傾向にあります。例えば、賃貸需要が安定したエリアを選んだり、複数の物件を所有してリスクを分散したりすることが重要です。 - 金融知識がある人・学ぶ意欲がある人
住宅ローンや固定資産税、減価償却などの知識を持っている、または学ぶ意欲がある人は不動産投資に適しています。国税庁のデータによると、減価償却を適切に活用することで節税効果を高められるため、税務の知識も役立ちます。
不動産投資に向いていない人
- すぐに大きな利益を求める人
不動産投資は長期的な運用が基本であり、短期間で大きな利益を狙う人には不向きです。例えば、物件の価値が上昇するまで数年単位で待つ必要があり、短期的に売却益を狙うのは難しいケースが多いです。 - リスクを過小評価する人
空室リスクや災害リスクなどを考慮せず、楽観的に投資を進める人は失敗しやすい傾向があります。例えば、地方の高利回り物件に飛びついたものの、賃貸需要が低く空室が続いてしまうケースもあります。 - 自己資金が少なすぎる人
ある程度の自己資金がないと、突発的な修繕費や空室時の支出に耐えられず、経営が厳しくなる可能性があります。日本政策金融公庫のデータによると、不動産投資を始める際の自己資金は平均500万円程度とされており、ある程度の資金力が求められます。
このように、不動産投資に向いている人は長期的な視点を持ち、リスク管理ができる人です。
一方で、短期的な利益を求めたり、自己資金が不足していたりする人には向いていません。
不動産投資を始める前に、自分の性格や資金状況と照らし合わせて慎重に判断することが大切です。
初期費用はいくら?

アパート経営を始める際には、物件購入費用以外にも多くの初期費用がかかるため、事前に資金計画を立てることが重要です。
初期費用には、自己資金、融資関連費用、諸経費などが含まれます。
1. 自己資金の目安
一般的に、金融機関のアパートローンでは物件価格の20%~30%程度の自己資金が求められます。
例えば、1億円のアパートを購入する場合、2,000万円~3,000万円程度の自己資金が必要になります。
また、金融機関によってはフルローン(全額融資)も可能ですが、金利が高くなるため、長期的な収支に注意が必要です。
2. 融資関連の初期費用
融資を受ける場合、以下のような費用が発生します。
- 融資手数料(借入額の1%~3%)
- 印紙税(契約書に応じて1万円~6万円)
- 抵当権設定費用(登記費用+司法書士報酬)
例えば、7,000万円を借りる場合、融資手数料だけで70万円~210万円かかることになります。
3. 購入時の諸費用
物件購入時には、以下の諸費用が発生します。
- 不動産取得税(固定資産税評価額の3~4%)
- 仲介手数料(物件価格の3%+6万円)
- 登記費用(登録免許税+司法書士報酬で20万円~50万円)
- 火災保険・地震保険(年間10万円~50万円)
例えば、1億円の物件を購入する場合、諸費用だけで500万円~1,000万円程度かかるケースもあります。
4. 運転資金
アパート経営では、購入時の初期費用だけでなく、当初の運転資金も確保する必要があります。
特に、空室が発生した際のリスクを考え、6ヶ月分のローン返済額+修繕費用を準備しておくと安心です。
例えば、月々のローン返済が30万円の場合、最低でも180万円~300万円の運転資金を持っておくことが推奨されます。
初期費用の総額の目安
以上を踏まえると、1億円のアパートを購入する際の初期費用の目安は以下のようになります。
| 費用項目 | 目安金額 |
|---|---|
| 自己資金(20%) | 2,000万円 |
| 融資手数料 | 70万円~210万円 |
| 仲介手数料 | 300万円 |
| 登記費用 | 20万円~50万円 |
| 火災保険・地震保険 | 10万円~50万円 |
| 不動産取得税 | 300万円~400万円 |
| 運転資金 | 180万円~300万円 |
| 合計 | 2,880万円~3,810万円 |
このように、アパート経営の初期費用は物件価格の20%~30%が目安となります。自己資金を十分に準備した上で、余裕のある資金計画を立てることが成功のポイントです。
アパート1棟新築の値段は?建てるのにいくらかかる?

アパート1棟を新築する際の費用は、建築コスト、土地代、付帯工事費などの要素によって大きく変わります。
エリアや建築規模、仕様によっても異なりますが、一般的な価格帯を把握することで、具体的な計画を立てやすくなります。
1. 建築費の目安
建築費は、構造や仕様によって単価が変動します。国土交通省の「建設工事費データ」によると、2023年時点での一般的なアパート建築費は以下の通りです。
- 木造アパート(2階建て):坪単価 60万円~90万円
- 鉄骨造アパート(3階建て以上):坪単価 80万円~130万円
- RC造アパート(鉄筋コンクリート造):坪単価 100万円~150万円
例えば、延床面積200㎡(約60坪)の木造アパートを建てる場合、建築費は約3,600万円~5,400万円程度が目安となります。
2. 土地代の考え方
アパートを建てるには、適切な土地の取得も必要です。土地価格は地域によって大きく異なりますが、一般的には土地価格=年間家賃収入の5倍~10倍程度が目安とされています。
例えば、年間家賃収入が800万円見込めるエリアでは、土地価格は4,000万円~8,000万円程度が想定されます。ただし、地方都市の場合はこれより安く、東京都心部ではさらに高額になる傾向があります。
3. その他の費用
アパート建築には、建築費や土地代以外にも以下のような費用がかかります。
- 設計費・施工管理費(建築費の5~10%程度)
- 水道・ガス・電気の引き込み工事(100万円~300万円)
- 外構工事(駐車場やフェンスなど)(200万円~500万円)
- 登記費用・税金(登録免許税、不動産取得税など)
これらを含めると、土地込みでの総費用は1億円~2億円になることも珍しくありません。
このように、アパート1棟の新築にはさまざまな要素が関係するため、事前に細かい費用を試算することが大切です。
アパート経営始め方と成功させるためのコツ
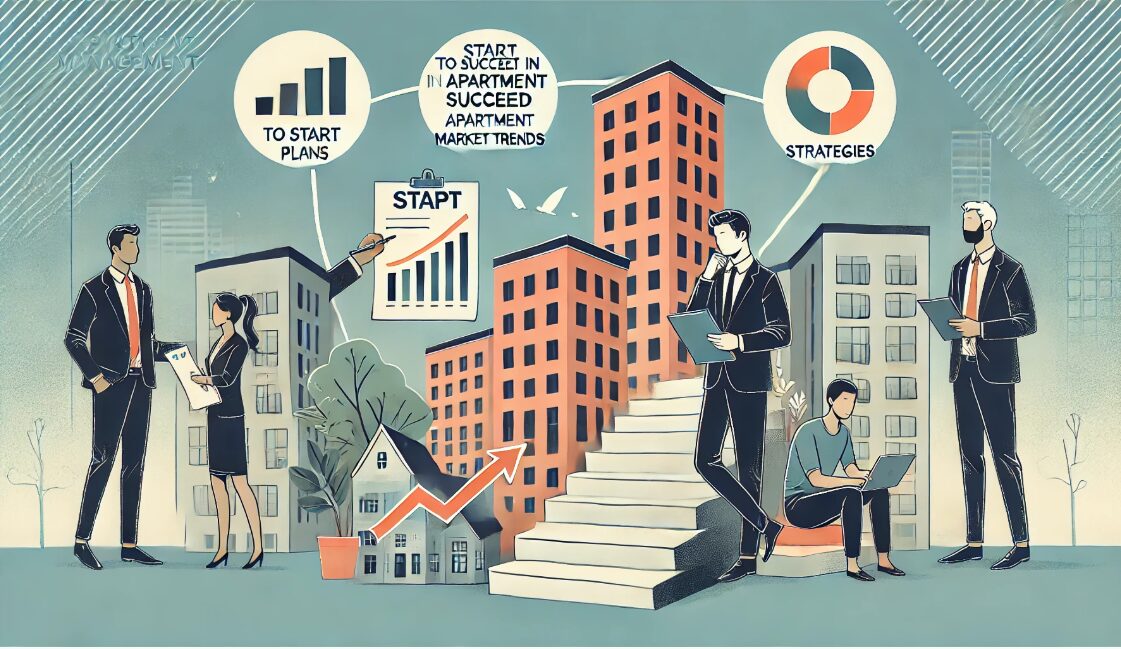
アパート経営を始めるには、以下のステップを順番に進めることが大切です。
① 目的と予算を決める
まず、アパート経営の目的を明確にします。
老後の資産形成、節税対策、副収入の確保など、人によって異なります。目的によって、必要な初期資金や運営方針が変わるため、具体的な計画を立てることが大切です。
また、予算を決める際は、「自己資金」と「借入可能額」の両方を把握し、無理のない投資額を設定します。
金融機関のアパートローンは、物件価格の70%~80%を融資するのが一般的ですが、自己資金は物件価格の20%程度を準備しておくと安心です。
② 物件の種類を選ぶ
アパート経営には、大きく分けて新築・中古・一棟・区分の選択肢があります。
- 新築アパート:初期修繕のリスクが低いが、価格が高め
- 中古アパート:購入費用は抑えられるが、修繕費がかかる可能性あり
- 一棟アパート:家賃収入が安定しやすいが、初期費用が高い
- 区分アパート:少額投資が可能だが、管理の自由度が低い
それぞれの特徴を踏まえて、自分に合った物件タイプを選ぶことが重要です。
③ 立地選びと市場調査
アパート経営で最も重要なのが立地です。
国土交通省の「住宅市場動向調査」によると、駅から徒歩10分以内の物件は入居率が高い傾向があります。
また、大学や商業施設、企業が多いエリアは需要が安定しやすいです。
市場調査のポイント:
- 人口動向(人口が増えている地域か?)
- 賃貸需要(単身者向けかファミリー向けか?)
- 競合物件の家賃相場(適正な家賃設定ができるか?)
④不動産会社の選定
信頼できる不動産会社を選ぶことが、良い物件に出会うための第一歩です。不動産会社を選ぶ際は、以下のポイントを確認すると良いでしょう。
- 実績が豊富か:過去の取引実績や顧客の評判を調べる。
- 管理業務のサポートがあるか:購入後の管理体制も考慮する。
- 市場の知識が豊富か:ターゲットエリアの賃貸市場に詳しいかを確認する。
また、国土交通省の「不動産業者登録情報」などを利用し、免許の有無や過去のトラブル歴を調べるのも有効です。
⑤資金調達とローンの選択
アパート経営をする際、多くの人は金融機関からの借り入れを利用します。融資を受けることで自己資金の負担を軽減し、効率的に資産を増やすことが可能になります。
アパートローンを扱う金融機関は多数ありますが、それぞれ融資条件が異なります。主な借入先には以下のようなものがあります。
- 都市銀行・地方銀行:金利が低いが、審査が厳しい。
- 信用金庫・信用組合:地域密着型で、比較的融資を受けやすい。
- 日本政策金融公庫:政府系金融機関で、創業支援融資などがある。
金融機関ごとの金利や融資条件を比較し、最適な借入先を選ぶことが重要です。
金融機関の審査では、以下の点が重視されます。
- 自己資金:一般的に物件価格の20~30%の自己資金が必要。
- 信用情報:過去の借入履歴や信用スコアが審査対象となる。
- 物件の収益性:家賃収入がローン返済を上回るかが重要。
また、日本銀行の「貸出動向調査」を参考にすると、最新の融資状況や金利動向を把握することができます。
⑥ 売買契約の流れ
物件契約の一般的な流れは以下の通りです。
- 重要事項説明の確認:宅地建物取引士が物件の詳細やリスクを説明する。
- 売買契約の締結:売主と買主が合意し、契約書を交わす。
- 手付金の支払い:契約時に、売買価格の5~10%程度を支払う。
契約時の注意点
- 契約書の内容確認:特に、引き渡し時期や違約金の条項に注意。
- 修繕履歴のチェック:建物の過去の修繕状況を確認する。
- ローン特約の有無:ローンが通らなかった場合の対応を明記する。
⑦管理会社に物件の管理を委託する
契約が完了したら、物件の引き渡しを受け、賃貸経営の準備を進めます。
物件の引き渡し
- 現地確認:契約時の状態と変わりがないかチェックする。
- 設備の動作確認:給排水・電気・ガスの動作を確認する。
- 鍵の受け取り:すべての鍵が揃っているか確認する。
管理体制の構築
賃貸経営をスムーズに行うためには、管理体制を整えることが重要です。
- 管理会社の選定:賃貸管理を委託する場合、実績のある会社を選ぶ。
- 入居者募集:不動産会社を通じて、広告や募集を行う。
- トラブル対応:修繕やクレーム対応のルールを決めておく。
このように、物件の引き渡し後は迅速に管理体制を整えることが、安定したアパート経営につながります。
次に、アパート経営で安定した収益を得るためには、以下のようにいくつかの重要なポイントがあります。
⑧空室対策を徹底する
アパート経営の最大のリスクは「空室」です。空室率が上がると収益が減り、ローン返済に影響を与える可能性があります。
- ターゲット層に合った設備投資(Wi-Fi無料、宅配ボックス、防犯カメラ)
- 家賃設定を適正にする(競合物件より高すぎると空室が増える)
- 定期的なリフォーム・リノベーション(築年数に応じた改善)
③ 税金対策を考える
アパート経営では、固定資産税、不動産取得税、所得税などの税金が発生します。
税理士と相談しながら、青色申告や減価償却を活用し、節税対策を行うことが大切です。
④ 長期的な修繕計画を立てる
築年数が経過すると、外壁塗装や屋根の補修、設備の交換が必要になります。
これらの修繕費を事前に積み立てることで、大きな出費にも対応しやすくなります。
⑤ 収支計画を常に見直す
アパート経営は長期的な投資です。購入時の収支計画だけでなく、年に1回は収支を見直し、収益が落ちていないか確認することが成功のカギとなります。
Q&A

Q1. アパート経営はやめたほうがいいと言われるのはなぜ?
A: アパート経営は空室リスクや修繕費の負担、ローン返済のリスクがあるため「やめたほうがいい」と言われることがある。 しかし、適切な物件選びや資金計画を行えば、安定した家賃収入を得ることが可能です。
Q2. アパート経営を成功させるためのポイントは?
A: 立地選びを慎重に行い、賃貸需要のあるエリアを選ぶことが重要。また、収支計画を綿密に立て、管理会社を活用することでリスクを抑えながら経営を安定させることができる。
Q3. 初心者がアパート経営を始める際に注意すべき点は?
A: 物件購入前に市場調査を行い、想定される家賃収入と支出のバランスを確認すること。また、空室リスクや修繕費に備え、一定の自己資金を確保しておくことが成功のカギとなる。
アパート経営はやめたほうがいい?についての総括
アパート経営は、しっかりと準備をすれば初心者でも成功しやすい投資手法です。
物件選び、資金計画、管理体制を整えることで、安定した家賃収入を得ることが可能になります。
また、成功のポイントは空室対策、適切な管理、税金対策、修繕計画を怠らないことです。
これらを意識しながら、長期的に安定した経営を目指しましょう。
総括をまとめると以下となります。
アパート経営はやめたほうがいいか結論
- 正しい知識を持てばアパート経営は安定した資産形成の手段となる
- 立地選びを慎重に行えば空室リスクを大幅に下げられる
- 管理会社を活用すれば手間を減らし、効率的な経営が可能になる
- 家賃保証会社を利用すれば家賃滞納リスクを回避できる
- 節税対策を適切に行えば収益を最大化できる
- 修繕費を計画的に積み立てれば急な支出に困ることはない
- 賃貸需要の高いエリアを選べば長期的に安定した収益が得られる
- 競争力のある物件を選べば資産価値の下落を防げる
- ローン返済比率を適切に設定すれば赤字経営を避けられる
- 収支計画を綿密に立てれば経営の安定性が高まる
- ターゲット層に合わせた設備投資で入居率を向上させられる
- 複数の収益源を確保すればリスクを分散できる
- 団体信用生命保険を活用すれば家族に資産を残せる
- 賃貸市場の動向を定期的に分析すれば適切な家賃設定ができる
- 適切なリフォームやリノベーションで築年数が経っても魅力を維持できる
アパート経営は「やめたほうがいい」と言われることもありますが、実際には準備と知識次第で成功している方も大多数いるのが現実です。
慎重な準備と継続的な情報収集を心がけ、後悔のない不動産投資を目指しましょう。
