
「最近、周りで投資を始める人が増えたけど、投資する人が増えるとどうなるんだろう?」と感じていませんか。
新NISAの開始などをきっかけに、日本でも投資への関心が高まっています。
実際に、投資する人が増えたことで、日本における投資している人の割合は変化しつつあります。
特に20代や30代の投資している人の割合は増加傾向にあり、40代や50代といった世代を含めた年代別の動向も注目されています。
一方で、依然として高い投資しない人の割合も存在し、投資しない人との格差が問題視されることもあります。
多くの人が、このまま投資しないとやばいと感じながらも、実際に投資するとどうなるのか、例えばアップル上場時に100万円投資していたらいくらになったのか、具体的なイメージが持てずにいるかもしれません。
この記事では、投資人口の増加が社会や個人にどのような影響を与えるのか、多角的な視点から分かりやすく解説します。
この記事は、そもそも「本当に投資しない方がいい人の特徴」とは何か、という大きなテーマを解説した特集の一部です。
記事のポイント
- 日本で投資する人が増えている現状と年代別の割合
- 投資が社会や経済に与えるプラスの影響
- 個人が投資で得られる具体的なリターンとリスク
- 投資をしない場合に起こりうる資産格差の問題
投資する人が増えるとどうなる?社会の変化
投資に参加する人が増えることは、個人の資産形成だけでなく、社会全体にもさまざまな影響を及ぼします。
この章では、日本における投資人口の現状をデータで確認しながら、投資の普及が社会や経済にどのような変化をもたらすのかを解説します。
- 投資する人が増えた日本の投資割合
- 20代で投資している人の割合
- 30代で投資している人の割合
- 40代で投資している人の割合
- 50代で投資している人の割合
- 年代別で見る投資している人の割合
- 投資しない人の割合と今後の動向
- 実際に投資するとどうなるのか
- アップル株に100万円投資していたら
- 投資しないとやばいと言われる理由
- 投資しない人と生まれる格差
- まとめ:投資する人が増えるとどうなるか
投資する人が増えた日本の投資割合
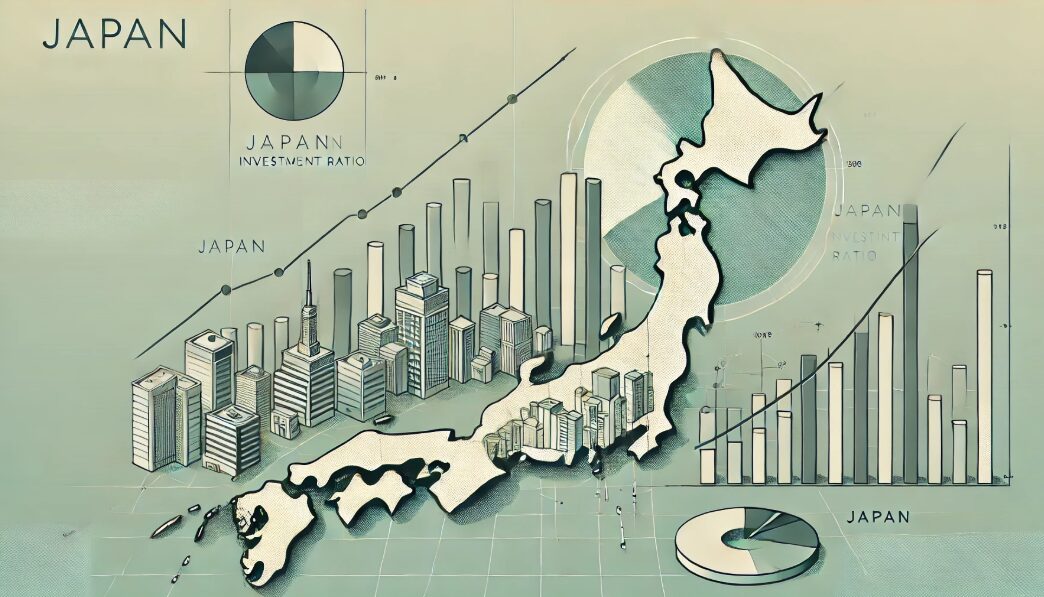
近年、日本において投資を行う人の割合は着実に増加しています。
特に2024年から始まった新NISA制度は、多くの人にとって投資を始める大きなきっかけとなりました。
日本証券業協会の「証券投資に関する全国調査(2024年)」によると、株式や投資信託などの有価証券を保有している人の割合は24.1%に達し、前回調査(2021年)の19.6%から4.5ポイント上昇しました。
これは、国民のおよそ4人に1人が何らかの投資を行っていることを示しています。
この背景には、長引く低金利で預貯金では資産が増えないことや、物価上昇による現金の価値目減りへの懸念があります。
「貯蓄から投資へ」という政府の方針も、この流れを後押ししていると考えられます。
投資が一部の富裕層だけのものではなく、一般の人々にとっても身近な資産形成の手段として認識され始めているのです。
20代で投資している人の割合

特に若年層である20代の投資への関心は非常に高まっています。
金融広報中央委員会の調査(令和5年)によると、20代の金融資産保有世帯のうち、株式や投資信託を保有している割合は合計で29.7%(株式13.2%、投資信託15.2%、債券1.3%)に上ります。
また、ある民間企業の調査では、20代の約3割がすでに投資を始めているという結果も出ています。
20代は、SNSを通じて投資情報を手軽に入手できる環境にあり、少額から始められる投資サービスやポイント投資の普及も、投資へのハードルを大きく下げています。
将来の年金への不安や、早い段階から資産形成を始めたいという堅実な考え方が、20代の投資参加率を高めている主な理由と言えるでしょう。
30代で投資している人の割合

30代は、キャリアの安定と共に収入が増加し、本格的な資産形成を考え始める世代です。
前述の金融広報中央委員会の調査では、30代の金融資産保有世帯における株式・投資信託の保有割合は、合計で33.18%(株式18.13%、投資信託15.05%)と、20代を上回っています。
この世代は、結婚、住宅購入、子どもの教育資金など、将来の大きなライフイベントを具体的に意識し始めます。
そのため、預貯金だけではなく、より効率的に資産を増やす手段として投資を選択する人が増える傾向にあります。
NISAやiDeCoといった税制優遇制度を積極的に活用し、将来に向けた長期的な資産形成の中核を担う世代であると分析できます。
40代で投資している人の割合

40代は、社会的にも家庭的にも責任が増し、老後資金を現実的な問題として捉え始める時期です。
データを見ると、40代の投資割合はさらに高まります。
金融広報中央委員会の調査によれば、40代の金融資産保有世帯の株式・投資信託の保有割合は、合計で27.8%です。
40代は、20代や30代と比較して収入や貯蓄額が多い傾向にあり、より大きな金額を投資に回すことが可能です。
子どもの教育費のピークを迎える家庭も多い一方で、退職までの期間を逆算し、iDeCoやNISAを活用して老後資金の準備を本格化させる人が多いのが特徴です。
リスク許容度に応じて、安定的な投資信託と成長が期待できる株式を組み合わせるなど、多様な運用スタイルが見られます。
50代で投資している人の割合

50代は、定年退職が視野に入ってくる世代であり、これまでの資産形成の集大成と、退職後の生活を見据えた運用がテーマとなります。
金融広報中央委員会の調査によると、50代の金融資産保有世帯における株式と投資信託の保有割合は、合わせて27.2%です。
この世代の投資の特徴は、退職金などまとまった資金をどう運用するかという点にあります。
これまでの積立投資を継続しつつも、リスクを抑えた運用へのシフトを考える人が増えます。
一方で、退職までのラストスパートとして、積極的に資産を増やそうとする動きも見られます。
50代の投資判断は、退職後の生活設計に直結するため、より慎重かつ計画的なアプローチが求められる年代です。
年代別で見る投資している人の割合

これまでのデータをまとめると、年代ごとに投資との関わり方が変化していく様子が見て取れます。
| 年代 | 投資割合(株式・投信・債券の合計) | 特徴 |
| 20代 | 29.7% | 将来への備えとして少額から開始。SNSでの情報収集が活発。 |
| 30代 | 33.18% | ライフイベントを意識し、NISAやiDeCoを活用した本格的な資産形成へ。 |
| 40代 | 27.8% | 老後資金を現実的に捉え、ある程度の資金力で多様な運用を行う。 |
| 50代 | 27.2% | 退職を見据え、資産の守りと攻めを両立させる運用が中心。 |
このように、若い世代ほど投資への関心が高く、年代が上がるにつれて資産全体に占める投資の割合は一定のレベルを保ちつつも、その目的やスタイルが変化していきます。
全世代を通じて投資への参加が広がっていることが、現代の日本の特徴です。
投資しない人の割合と今後の動向
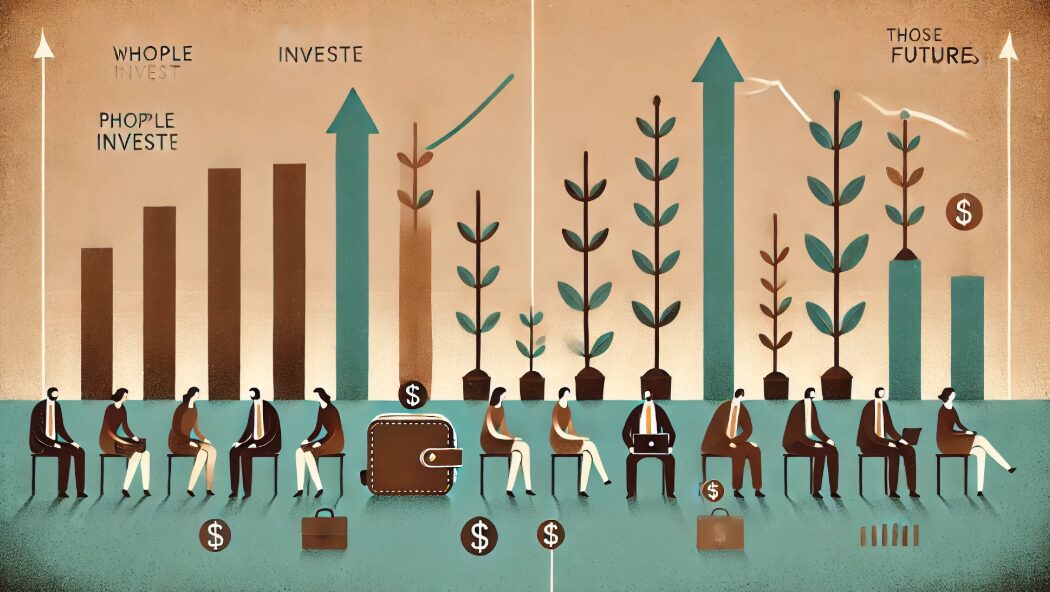
投資する人が増えている一方で、依然として日本の家計金融資産の半分以上は現金・預金で占められており、投資をしていない人が多数派であるという事実は変わりありません。
前述の通り、投資をしている人の割合は約24%であり、残りの約76%は投資を行っていない計算になります。
しかし、この状況は今後変化していくと予想されます。
インフレの常態化により「預金だけでは資産が目減りする」という認識が広まっていること、そして2022年度から高校の授業で金融教育が必修化されたことなどが、長期的に投資人口を押し上げる要因となるでしょう。
将来的には、投資が特別なものではなく、誰もが当たり前に行う資産形成の手段の一つとして定着していく可能性が高いと考えられます。
投資する人が増えるとどうなる?個人の資産
投資の普及は、社会だけでなく、私たち一人ひとりの資産にも大きな影響を与えます。
ここでは、投資を始めることで個人にどのような変化が起こるのか、また、投資をしない場合に考えられるリスクについて具体的に見ていきます。
- 投資する人が増えた日本の投資割合
- 20代で投資している人の割合
- 30代で投資している人の割合
- 40代で投資している人の割合
- 50代で投資している人の割合
- 年代別で見る投資している人の割合
- 投資しない人の割合と今後の動向
- 実際に投資するとどうなるのか
- アップル株に100万円投資していたら
- 投資しないとやばいと言われる理由
- 投資しない人と生まれる格差
- まとめ:投資する人が増えるとどうなるか
実際に投資するとどうなるのか

投資を始めると、自分のお金が社会や経済の動きと連動して増えたり減ったりするようになります。これは、預貯金にはない大きな特徴です。
投資から得られる利益には、主に二つの種類があります。
一つは「インカムゲイン」で、株式の配当金や投資信託の分配金のように、資産を保有しているだけで定期的にお金が入ってくる仕組みです。
もう一つは「キャピタルゲイン」で、購入した株式や投資信託が値上がりした時に売却することで得られる利益を指します。
もちろん、投資にはリスクが伴います。
購入した資産の価値が下落し、元本割れを起こす可能性もあります。
しかし、適切な商品を選び、長期的な視点で運用を続けることで、預貯金の金利をはるかに上回るリターンを得て、資産を大きく増やせる可能性があります。
投資は、自分のお金に働いてもらい、将来の豊かさを作るための有効な手段なのです。
アップル株に100万円投資していたら

投資が持つ可能性を理解するために、世界的な企業であるAppleを例に考えてみましょう。
もし、Appleが株式を上場した1980年12月に100万円を投資し、現在まで保有し続けていたら、その資産はいくらになっているでしょうか。
Appleはこれまでに何度も株式分割を行っていますが、それらをすべて考慮して計算すると、驚くべき結果が見えてきます。
上場当時の分割調整後株価は1株あたり約0.1ドルでした。2025年9月現在、株価は1株200ドルを超えています。
単純計算すると、株価は約2,000倍になったことになります。
つまり、40年以上前に投資した100万円は、為替レートの変動を考慮したとしても、数十億円という莫大な資産に成長していた可能性があるのです。
これは極端な成功例ですが、将来性のある企業に長期的に投資することで、人生を変えるほどのリターンを得られる可能性があることを示しています。
投資しないとやばいと言われる理由

「投資しないとやばい」という言葉が使われる背景には、主に「インフレ」と「社会保障制度の不確実性」という二つの大きな問題があります。
インフレは、物価が上昇し、お金の価値が下がることです。
年2%のインフレが続くと、現在100万円の価値は10年後には約82万円に、20年後には約67万円にまで実質的に目減りしてしまいます。
現在の超低金利では、銀行に預けているだけではこの目減りを防ぐことはできません。
さらに、少子高齢化が進む日本では、将来的に公的年金の給付額が減少していくことが予想されます。
かつてのような手厚い退職金も期待できなくなりつつあります。
これらのことから、給与収入と預貯金だけで将来の生活を支えることが難しくなっているのです。
自らの資産をインフレから守り、将来のために育てていく手段として、投資の必要性が高まっています。
投資しない人と生まれる格差

インフレが進み、経済が成長する局面では、投資をする人としない人の間で資産の格差が拡大しやすくなります。
企業の利益が伸びれば株価は上昇し、不動産の価値も上がる傾向にあります。
株式や投資信託、不動産などの資産を保有している人は、経済成長の恩恵を受けて資産を増やすことができます。
一方で、資産の大部分を現金や預金で保有している人は、インフレによって資産価値が実質的に目減りするだけで、経済成長の恩恵を受けることができません。
この差は、1年や2年ではわずかかもしれませんが、10年、20年という長い期間で見ると非常に大きなものになります。
資産から得られる収益(資産所得)の有無が、将来の経済的な豊かさを大きく左右する時代になっており、「投資をしない」という選択自体が、相対的に貧しくなるリスクをはらんでいるのです。
まとめ:投資する人が増えるとどうなるか
- 投資する人が増えると企業は資金調達しやすくなる
- 新しい技術やサービスが生まれ経済が活性化する
- 個人の資産が増えれば消費が活発になる効果も期待できる
- 日本では新NISAをきっかけに投資する人が増えている
- 特に20代や30代の若年層の参加が目立つ
- それでもまだ国民の約4分の3は投資をしていない
- 長期投資は大きなリターンを生む可能性がある
- Apple株の例は将来性ある企業への投資の夢を示している
- 投資をしないとインフレで資産が実質的に目減りするリスクがある
- 貯蓄だけで資産を守ることが難しい時代になっている
- 投資の有無が将来の資産格差につながる可能性がある
- 投資は社会と個人の両方にプラスの影響を与え得る
- リスクを正しく理解し少額から始めることが大切
- 将来の資産形成のために投資は有効な選択肢の一つ
- この記事を機に自分に合った資産形成を考えてみよう
より広い視点から『投資しない方がいい人の特徴と、それでも始めるべき理由』について体系的に理解したい方は、ぜひこの記事も合わせてご覧ください。
