
みんなの年金とは?仕組みを分かりやすく解説
- みんなの年金の主な特徴と仕組み
- みんなの年金のメリット・デメリットを徹底比較
- みんなの年金の評判・口コミを調査
- みんなの年金はどんな人におすすめ?
- みんなの年金は怪しい?安全性と注意すべきリスク
- みんなの年金の口座開設から投資を始めるまでの全手順
- 実施中のキャンペーン情報
- まとめ:みんなの年金の評価と利用の判断ポイント
- みんなの年金に関するよくある質問
「みんなの年金」とは、多くの投資家から集めた資金を元手にして不動産へ投資し、そこから得られた利益を分配する「不動産クラウドファンディング」と呼ばれるサービスの一つです。
その名の通り、公的年金だけでは将来の生活に不安を感じる方々が、年金を補う安定した収入源を作ることをコンセプトに設計されています。
投資家はインターネットを通じて手軽に不動産投資を始められ、賃貸や売却によって生まれた収益の一部を配当として受け取ることが可能です。
最低10万円から始められるため、大きな初期費用を準備することなく資産運用への第一歩を踏み出せます。
都市部のマンションに投資できる不動産クラウドファンディング
みんなの年金が投資対象として主に選んでいるのは、東京、名古屋、大阪、福岡といった日本の主要都市に位置するワンルームマンションです。
都市部の不動産は、地方に比べて人口が集中しやすく賃貸需要が高いため、不動産価格が下がりにくいという特徴を持っています。
このように、比較的価値が安定している資産に投資することで、投資家が元本を失うリスクをできる限り低減させる運用方針をとっています。
不動産投資に興味はあるものの、物件選びやリスク管理に不安を感じる初心者の方でも、安心して参加しやすい仕組みと言えるでしょう。
運営会社「株式会社ネクサスエージェント」について
このサービスを運営しているのは、株式会社ネクサスエージェントです。
同社は2016年1月に設立されたベンチャー企業で、不動産事業とITを組み合わせた事業で成長を続けています。
みんなの年金の運営は2021年からですが、会社全体としては順調に業績を拡大しており、2023年には売上高151億円を達成しました。
不動産特定共同事業の許可も正式に取得しているため、信頼性の高い企業が運営しているサービスであることが分かります。
以下に詳細な会社概要をまとめます。
| 項目 | 情報 |
| 運営会社 | 株式会社ネクサスエージェント |
| 代表者 | 代表取締役社長 岩田 講典 |
| 設立 | 2016年1月27日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 所在地 | 【東京本社】 〒105-0004 東京都港区新橋1丁目11番7号 新橋センタープレイス3F 【大阪本店】 〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 22階 |
| 許可番号 | ・宅建免許番号:国土交通大臣(2)第9256号 ・賃貸住宅管理業登録番号:国土交通大臣(2)第2536号 ・不動産特定共同事業:大阪府知事 第14号 |
みんなの年金の主な特徴と仕組み
みんなの年金が多くの投資家から支持される背景には、投資家の資産を守るためのいくつかの特徴的な仕組みが存在します。
特に、元本割れのリスクを低減するための工夫が複数導入されており、サービスの安全性を高める重要な要素となっています。
ここでは、主な3つの仕組みについて解説します。
投資家の元本割れリスクを低減する「優先劣後システム」
みんなの年金では、投資家の資産を守るために「優先劣後システム」という仕組みを採用しています。
これは、不動産投資の出資金を、投資家からの「優先出資」と、運営会社であるネクサスエージェントからの「劣後出資」の二つに分ける方法です。
もし不動産の価値が下落して損失が出た場合、まずは劣後出資者である運営会社の出資金から損失が補填されます。
例えば、劣後出資の割合が30%であれば、30%までの損失は運営会社が負担するため、投資家の元本には影響がありません。
このように、投資家が優先的に保護されることで、元本割れのリスクが大きく低減されています。
資産を分別管理する「信託保全」を採用
投資家から預かった資金の管理方法も、安全性を高める上で重要なポイントです。
みんなの年金では、まだ投資されていない資金を「信託銀行」の口座で管理する「信託保全」という方法を取り入れています。
これは、運営会社の自社の資産と、投資家から預かった資金を明確に分けて管理する仕組みです。
このため、万が一運営会社が倒産するような事態に陥ったとしても、信託銀行に預けられている投資家の資金は法的に保護されます。
投資家は安心して資金を預けることができるでしょう。
空室リスクに備える「家賃保証」付きファンド
みんなの年金のファンドの中には、インカム型(家賃収入を原資とするタイプ)において「家賃保証」が付いているものがあります。
これは、投資対象の物件を第三者が一括で借り上げ、実際の入居者の有無にかかわらず、毎月一定の賃料を保証する契約のことです。
この仕組みにより、投資期間中に空室が発生したり、家賃の滞納が起きたりしても、安定した収益を確保しやすくなります。
ただし、すべてのファンドに家賃保証が付いているわけではないため、投資を検討する際には、ファンドの詳細ページで保証の有無を確認することが大切です。
みんなの年金のメリット・デメリットを徹底比較

どのような投資にも、良い面と注意すべき点が存在します。
みんなの年金も例外ではなく、その特徴を正しく理解した上で、自身の投資スタイルに合っているかを判断することが重要です。
ここでは、主なメリットとデメリットを比較しながら解説していきます。
【メリット①】想定利回り8%と高い利回りが期待できる
みんなの年金の最大の魅力は、その利回りの高さにあります。
サービス開始以来、募集されるファンドの想定利回りは一貫して8.0%に設定されています。
これは、一般的な不動産クラウドファンディングの平均利回りである3~5%や、不動産投資信託(J-REIT)の平均利回り約4.3%と比較しても、非常に高い水準です。
さらに、これまでの実績では実質平均年利回りが8.4%となっており、想定を上回るリターンを達成したケースもあります。
高い収益性を求める投資家にとって、これは大きなメリットと言えるでしょう。
【メリット②】2ヶ月に1回と早いペースで分配金がもらえる
多くの不動産クラウドファンディングでは、分配金が運用期間の最後に一括で支払われることが少なくありません。
一方、みんなの年金は、2ヶ月に1回という早いペースで分配金を受け取ることができます。
公的年金が偶数月に支給されることを踏まえ、みんなの年金の分配金は奇数月に支払われるように設計されています。
これにより、年金受給者の方は毎月安定した収入を得られるようになり、投資の効果を定期的に実感しやすいという利点があります。
【メリット③】運用実績として元本割れや配当遅延がゼロ
投資を行う上で、過去の実績は信頼性を判断する重要な材料となります。
みんなの年金は、2021年3月のサービス開始以来、現在までに運用が終了した全てのファンドにおいて、元本割れや配当の遅延が一度も発生していません。
もちろん、これは将来の安全を保証するものではありませんが、100件以上のファンドを運用してきた中で、着実に利益を還元し続けているという事実は、投資家にとって大きな安心材料になるはずです。
【メリット④】手間をかけずに都市部の不動産へ分散投資できる
実物の不動産投資では、物件の管理や修繕、固定資産税の支払いなど、多くの手間と時間が必要になります。
しかし、みんなの年金を利用すれば、そのような面倒な手続きはすべて運営会社に任せることが可能です。
投資家は、一度出資すればあとは分配金が入金されるのを待つだけで済みます。
複数の物件で構成されるファンドに投資すれば、手軽にリスクを分散させながら、価値の安定した都市部の不動産へ投資できる点も魅力です。
【デメリット①】最低投資額が10万円からと高めに設定されている
手軽に始められる一方で、最低投資額が10万円からというのは、人によっては少しハードルが高いと感じるかもしれません。
他の不動産クラウドファンディングサービスの中には、1万円から投資できるものも多く存在します。
このため、「まずは少額から試してみたい」と考えている初心者の方にとっては、最初の投資に少し勇気が必要になる可能性があります。
ある程度まとまった余裕資金がある方向けのサービスと言えるでしょう。
【デメリット②】応募前に投資資金を入金しておく必要がある(事前入金形式)
みんなの年金でファンドに応募するためには、あらかじめ専用の投資口座へ資金を入金しておく必要があります。
これを「事前入金形式」または「投資口座預託形式」と呼びます。
この形式では、抽選に外れたり、先着順の募集に間に合わなかったりした場合でも、その資金は口座に残り続けます。
次の投資機会まで資金が拘束されてしまうため、資金効率を重視する投資家にとってはデメリットと感じられる点です。
【デメリット③】みんなの年金の出金手数料はいくら?他社との比較
専用口座から自分の銀行口座へ資金を払い戻す際には、出金手数料が発生します。
手数料の金額は、PayPay銀行への出金であれば55円、その他の銀行では160円程度とされています。
月1回まで無料といったサービスも他社には存在するため、手数料がかかる点をデメリットと捉える声もあります。
ただ、手数料自体は比較的に安価な設定であり、頻繁に出金を繰り返さない限り、大きな負担にはならないでしょう。
みんなの年金の評判・口コミを調査

実際にサービスを利用している投資家は、みんなの年金をどのように評価しているのでしょうか。
ここでは、インターネット上に見られる良い評判と、注意が必要な悪い評判の両方を取り上げ、利用者のリアルな声を紹介します。
良い評判・口コミ
良い口コミとして最も多く見られるのは、やはり利回り8%という収益性の高さに対する満足の声です。
安定して高いリターンが得られる点を評価する意見が目立ちます。
また、2ヶ月に1回の分配金が予定通りに入金されることへの安心感や、投資家登録の審査が迅速で、思い立ってからすぐに投資を始められたという手際の良さを評価する声も挙がっています。
さらに、問い合わせに対する運営会社の対応が丁寧で早かったというコメントもあり、サポート体制への信頼も伺えます。
悪い評判・口コミ
一方で、悪い評判として指摘されがちなのが、人気の高さゆえの投資のしにくさです。
特に先着方式のファンドでは、「募集開始から1分で完売してしまった」という口コミもあり、投資したくてもなかなかできないという不満の声が見られます。
前述の通り、事前に入金が必要なシステムについても、資金が長期間拘束される点をデメリットとして挙げる意見があります。
当選してから入金する形式に変更してほしい、という要望も少なくありません。
早期償還で利益が上振れる可能性も
口コミの中には、「早期償還」に関するものも多く見られます。
早期償還とは、予定されていた運用期間よりも早くファンドの運用が終了し、元本と分配金が投資家に返還されることです。
例えば、運用期間12ヶ月の予定が8ヶ月で終了した場合、通常は分配金も期間に応じて減額されます。
しかし、みんなの年金では、当初予定していた12ヶ月分の分配金を支払ってくれたという事例が報告されており、結果的に年間の利回りが予想以上に高くなったと喜ぶ声がありました。
これは投資家にとって嬉しいサプライズと言えるでしょう。
みんなの年金はどんな人におすすめ?
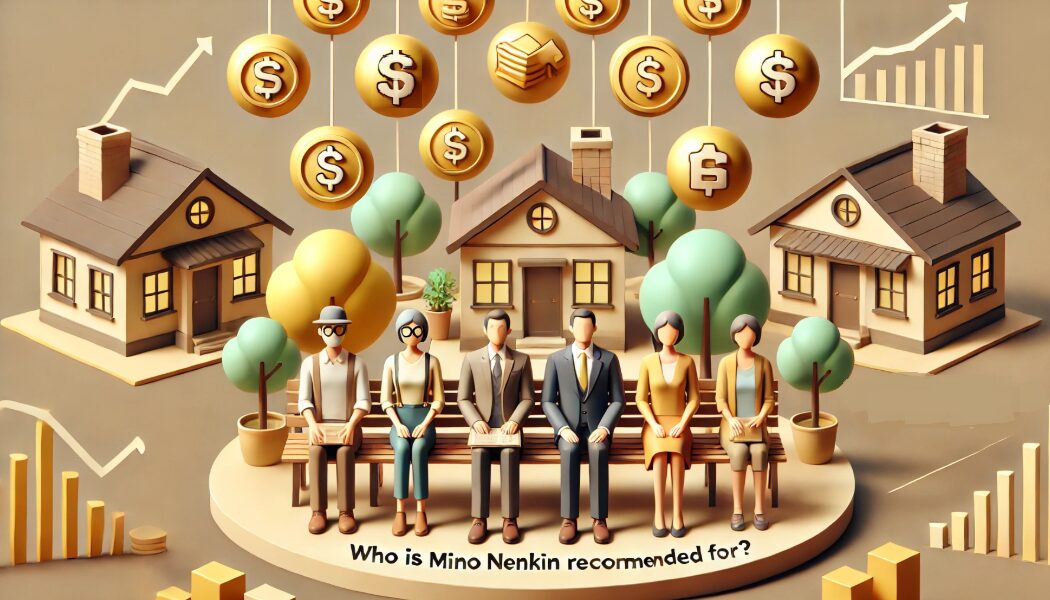
ここまで解説してきた特徴やメリット・デメリットを踏まえると、みんなの年金は特定のニーズを持つ方に特に適したサービスと言えます。
ここでは、どのような方にみんなの年金がおすすめできるのか、具体的な人物像を3つのタイプに分けて紹介します。
安定した分配金収入を定期的に得たい方
公的年金の受給額だけでは将来が不安な方や、毎月の収入にもう一つプラスアルファを加えたいと考えている方には、みんなの年金が非常に適しています。
2ヶ月に1回という定期的な分配金の支払いは、安定したキャッシュフローを生み出します。
特に、公的年金を受け取っている方であれば、年金が支給されない奇数月に分配金が入ることで、毎月の収入を平準化させることが可能です。
8%以上の高い利回りを求める方
現在の低金利時代において、銀行預金の金利はごくわずかです。
資産をただ寝かせておくだけでなく、積極的に増やしていきたいと考える、利回り重視の投資家にもみんなの年金はおすすめです。
想定利回り8%という業界でもトップクラスの水準は、資産形成のスピードを加速させる可能性があります。
もちろんリスクは伴いますが、それを理解した上で高いリターンを狙いたい方にとって魅力的な選択肢となるでしょう。
10万円以上の余裕資金をまとめて投資できる方
みんなの年金の最低投資額は10万円です。
このため、日々の生活に影響を与えない範囲で、少なくとも10万円以上の余裕資金を準備できる方が対象となります。
少額からコツコツ投資するというよりは、ある程度まとまった資金を一度に投じて、効率的に収益を得たいと考える方に合ったサービスです。
みんなの年金は怪しい?安全性と注意すべきリスク
高い利回りを提示するサービスに対して、「何か裏があるのではないか」「怪しいサービスではないか」と不安に感じるのは自然なことです。
ここでは、みんなの年金の安全性について検証するとともに、投資する上で必ず知っておくべきリスクについて解説します。
「みんなの年金は怪しい・詐欺」という噂は本当?理由を解説
「みんなの年金は怪しい」という声が聞かれる主な理由は、その利回りの高さにあります。
平均3~5%の業界において8%という数字は、確かにうますぎる話に聞こえるかもしれません。
しかし、これは詐欺ではありません。
運営会社のネクサスエージェントが、これまでの不動産事業で培ったノウハウを活かし、高い収益を見込める物件を厳選しているからこそ実現可能な数字です。
前述の通り、これまでに元本割れや配当遅延が一度もないという実績や、信託保全といった投資家保護の仕組みが、その安全性を裏付けています。
【リスク①】みんなの年金で元本割れは起こる?実績とリスクを解説
まず理解しておくべき最も重要な点は、みんなの年金は元本が保証された商品ではないということです。
これは法律で定められており、あらゆる投資に共通する原則です。
これまでの実績として元本割れは一度もありませんが、将来的に不動産市況が大きく悪化した場合や、予期せぬ災害が発生した場合には、元本が割れてしまう可能性はゼロではありません。
ただし、優先劣後システムにより、一定の損失までは運営会社が負担するため、リスクは低減されています。
【リスク②】人気が高く、募集開始後すぐに完売してしまうことがある
これは嬉しい悲鳴とも言えますが、人気の高さから、投資したくてもできないケースが頻発しています。
特に募集金額が少ないファンドでは、募集開始からわずか数分で上限に達してしまうことも珍しくありません。
このため、投資の機会を逃さないためには、公式サイトをこまめにチェックし、募集開始のタイミングを事前に把握しておく必要があります。
確実に投資できるとは限らない点は、あらかじめ理解しておくべきでしょう。
【リスク③】原則として運用期間中の中途解約はできない
一度ファンドに投資すると、運用期間が満了するまで資金を引き出すことは原則としてできません。
公式サイトには「やむを得ない事情がある場合のみ可能」と記載されていますが、これは非常に限定的なケースであり、基本的には解約できないと考えておくべきです。
急にお金が必要になった場合でも、すぐに現金化することは難しいです。
投資は、あくまで当面使う予定のない余裕資金で行うことが大前提となります。
【リスク④】不動産特有のリスク(天災・価格変動など)
不動産クラウドファンディングも不動産投資の一種であるため、不動産そのものが持つリスクと無関係ではありません。
例えば、大規模な地震や水害といった自然災害によって、投資対象の物件が損害を受ける可能性があります。
また、景気の変動によって不動産価格や家賃が下落すれば、想定通りの収益が得られなくなることも考えられます。
これらのリスクは、都市部の物件を選ぶことである程度は低減されていますが、完全に避けることはできません。
みんなの年金の口座開設から投資を始めるまでの全手順

みんなの年金で投資を始めるには、まず会員登録と投資家登録を済ませる必要があります。
手続きはすべてオンラインで完結し、それほど難しいものではありません。
ここでは、実際に投資を始めるまでの流れを4つのステップに分けて解説します。
step
1公式サイトで無料会員登録を行う
まずは、みんなの年金の公式サイトにアクセスし、「新規登録」ボタンから手続きを開始します。
メールアドレスとパスワードを設定すると、登録したメールアドレスに確認メールが届きます。
メールに記載されたURLをクリックして、基本的な会員情報を入力すれば、仮登録は完了です。
step
2投資家登録と本人確認を申請する
次に、より詳細な個人情報を入力して、投資家登録を行います。
氏名、住所、年収、投資経験などの必要事項を入力した後、本人確認の手続きに進みます。
運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類をスマートフォンのカメラで撮影し、アップロードすることで申請は完了します。
審査は比較的早く、数日で結果が通知されることが多いようです。
step
3払戻口座を登録し、投資口座へ入金する
投資家登録が承認されたら、マイページにログインし、分配金や償還金を受け取るための自分の銀行口座(払戻口座)を登録します。
この払戻口座を登録すると、自動的に投資資金を入金するための専用口座(投資口座)が開設されます。
ファンドに応募する前に、この専用口座へ投資したい金額を入金しておきましょう。
step
4希望するファンドに応募する
入金が完了したら、あとは募集中のファンドの中から投資したいものを選び、応募するだけです。
ファンドには先着方式と抽選方式がありますので、募集要項をよく確認してください。
無事に出資が確定すれば、運用が開始され、あとは定期的に分配金が支払われるのを待つことになります。
実施中のキャンペーン情報
投資を始めるなら、少しでもお得に始めたいと思うのは当然のことです。
ここでは、みんなの年金で実施されているキャンペーンや、ポイントサイトを経由した登録の可否について、最新の情報をまとめました。
みんなの年金で実施中のキャンペーン情報
2025年10月現在、みんなの年金では新規会員登録などを対象とした大規模なキャンペーンは実施されていないようです。
過去には登録キャンペーンを行っていたこともあるため、今後新たにキャンペーンが開始される可能性はあります。
最新の情報については、公式サイトを定期的に確認することをおすすめします。
お得な機会を逃さないように、こまめにチェックしておくと良いでしょう。
ポイントサイト経由での登録は可能か?
以前は、一部のポイントサイトにみんなの年金の広告が掲載されており、サイト経由で登録することでポイントが付与されることがありました。
しかし、現在では主要なポイントサイトでの案件掲載は終了しているようです。
こちらもキャンペーンと同様に、将来的に再び掲載が再開される可能性もあります。
ポイントサイトを頻繁に利用される方は、登録を検討するタイミングで、念のため各サイトを確認してみるのが良いかもしれません。
まとめ:みんなの年金の評価と利用の判断ポイント
この記事では、不動産クラウドファンディングサービス「みんなの年金」について、その仕組みからメリット・デメリット、利用者の評判やリスクまで、多角的に解説してきました。
結論として、みんなの年金は「業界トップクラスの利回り8%」と「2ヶ月に1回の定期的な分配」、「元本割れゼロという優れた運用実績」を両立させた、信頼性の高いサービスと言えます。
特に、公的年金を補う安定収入源を確保したい方や、高い収益性を求める投資家にとって、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。
一方で、「最低投資額10万円」というハードルの高さや、「人気が高く投資機会を得にくい」というデメリットも存在します。
これらの特徴を十分に理解し、ご自身の余裕資金の範囲内で、長期的な視点を持って取り組むことが大切です。
この記事が、あなたの投資判断の一助となれば幸いです。
みんなの年金に関するよくある質問
最後に、みんなの年金に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。
Q1. 元本は保証されていますか?
いいえ、元本は保証されていません。
これは出資法という法律で定められており、みんなの年金に限らず、すべての不動産クラウドファンディングサービスで共通です。
ただし、優先劣後システムにより、投資家の元本が保護されやすい仕組みになっています。
Q2. 確定申告は必要ですか?損失が出た場合、損益通算はできますか?
みんなの年金で得た分配金は「雑所得」に分類されます。
会社員の方で、給与以外の所得(雑所得など)の合計が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
分配金は源泉徴収(20.42%)された後の金額が振り込まれます。
また、雑所得は他の所得(給与所得など)と損益通算することはできません。
Q3. 「みんなで大家さん」とは関係がありますか?
いいえ、全く関係ありません。
「みんなの年金」と「みんなで大家さん」は名前が似ていますが、運営会社もサービスの仕組みも異なる、全く別のサービスです。
混同しないように注意しましょう。
Q4. 手数料について詳しく教えてください。
投資家が負担する主な手数料は、投資口座への「入金手数料(利用する銀行による)」と、投資口座からの「出金手数料(PayPay銀行なら55円、他行なら160円程度)」です。
ファンドへの出資自体に手数料はかかりません。
Q5. 中途解約は本当にできませんか?
原則として、運用期間中の中途解約はできません。
公式サイトでは「やむを得ない事由がある場合」に限り可能とされていますが、これは非常に例外的なケースです。
一度投資した資金は、運用期間が終了するまで動かせないものと考えておく必要があります。
