
大東建託でのアパート経営を検討する中で、「本当に儲かるのか」という疑問や不安を感じていませんか。
大東建託のアパート経営の評判を調べると良い話ばかりではなく、アパート経営はやめたほうがいいという意見や、実際に大東建託のアパート経営で失敗した事例も目にします。
特に、35年一括借り上げのデメリットや、大東建託の一括借り上げのからくりについては、多くの方が知りたい点でしょう。
実際に、家賃保証がこんなはずではなかったというオーナートラブルは少なくなく、中には30年一括借り上げを巡る大東建託との訴訟にまで発展するケースもあります。
最悪の場合、オーナーが破産したり、オーナー死亡後に家族が問題を抱えたりすることも。
この記事では、大東建託のオーナーの収入や経営費用といった実情から、アパート経営の出口戦略まで、アパート経営を成功に導くための情報を網羅的に解説します。
この記事でわかる事
- 大東建託の一括借り上げ(サブリース)の仕組みと潜むリスク
- 実際に報告されているオーナートラブルや失敗の具体例
- アパート経営で安定した収益を上げるための成功戦略
- 経営が困難になった場合の具体的な出口戦略(売却など)
【結論】アパート経営は「仕組み」を知らないとカモにされます
大東建託の仕組みを知ることは重要ですが、それ以上に大切なのは「業者に依存せずに利益を出す投資戦略」を持つことです。
サブリースに頼らず、会社員の信用力を武器に堅実に資産を築く「ハイブリッド投資戦略」の全貌をまずは知ってください。
業者任せの経営から卒業しましょう。
大東建託一括借り上げのからくりとアパート経営成功の鍵
- まずは大東建託アパート経営の評判
- 大東建託の一括借り上げのからくり
- 35年一括借り上げのデメリットとは
- 家賃保証が「こんなはずでは」となる訳
- 大東建託のオーナートラブルと訴訟事例
- 大東建託のアパート経営失敗パターン
- アパート経営はやめたほうがいいのか
- 儲かる?オーナーの収入と経営費用
- オーナーが破産や死亡するリスク
- アパート経営に必須の出口戦略
- 大東建託一括借り上げのからくりとアパート経営成功
まずは大東建託アパート経営の評判
大東建託は、賃貸住宅管理戸数で長年業界トップクラスを維持しており、その知名度と実績はアパート経営を考える多くの方にとって大きな安心材料です。
テレビCMなどでもおなじみであり、全国に広がる支店網によるサポート体制も強みと言えるでしょう。
実際に、「大手だから安心」「管理を全て任せられるので楽」といった良い評判は少なくありません。
特に、土地を所有しているものの活用方法に悩む方や、不動産経営の初心者にとっては、企画提案から管理運営まで一貫してサポートしてくれる体制は魅力的に映ります。
しかし、その一方でインターネット上では、経営の失敗談やオーナートラブルに関するネガティブな評判も多く見受けられるのが実情です。
評判を鵜呑みにするのは危険
良い評判と悪い評判が混在しているのは、オーナー一人ひとりの状況や担当者、物件の立地条件が大きく異なるためです。
成功事例がある一方で、計画通りに進まず苦労しているオーナーがいることも事実として認識し、多角的な視点から情報を集めることが重要になります。
「一括借り上げだから安心」という言葉の裏にあるリスクを理解せず始めてしまうと、後々大きな問題に発展しかねません。
だからこそ、表面的な評判だけでなく、契約の仕組みや具体的なリスクについて深く理解する必要があります。
大東建託の一括借り上げのからくり

大東建託が提供する「一括借り上げ」は、一般的にサブリース契約と呼ばれるものです。
この仕組みを正しく理解することが、アパート経営のリスクを把握する第一歩となります。
サブリース契約は、オーナー、大東建託(サブリース会社)、そして入居者の三者間で成り立っています。
まず、大東建託がオーナーからアパート全室を一括で借り上げます。
そして、大東建託が貸主となって、実際に入居者を募集し、個別の賃貸借契約を結ぶのです。
この仕組みにより、オーナーには以下のようなメリットが生まれます。
メリット
- 空室の有無にかかわらず、毎月一定の賃料(保証賃料)が大東建託から支払われる
- 入居者募集や家賃滞納の督促、クレーム対応などの管理業務を全て任せられる
保証賃料の源泉はどこか?
重要なのは、大東建託がオーナーに支払う保証賃料は、実際に入居者から得られる家賃が源泉であるという点です。
大東建託は、入居者から受け取る家賃総額から、自社の手数料(一般的に10%~20%程度)や経費を差し引いた金額を、オーナーへの保証賃料として支払います。
つまり、オーナーが直接入居者に貸す場合よりも、手取りの収入は少なくなるのが基本です。
この「手数料」が、管理業務を代行してもらう対価であり、大東建託の利益となります。
一見すると、空室リスクがなくなり安定収入が得られる魅力的なシステムですが、この構造自体が後のトラブルの原因となる可能性を秘めているのです。
35年一括借り上げのデメリットとは
「35年間、家賃収入が保証される」という言葉は、非常に魅力的です。
しかし、この長期保証にはいくつかの重要な注意点、つまりデメリットが存在します。
これらを理解せずに契約すると、将来的に大きなリスクを背負うことになりかねません。
① 家賃保証額は永続ではない
最大のデメリットは、契約当初の家賃保証額が35年間固定されるわけではないという点です。
大東建託の契約では、一般的に最初の10年間は賃料が固定され、その後は5年ごとに見直しが行われます。
周辺の家賃相場の下落や建物の老朽化、空室率の上昇などを理由に、大東建託から賃料の減額を要求される可能性があるのです。
この減額交渉に応じなければ、契約を解除されるケースもあります。
② オーナーからの解約が非常に難しい
サブリース契約は、法律上「賃貸借契約」にあたります。
日本の借地借家法では、借主(この場合は大東建託)の権利が強く保護されています。
そのため、貸主であるオーナー側から一方的に契約を解除することは、正当な事由がない限り非常に困難です。
たとえより良い条件の管理会社を見つけたり、物件を売却したくなったりしても、簡単には解約できないという縛りが生じます。
法的な壁は想像以上に厚いのが現実です。判例を知らずに交渉すると痛い目を見ます。
③ 免責期間が存在する
契約内容によっては、「免責期間」が設けられている場合があります。
これは、新築後の入居者募集期間や、入居者が退去してから次の入居者が決まるまでの一定期間、家賃保証が適用されないというものです。
この期間中の収入はゼロになるため、収支計画に影響を与える可能性があります。
これらのデメリットは、契約書に記載されていますが、営業担当者から十分に説明されないケースも考えられます。
「35年一括借り上げ」という言葉の安心感に惑わされず、契約書の細かい条項までしっかりと確認し、リスクを正確に把握することが極めて重要です。
家賃保証が「こんなはずでは」となる訳

「空室があっても家賃が保証されるはずだったのに、話が違う」。
このような事態に陥るオーナーは少なくありません。
なぜ「こんなはずでは」という状況が生まれるのでしょうか。
その主な理由は、家賃保証額の減額リスクに対する認識の甘さにあります。
前述の通り、家賃保証額は定期的に見直されます。
大東建託が家賃の減額を提案する主な根拠は、「周辺の家賃相場の変動」です。
アパート経営を始めると、競合となる物件は常に現れます。
特に地方では、大東建託自身が近隣に新しいアパートを次々と建設することで、供給過多となり家賃相場全体が下落する一因となるケースも見られます。
「あなたの物件の入居率を維持するためには、家賃を下げざるを得ません。
そうでなければ、もっと新しくて家賃の安い近隣の物件に入居者が流れてしまいますよ」
このように説明され、減額に応じざるを得ない状況に追い込まれることがあります。
また、営業担当者が提示する当初の収支シミュレーションにも注意が必要です。
シミュレーションは、あくまで現時点での家賃相場に基づいた予測であり、将来の家賃下落リスクが十分に織り込まれていないことがあります。
楽観的なシミュレーションを鵜呑みにしてしまうと、数年後に家賃が減額された際、ローンの返済計画が大きく狂い、キャッシュフローが悪化。
赤字経営に陥ってしまうのです。
「家賃保証」という言葉は、「収入の保証」とイコールではありません。
あくまで「空室リスクをサブリース会社が負う」という意味合いが強く、事業全体の収益性が保証されるわけではないことを、肝に銘じておく必要があります。
大東建託のオーナートラブルと訴訟事例
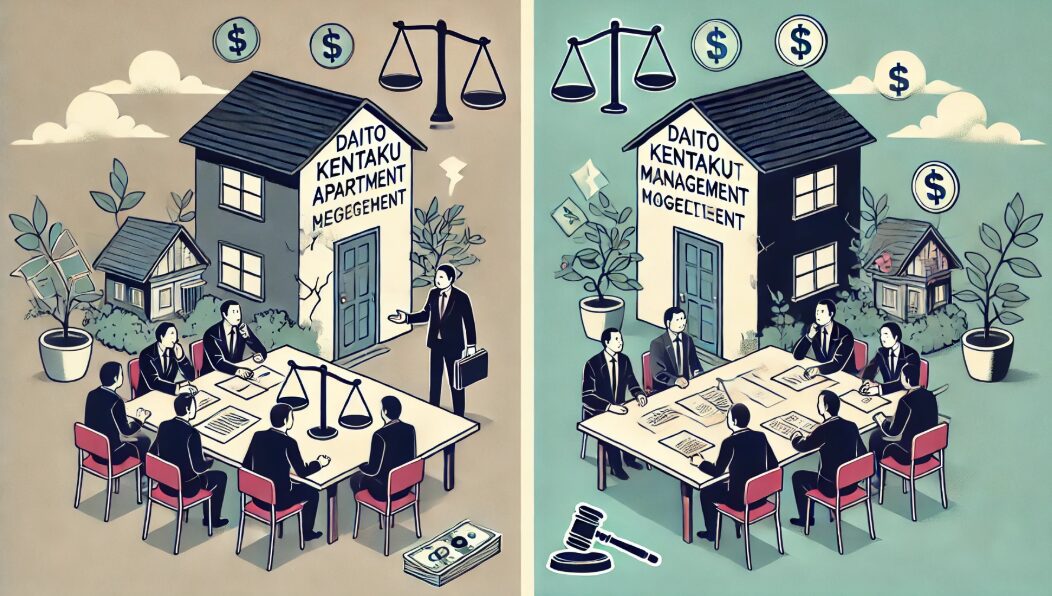
大東建託のアパート経営を巡るトラブルはあるようです。
実際に、建物建築請負契約の申込金返金についてトラブルが起こっている事が特定適格消費者団体である※1消費者機構日本にて確認することができます。
また、大東建託にてアパートを建てる際に必ず進められるサブリース契約についても※2独立行政法人国民生活センターや※3消費者庁が注意喚起を行っており、多くのオーナーが問題を抱えている実態がうかがえます。
特にトラブルになりやすいのは、これまで解説してきた家賃の減額交渉です。
30年一括借り上げなどの長期契約を結んだオーナーが、数年後に大幅な家賃減額を要求され、これを拒否したところ契約解除を迫られるといった事例が報告されています。
裁判では、家賃減額の妥当性が争点となりますが、法的には経済事情の変動による賃料の増減請求権が認められているため、オーナー側が常に有利とは限りません。
※1.「引用元:消費者機構日本」※2.「引用元:独立行政法人国民生活センター」※3.「引用元:消費者庁」
その他の主なトラブル事例
- 高額な修繕費用
建物の維持管理に必要な修繕は、オーナー負担となるのが一般的です。大東建託の指定する業者による修繕が必須とされ、相場よりも高額な費用を請求されたというトラブル。 - 解約時の違約金
前述の通りオーナーからの解約は困難ですが、仮に合意解約に至った場合でも、高額な違約金を請求されることがあります。 - 営業担当者の説明不足
契約時にリスクについて十分な説明がなく、後になって不利な条件に気づいたというトラブル。
これらのトラブルは、大東建託に限らずサブリース契約全般に共通するリスクとも言えます。
しかし、業界最大手であるからこそ、その契約数に比例してトラブルの件数も多くなっているのが現状です。
契約前には、同様のトラブルが起きていないか情報収集し、契約書の隅々まで目を通すことが自衛のために不可欠です。
大東建託のアパート経営失敗パターン
実は、大東建託に限らず、アパート経営で失敗する人には共通の「型」があります。
大東建託でアパート経営を始めて失敗に至るケースには、いくつかの共通したパターンが見られます。
これらのパターンを知ることで、同じ轍を踏むリスクを減らすことができます。
① 営業マンの言葉を鵜呑みにする
営業担当者はアパートを販売するプロであり、経営のプロではありません。
彼らの目的は契約を獲得することです。
「全てお任せください」「絶対に儲かります」といった甘い言葉や、メリットばかりを強調するトークを信じ込み、リスクを十分に検討しないまま契約してしまうのが最も典型的な失敗パターンです。
② 楽観的なシミュレーションを信じ切る
提示される収支シミュレーションは、あくまで現時点での予測に過ぎません。
将来の家賃下落、空室率の上昇、金利の上昇、予期せぬ修繕費の発生といったリスクが考慮されていない、あるいは非常に甘く見積もられていることがあります。
シミュレーション通りにいくと思い込み、余裕のない資金計画を立ててしまうと、少しの計画の狂いで経営は破綻に向かいます。
③ 節税目的が先行してしまう
「相続税対策になりますよ」という言葉は、地主にとって非常に魅力的です。
確かにアパートを建てることで節税効果は期待できます。
しかし、節税はあくまで副次的な効果であり、アパート経営の本質は「事業として収益を上げること」です。
節税目的が先行し、賃貸需要の低い土地にアパートを建ててしまっては、本末転倒です。
赤字を垂れ流して節税しても、資産は減る一方です。
④ 地方での過剰供給と競争激化
特に人口が減少している地方では、賃貸需要が限られているにもかかわらず、相続税対策などの理由でアパートが次々と建設され、供給過剰に陥っているエリアが少なくありません。
総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、日本の空き家率は13.6%と過去最高を記録しており、このようなマクロ環境が地方のアパート経営をより一層難しくしています。
このような場所で経営を始めると、激しい入居者獲得競争に巻き込まれ、家賃の下落は避けられません。
競合が多く、将来的な賃貸需要が見込めないエリアでの経営は極めて困難です。
からくりを理解し大東建託のアパート経営で成功する戦略
- まずは大東建託アパート経営の評判
- 大東建託の一括借り上げのからくり
- 35年一括借り上げのデメリットとは
- 家賃保証が「こんなはずでは」となる訳
- 大東建託のオーナートラブルと訴訟事例
- 大東建託のアパート経営失敗パターン
- アパート経営はやめたほうがいいのか
- 儲かる?オーナーの収入と経営費用
- オーナーが破産や死亡するリスク
- アパート経営に必須の出口戦略
- 大東建託一括借り上げのからくりとアパート経営成功
アパート経営はやめたほうがいいのか

これまでの解説を読むと、「やはりアパート経営はやめたほうがいいのではないか」と感じるかもしれません。
結論から言えば、「誰でも簡単に儲かる話ではないが、正しい知識と戦略があれば成功の可能性はある」というのが答えになります。
アパート経営は、株式投資などとは異なり、不動産という実物資産を扱う「事業」です。
事業である以上、経営者としての視点と努力が不可欠です。
全てを人任せにして楽にお金が入ってくる、という考えでは成功はおろか、大きな負債を抱えることになりかねません。
アパート経営を成功させるための最低条件
成功させるための条件
- 立地選定を最優先する
将来にわたって安定した賃貸需要が見込めるエリアか、徹底的に調査することが最も重要です。駅からの距離、周辺の商業施設、大学や企業の有無など、客観的なデータに基づいて判断します。 - 十分な自己資金を準備する
自己資金が少ないと借入額が大きくなり、金利負担が重くなります。また、予期せぬ支出に対応できず、資金繰りが悪化するリスクが高まります。建築費の2割程度は自己資金で用意することが望ましいでしょう。 - 経営者意識を持つ
サブリース契約を結ぶにしても、全てを丸投げにするのではなく、定期的に収支報告を確認し、周辺の市場環境を調査するなど、主体的に経営に関わる姿勢が求められます。
逆に言えば、これらの条件を満たさずに、営業担当者の言うがままに始めてしまうのであれば、「やめたほうがいい」と言えるでしょう。
アパート経営を始めるかどうかは、これらのリスクと責任を自身が負えるかどうかを慎重に判断した上で決めるべきです。
「やめる」前に知るべき、勝てる投資家のゴール設定
ただ闇雲に「やめる」のではなく、勝てるルールで戦うことが重要です。
多くの成功している投資家は、営業マンの提案を待つのではなく、自ら「資産形成のゴール」を設定して動いています。
では、具体的に何を目標にすべきなのか?以下の記事で、失敗しないためのゴール設定とロードマップを公開しています。
儲かる?オーナーの収入と経営費用
アパート経営の収益性を判断するためには、具体的な収入と支出を把握することが不可欠です。
「利回り」という言葉をよく耳にしますが、これには種類があり、正しく理解しないと収益性を見誤ります。
収入の内訳
主な収入は家賃です。
サブリース契約の場合は、大東建託から支払われる保証賃料が収入となります。
その他、入居者が入れ替わる際の礼金や、契約更新時の更新料も収入に含まれますが、これらは安定的に見込めるものではありません。
支出(経営費用)の内訳
収入から差し引かれる経費は多岐にわたります。
- ローン返済費
最も大きな割合を占める支出です。 - 管理委託料(サブリース手数料)
家賃収入の10%~20%程度。 - 修繕費
退去時の原状回復費用や、外壁塗装、設備交換などの大規模修繕に備えた積立金。 - 税金
固定資産税、都市計画税、そして利益に対してかかる所得税・住民税。 - 保険料
火災保険、地震保険など。 - その他
共用部分の光熱費など。
収支シミュレーション例(木造2階建て・6戸)
あくまで簡易的な例ですが、具体的な数字で見てみましょう。
| 分類 | 項目 | 金額(年間) | 備考 |
| 収入 | 満室時想定家賃収入 | 504万円 | 家賃7万円×6戸×12ヶ月 |
| 収入合計 | 504万円 | - | |
| 支出 | ローン返済額 | 約220万円 | 借入6,000万円、金利1.5%、35年返済の場合 |
| サブリース手数料 | 約75万円 | 家賃収入の15%と仮定 | |
| 修繕費積立 | 約25万円 | 家賃収入の5%と仮定 | |
| 固定資産税等 | 約30万円 | 物件により変動 | |
| 保険料等 | 約10万円 | 物件により変動 | |
| 支出合計 | 約360万円 | - | |
| 年間手残り(税引前) | 約144万円 | 収入合計 - 支出合計 |
このシミュレーションは空室や家賃下落を考慮していません。
将来的に家賃が10%下落すれば、年間の家賃収入は約50万円減少し、手残りは100万円を切ることになります。
このように、常に余裕を持った資金計画を立てることが重要です。
オーナーが破産や死亡するリスク
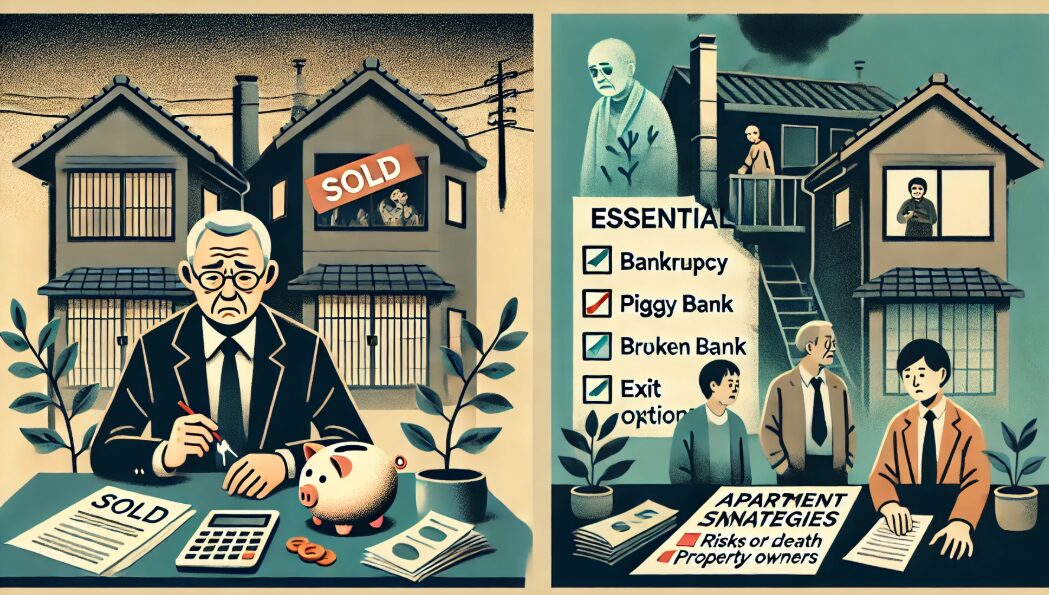
アパート経営には、事業が立ち行かなくなる「破産」のリスクと、オーナー自身の「死亡」に伴うリスクが常に存在します。
破産のリスク
破産に至る主な原因は、キャッシュフローの悪化です。
家賃収入から経費を支払った後に、ローンの返済額を下回る状態(赤字)が続くと、自己資金を取り崩して補填することになります。
その自己資金が尽きたとき、経営は破綻します。
特に、予期せぬ大規模修繕費の発生や、金利の上昇によるローン返済額の増加は、キャッシュフローを急激に悪化させる要因となります。
サブリース契約だからといって安心はできず、家賃減額によって赤字に転落し、破産に至るケースも考えられます。
死亡のリスク(相続問題)
オーナーが亡くなった場合、アパートとローンは相続人に引き継がれます。
ここで問題となるのが、相続トラブルと相続税です。
アパートのような不動産は現金と違って簡単に分割できないため、誰が相続するかで兄弟間のトラブルに発展しがちです。
また、経営を引き継ぐ意思や知識のない相続人にとっては、アパートは「収益を生む資産」ではなく「負債を抱えた厄介な不動産」になりかねません。
アパートローンを組む際には、通常「団体信用生命保険(団信)」に加入します。
これは、オーナーが死亡または高度障害状態になった場合に、保険金でローン残債が完済される仕組みです。
団信に加入していれば、相続人はローン返済の負担なくアパートを相続できますが、その後の経営や税金の負担がなくなるわけではありません。
経営者として、万が一の事態を想定し、誰に経営を引き継いでもらうのか、遺言書を作成しておくなどの生前対策を講じておくことも重要な責任の一つです。
アパート経営に必須の出口戦略

アパート経営を始める際には、必ず「いつ、どのように終えるか」という出口戦略を考えておく必要があります。
永遠に経営を続けられるわけではなく、建物の老朽化や市場の変化に対応できなくなったとき、適切な出口を選べなければ、損失が拡大してしまいます。
出口戦略には、主に以下の選択肢があります。
簡単な流れ
- 経営を継続する(修繕・リフォーム)
大規模なリフォームを行い、物件の競争力を高めて経営を続けます。 - 入居者付きで売却する(オーナーチェンジ)
アパート経営をしたい別の投資家に、現在の入居者がいる状態で物件を売却します。入居率が高いほど、高く売却できる可能性があります。 - アパートを解体して土地として売却する
建物の老朽化が激しく、収益性も見込めない場合に選択します。解体費用がかかりますが、立地が良い場所では土地としての価値が高く評価されることもあります。 - 建て替える
既存のアパートを取り壊し、新しい賃貸物件を建設します。多額の資金が必要になります。
すでに経営で困っている方は「売却」を検討
もし、あなたがすでに大東建託のアパート経営で赤字に苦しんでいたり、将来性に不安を感じていたりするのであれば、傷が浅いうちに「売却」という出口戦略を具体的に検討することをおすすめします。
不動産会社に査定を依頼し、現在の物件価値を把握することから始めましょう。
複数の会社に相談し、最も良い条件を提示してくれるパートナーを見つけることが重要です。
特に大東建託の物件には特有の売却難易度や注意点があります。
これからアパート経営を始める方も、購入(建築)する段階で「何年後にいくらで売れそうか」というシミュレーションをしておくべきです。
出口を見据えた事業計画こそが、成功の鍵を握ります。
あなたのアパートは今いくら?適正価格を知ることから再出発
「うちのアパートは今いくらなのか?」この問いに即答できない場合は、危険信号です。
独自の販売網を持つ業者や、地方物件に強い業者など、選び方一つで査定額に数百万円の差が出ることがあります。
手遅れになる前に、まずは複数の会社で査定を行い、適正価格を把握することから始めてください。
大東建託一括借り上げのからくりとアパート経営成功
- 大東建託の一括借り上げは入居者募集や管理の手間を省けるサブリース契約である
- オーナーは空室の有無に関わらず一定の保証賃料を受け取れるメリットがある
- 一方で保証賃料は入居者の家賃から手数料が引かれた額になる
- 35年一括借り上げでも契約当初の家賃が保証され続けるわけではない
- 一般的に10年後に家賃の見直しがあり減額されるリスクがある
- 家賃減額の主な理由は周辺の家賃相場の下落や建物の老朽化である
- オーナー側からの契約解除は借地借家法により非常に困難な場合が多い
- 「こんなはずでは」というトラブルは家賃減額リスクの認識不足から生じる
- 過去にはオーナートラブルが訴訟に発展した事例もある
- 営業マンの言葉や楽観的なシミュレーションを鵜呑みにするのは失敗の元である
- アパート経営は事業であり経営者としての視点と知識が不可欠である
- 成功のためには立地選定、自己資金、経営者意識が重要になる
- オーナーが死亡した際の相続問題も事前に考えておく必要がある
- 経営を始める際には必ず売却などの出口戦略を立てておくべき
- すでに経営難に陥っている場合は早めに売却を検討することが賢明である
