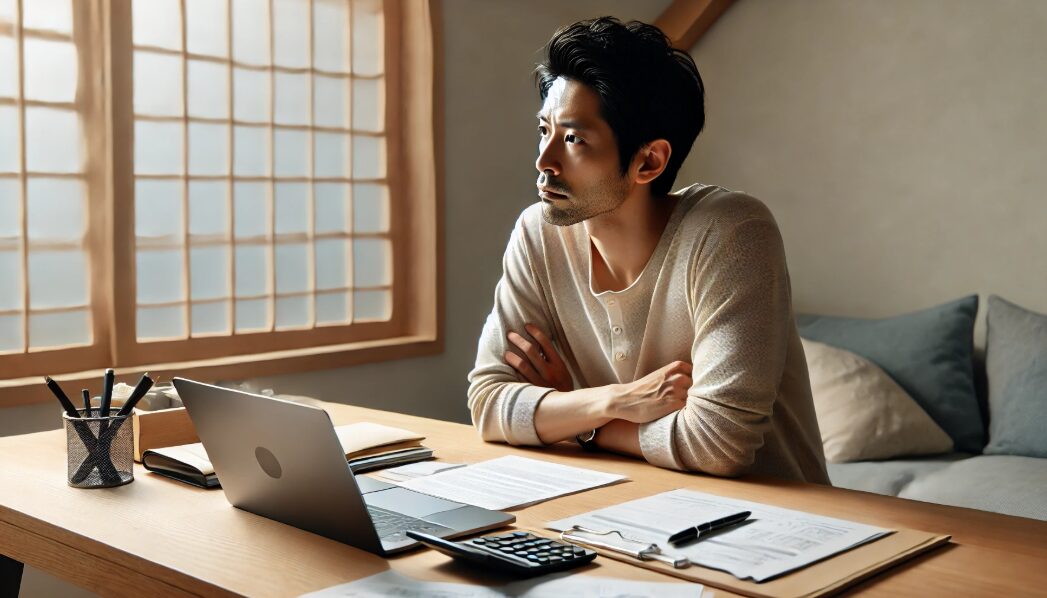
35歳から40歳という年齢で、貯金3000万円を達成したものの、「もしかして、この金額は少ないのではないか?」という不安を感じて検索されたのではないでしょうか。
3000万円貯めるには何年かかったのか、その苦労を振り返りつつも、周囲の状況が気になってしまうかもしれません。
実際のところ、貯金3000万がある30代から40代の割合はどれくらいなのか、特に貯金3000万を達成した独身の方のデータはどうなっているのか。
また、金融資産3000万円以上の人達の日常とはどのようなものなのか、気になるところです。
確かに、資産3000万円がもたらす精神的余裕は大きいはずです。
しかし、この先インフレが進んだ場合、貯金3000万だけでは何年暮らせるのかという現実的な心配もあるでしょう。
35から40歳で貯金3000万は少ないと感じるその感覚は、将来を見据えているからこそ生まれるものかもしれません。
この記事では、客観的なデータに基づきながら、貯金3000万超えたら考えるべきこと、そしてその不安を解消するための次のステップについて詳しく解説します。
3,000万円はゴールではなく「通過点」です
3,000万円は決して少ない金額ではありませんが、それを銀行に眠らせておくのは機会損失です。
実は、その信用と資金力を活かして、より堅実に資産を拡大する「二階建て」の仕組みがあることをご存知でしょうか。
この記事のポイント
- 30代・40代で貯金3000万円を持つ人の客観的な割合
- 「少ない」と感じてしまう不安の正体と、その妥当性
- 3000万円を貯蓄だけで使い切った場合のシミュレーション
- 貯金3000万円を超えたら始めるべき資産の「守り方」と「増やし方」
35歳から40歳で貯金3000万は少ない?
- 貯金3000万がある30代から40代の割合
- 貯金3000万がある独身世帯のデータ
- 3000万円貯めるには何年必要か
- 35から40歳の人が貯金3000万で少ないと感じる訳
- 貯金3000万だけだと何年暮らせる?
- 資産3000万円がもたらす精神的余裕
- 貯金3000万を超えたら「守る」意識を持とう
- インフレで資産価値が目減りする
- 金融資産3000万円以上の人達の日常
- 35歳から40歳の人の貯金3000万は少ないのではなく次のスタートライン
貯金3000万がある30代から40代の割合
結論から言えば、35歳から40歳で金融資産3,000万円以上を保有している人は、全体の中でも上位層に位置します。
つまり「非常に多い」というよりは、「かなり限られた少数派」といえるでしょう。
金融広報中央委員会が公表している「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年・総世帯調査)」によると、年代別に3,000万円以上の金融資産を保有している世帯の割合は次の通りです。
| 年代 | 3,000万円以上保有世帯の割合 |
|---|---|
| 20代 | 0.8% |
| 30代 | 4.0% |
| 40代 | 9.6% |
| 50代 | 16.0% |
| 60代 | 24.6% |
このデータを見ても分かるように、30代で3,000万円以上の資産を持つ人は約4%、40代でも約9.6%しかいません。
35歳から40歳という年齢層は、この中間に位置するため、おおよそ全体の上位5〜7%ほどと推定できます。
この割合からも、35歳から40歳で3,000万円を達成している人は、平均よりも大きく先行していることが分かります。
言い換えれば、それだけの資産を築いた人は、家計管理や資産形成の面で高い意識と継続力を持っているといえます。
一方で、野村総合研究所の資産階層区分では、純金融資産3,000万円以上5,000万円未満の世帯を「アッパーマス層」と呼んでいます。
この層は全世帯の約10.3%にあたるとされており、30代・40代の段階でこの水準に到達している場合は、全国的に見ても上位1割前後の資産レベルにあることを意味します。
したがって、35歳から40歳で3,000万円の資産を持っている人は、「まだ少ない」と感じるかもしれませんが、客観的な統計で見れば確実に上位層に入っていると言えるでしょう。
貯金3000万がある独身世帯のデータ
結論から言えば、独身(単身世帯)で金融資産3,000万円を保有している人も、全体から見ると上位層に属します。
これは決して一般的な水準ではなく、むしろ高い金融リテラシーと計画的な貯蓄行動の結果といえます。
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年・単身世帯調査)」によると、単身世帯のうち金融資産を3,000万円以上保有している人の割合は次の通りです。
| 世帯区分 | 3,000万円以上保有割合 |
|---|---|
| 単身世帯 | 8.6% |
| 二人以上世帯 | 12.7% |
| 総世帯(全体) | 11.8% |
この調査結果から、単身世帯で3,000万円以上の金融資産を持つ人は、全体の上位8.6%に当たります。
つまり、およそ12人に1人しかいない割合です。
一方で、二人以上世帯では12.7%と若干高い水準にあります。
これは、共働きや世帯収入の合算による資産形成効果が反映されていると考えられます。
さらに年代別の単身データを見ると、30代では4.6%、40代では13.0%が3,000万円以上の金融資産を保有しています。
このことから、35歳から40歳の独身の方が3,000万円を達成している場合、同年代全体でもかなり上位の位置にあるといえるでしょう。
特に独身の場合、自身の収入のみで生活費と貯蓄を両立させる必要があります。
そのため、3,000万円という水準を築いた人は、支出管理や投資・貯蓄のバランスを非常に上手に保っているケースが多いです。
このように、単身世帯で3,000万円を超える金融資産を築くことは、統計的にも難易度が高く、同時に大きな経済的自立を達成していることを意味します。
決して「少ない」金額ではなく、安定した生活基盤を手に入れた証とも言えるでしょう。
3000万円貯めるには何年必要か

35歳から40歳で3,000万円を達成したということは、逆算すると非常に早い段階から、または非常に高い金額で貯蓄を継続してきたことが推察されます。
仮に貯金ゼロからスタートして3,000万円を貯めるために必要な年数を、毎月の積立額別にシミュレーションしてみましょう(金利は考慮しない場合)。
| 毎月の積立額 | 年間積立額 | 3,000万円達成に必要な年数 |
|---|---|---|
| 5万円 | 60万円 | 50.0年 |
| 7万円 | 84万円 | 約35.7年 |
| 10万円 | 120万円 | 25.0年 |
| 15万円 | 180万円 | 約16.7年 |
| 20万円 | 240万円 | 12.5年 |
もし23歳(大学卒業)から貯蓄を始めたとして、40歳(17年間)で達成するには、毎月15万円近い金額を貯蓄し続ける必要があります。
35歳(12年間)で達成するには、毎月20万円以上の貯蓄が必要です。
これは、ボーナスを考慮しない単純計算ですが、いかに高いハードルであるかが分かります。
これを実現したことは、ご自身の収入管理能力と忍耐力の賜物です。
35から40歳の人が貯金3000万で少ないと感じる訳
客観的なデータでは「非常に多い」にもかかわらず、なぜ「少ない」と感じてしまうのでしょうか。
その理由は、将来への具体的な不安要素が見えているからにほかなりません。
主に、以下の3つの点が考えられます。
1. ゆとりある老後資金としては不足する可能性
老後の生活費として、年金以外にいくら必要かという試算があります。
「最低限の老後生活」であれば3,000万円で不足分を補える可能性はありますが、「ゆとりある老後生活」を目指す場合、不足する可能性が高いです。
ある調査では、「ゆとりある老後生活」には平均で月額約38万円が必要とされています。
年金受給額を仮に月23万円とすると、毎月15万円が不足します。
この場合、65歳から100歳までの35年間で6,300万円(15万円×12ヶ月×35年)が必要となり、3,000万円では足りません。
2. セミリタイア(早期退職)は困難
35歳から40歳という年齢で3,000万円を達成すると、「セミリタイア」や「FIRE(経済的自立と早期退職)」が視野に入るかもしれません。
しかし、現実的には3,000万円でリタイア生活を維持するのは困難です。
次の項目でシミュレーションしますが、貯蓄だけで生活すると十数年で資産が尽きる可能性があります。
セミリタイアを実現するには、労働収入を補うための資産収入(配当金や家賃収入など)が必要ですが、3,000万円を元手に十分な不労所得を得ることも簡単ではありません。
3. インフレによる資産価値の目減り
現在の物価上昇(インフレ)も不安要素です。
銀行預金に3,000万円を置いているだけでは、お金の額面は変わりませんが、モノを買う力(購買力)は年々低下していきます。
例えば、年2%のインフレが続けば、10年後には現在の3,000万円の実質的な価値は約2,460万円程度に目減りしてしまいます。
「貯めているだけでは資産が減っていく」という感覚が、「少ない」という不安につながっています。
つまり、35歳から40歳で「少ない」と感じるその感覚は、将来のリスクを現実的に見据えている証拠であり、非常に真っ当な感覚だと言えます。
「まとまった資金があれば投資なんてしなくて良いのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、資産額が増えるほど、インフレや税金による目減りリスクは深刻化します。
貯金3000万だけだと何年暮らせる?

では、もし今仕事を辞め、貯金3,000万円を取り崩して生活した場合、一体何年暮らせるのでしょうか。
総務省の家計調査(2021年データ参考)によると、月間の消費支出額は以下のようになっています。
- 二人以上世帯:月間約28万円
- 単身世帯:月間約16万円
この支出額を基に、3,000万円を使い切る期間をシミュレーションします。
| 世帯 | 月間消費支出 | 3,000万円で暮らせる期間 |
|---|---|---|
| 二人以上世帯 | 約28万円 | 3,000万円 ÷ 28万円 ≒ 107ヶ月 (約9年) |
| 単身世帯 | 約16万円 | 3,000万円 ÷ 16万円 ≒ 188ヶ月 (約16年) |
もちろん、これはあくまで平均的なデータであり、個人のライフスタイルによって大きく変動します。
しかし、35歳から40歳という年齢を考えると、9年や16年では老後まで到底足りないことが明確です。
このシミュレーションからも、3,000万円は「人生を上がり(ゴール)」にするための金額ではなく、あくまで「次の準備」のための資金であることがわかります。
貯蓄を取り崩すだけの生活から脱却するために
貯蓄を取り崩すだけの生活には限界があります。真の安心を得るためには、資産そのものが収益を生み出す仕組みが必要です。
会社員の信用力と手元の資金を組み合わせ、リスクを抑えて資産を増やす具体的な手順について解説します。
資産3000万円がもたらす精神的余裕

ただし、不安要素ばかりではありません。
3,000万円という資産がもたらす最大のメリットは、「精神的な余裕」です。
3,000万円の貯蓄は、人生における強力なセーフティネットとなります。
例えば、急な病気やケガで働けなくなっても、数年間は生活に困りません。
また、現在の職場に不満がある場合でも、「いざとなれば辞められる」という余裕があるため、精神的に追い詰められにくくなります。
さらに、キャリアチェンジのための学習や、起業といった新しい挑戦もしやすくなります。
お金の心配をせずに人生の選択肢を広げられることは、3,000万円という資産がもたらす非常に大きな価値です。
3,000万円という資産は確かに大きな安心材料ですが、それを実際に手にした人がどのようなマインドセットの変化を経験し、さらに上のステージへ進んでいるのかを知ることも重要です。
35歳から40歳の人が貯金3000万で少ないと感じる不安の消し方
- 貯金3000万がある30代から40代の割合
- 貯金3000万がある独身世帯のデータ
- 3000万円貯めるには何年必要か
- 35から40歳の人が貯金3000万で少ないと感じる訳
- 貯金3000万だけだと何年暮らせる?
- 資産3000万円がもたらす精神的余裕
- 貯金3000万を超えたら「守る」意識を持とう
- インフレで資産価値が目減りする
- 金融資産3000万円以上の人達の日常
- 35歳から40歳の人の貯金3000万は少ないのではなく次のスタートライン
貯金3000万を超えたら「守る」意識を持とう

3,000万円という節目を達成したいま、持つべきは「貯める」意識から、「守りながら増やす」という意識への転換です。
ここでの「守る」とは、単に銀行に預けておくことではありません。
インフレや将来の支出増に備え、資産の実質的な価値を守ることを指します。
まず行うべきは、ご自身の資産の仕分けです。
1. 生活防衛費を確保する
何があっても手を付けてはいけないお金として、「生活防衛費」を現金(普通預金など)で確保します。
これは、突発的な事故、病気、失業などに備えるためのお金です。
目安は、ご自身の1ヶ月の生活費の3ヶ月分から、多くても1年分程度です。
| 世帯 | 生活防衛費の目安 |
|---|---|
| 独身・ひとり暮らし | 生活費の3〜6ヶ月分 |
| 夫婦2人暮らし | 生活費の3〜6ヶ月分 |
| 子どもがいる世帯 | 生活費の6〜12ヶ月分 |
2. 余剰資金を「投資」に回す
3,000万円から生活防衛費を引いた残りのお金が、当面(5年~10年)使う予定のない「余剰資金」です。
この余剰資金を、資産運用(投資)に回して「増やす」ことを検討します。
35歳から40歳という年齢は、老後までまだ20年以上の長期的な運用期間を確保できます。
これは資産運用において非常に有利な条件です。
また、NISAで運用して増えた資産を将来どう使うか、あるいは暴落時にどう守るかという「出口」の計画はできていますか?資産寿命を延ばすためには、株式と不動産を組み合わせた戦略が有効です。
インフレで資産価値が目減りする
前述の通り、資産を「守る」上で最大の敵となるのがインフレです。
なぜなら、銀行の普通預金金利は年0.001%程度(2025年現在)であることが多く、物価が年1%や2%上昇する状況では、預金しているだけで資産の価値は実質的に減っていくからです。
3,000万円という大金をインフレリスクにさらし続けることは、機会損失であると同時に、将来の不安を増大させる要因にもなります。
このインフレリスクに対応し、資産価値を「守る」ためにも、インフレ率を上回るリターンが期待できる資産運用(投資)の知識が不可欠になります。
金融資産3000万円以上の人達の日常

3,000万円を達成した「アッパーマス層」の人々は、どのような日常や考え方を持っているのでしょうか。
もちろん個人差はありますが、多くの場合、3,000万円をゴールとは考えていません。
むしろ、これを「元手(種銭)」として、次のステップである資産運用を本格化させています。
彼らにとって3,000万円は、「貯金」ではなく「金融資産」の一部です。
預貯金だけでなく、株式、投資信託、債券などに資産を分散させています。
特にまとまった資金があるからこそ、以下のような安定性の高い運用方法も選択肢に入ってきます。
- 債券投資
国や企業が発行する債券は、株式に比べてリスクが低く、固定の利子(クーポン)が期待できます。 - 投資信託(インデックスファンド)
NISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用し、全世界の株式や債券に分散投資を行い、長期的な成長を目指します。 - 不動産投資(REITなど)
少額から不動産に投資できるREIT(不動産投資信託)なども活用し、資産の分散先を広げます。
このように、3,000万円を超えた人々の多くは、銀行預金に偏った資産構成を見直し、インフレに負けない「資産の置き場所」を真剣に考え、実行しているのです。
35歳から40歳の人の貯金3000万は少ないのではなく次のスタートライン
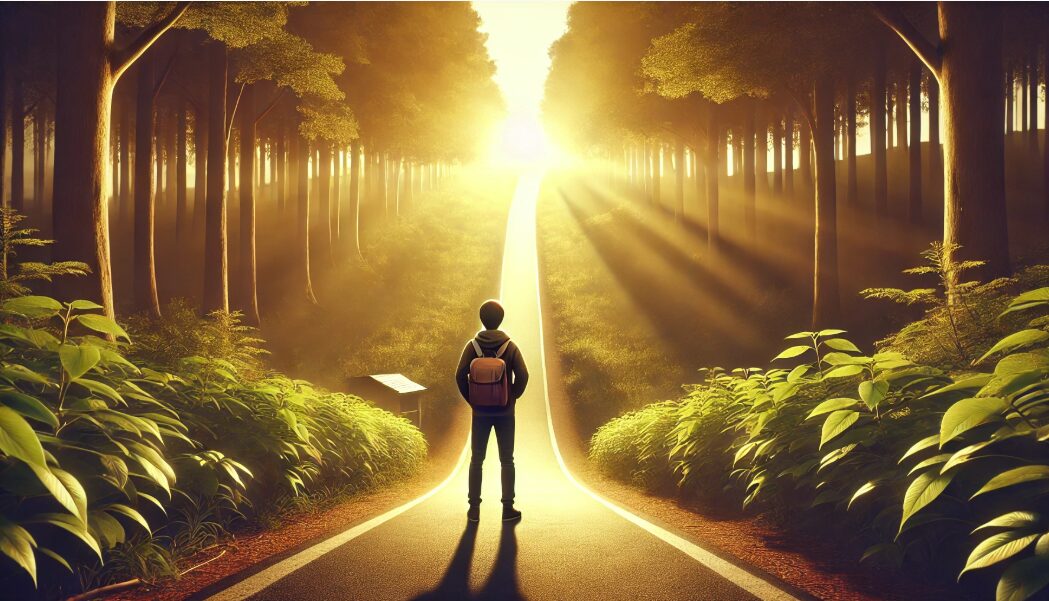
35歳から40歳という年齢で貯金3000万円を達成したにもかかわらず、「少ないかもしれない」と感じる不安は、決して間違いではありません。
それは、インフレや将来必要となる老後資金など、現実的なリスクをしっかりと見据えている証拠です。
本記事で確認したように、統計データ上、あなたの資産状況は同世代の中で「非常に多い」上位層に入っています。
まずは、その事実に自信を持ってください。
そして、その大切な3,000万円を「人生のゴール」として取り崩していくだけでなく、「次の資産形成へのスタートライン」として捉え直すことが、その不安を解消する鍵となります。
これからは「貯める」ステージから、インフレに負けないよう資産を「守り・増やす」ステージです。
まずはご自身の資産を「生活防衛費」と「余剰資金」に仕分けし、NISAやiDeCoといった制度を活用しながら、長期的な資産運用を学び始めることからスタートしてみてはいかがでしょうか。
その一歩が、あなたの精神的な余裕をさらに確かなものにし、より豊かな未来へとつながっていきます。
最後に、この記事の要点をまとめます。
- 35歳から40歳で貯金3000万円を持つ人は統計的に「非常に多い」
- 30代で3000万円以上を持つ人は上位4%程度
- 40代で3000万円以上を持つ人は上位10%程度
- 独身(単身世帯)でも3000万円以上は上位8.6%
- 3000万円は「アッパーマス層」と呼ばれる資産階級にあたる
- 3000万円を貯めるには月15万から20万の積立を10数年続ける必要がある
- それでも「少ない」と感じる理由は将来不安が明確だから
- 不安の正体は「ゆとりある老後資金への不足」
- 不安の正体は「セミリタイアには足りない」という現実
- 不安の正体は「インフレによる資産価値の目減り」
- 貯金3000万円を支出のみで使うと約9年から16年で尽きる
- 3000万円がもたらす最大の価値は「精神的余裕」と「人生の選択肢」
- 3000万円を超えたら「貯める」から「守り・増やす」へ意識転換する
- 生活防衛費を現金で確保し、残りの「余剰資金」を投資に回す
- 35歳から40歳は「少ない」のではなく「次のスタートライン」に立った状態
あなたの3000万円を「一生のお金」に変える設計図
あなたはすでに、上位数%に入る資産を築く力を持っています。その努力を無駄にしないために、次は「労働による貯蓄」から「資産による資産形成」へとシフトチェンジする時です。
NISAで土台を固め、さらに不動産投資を組み合わせて加速させる。私たちが推奨する、会社員のための再現性の高い資産形成術を、まずは知ることから始めてください。
あわせて読みたい関連記事
