
こんにちは、「ぼちぼち大家」です。
不労所得を目指して資産運用を日々私自身も勉強しています。
「不動産投資 始め方」と検索すると、「やめとけ」とか「サラリーマン大家はカモだ」なんて、ちょっと怖い言葉がたくさん出てきて不安になりますよね。
特に初心者の方は、具体的な流れや、いったいどれくらいの資金(初期費用)が必要なのか、自分の年収で本当にローンが組めるのか、新築と中古はどっちがいいのか、リスクはどうなっているんだ…と、分からないことだらけかと思います。
私も最初はそうでした。
不動産投資は、いきなり始めると失敗するリスクが高いのは事実です。
でも、それは勉強不足や準備不足が原因なことがほとんどなんですね。
この記事では、利回りやキャッシュフローの基本的な見方から、小さく始める方法、万が一のリスク対策まで、私が学んできた「カモ」にならずに堅実に進めるためのステップを、私の視点で解説していきたいと思います。
この記事のポイント
- 「やめとけ」と言われる本当の理由
- 不動産投資を始めるための具体的な流れ
- 必要な資金計画とローンの目安
- 初心者が学ぶべきリスク対策
この記事では、不動産投資の「始め方」の全手順を解説しますが、もしあなたが、
- 不動産投資を「点」ではなく、資産形成全体の「ロードマップ」として体系的に学びたい
- まずは無料で参加できる優良セミナーで、プロの意見を聞いてみたい
と既にお考えの場合は、以下の記事が近道になるかもしれません。
「やめとけ」は嘘?不動産投資 始め方の誤解
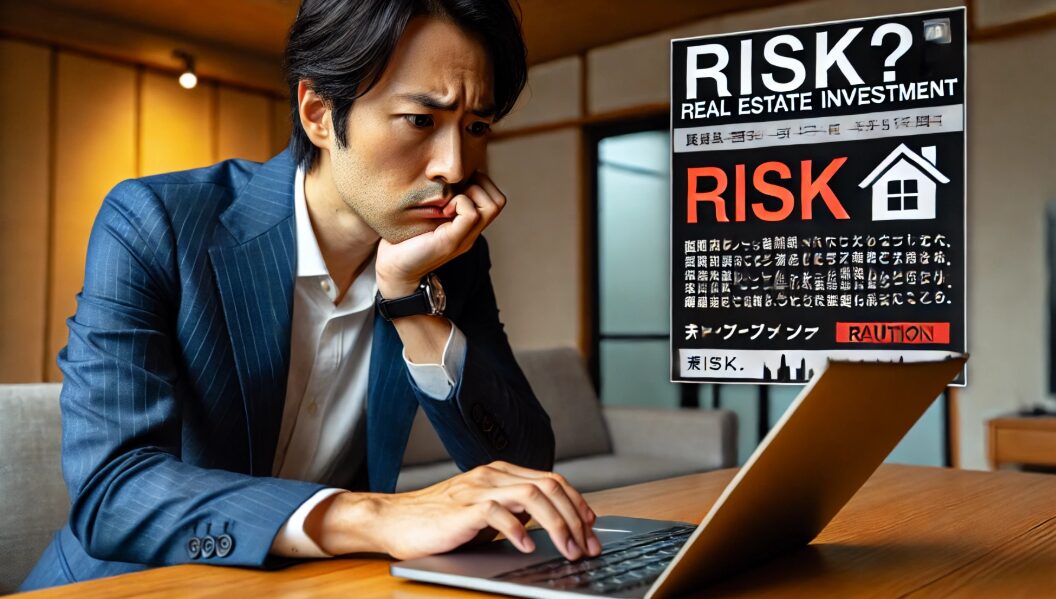
不動産投資の世界に足を踏み入れようとすると、必ず目にするのが「やめとけ」という言葉。
でも、それを鵜呑みにして諦めるのは早いかもしれません。
なぜそう言われるのか、その理由をしっかり理解することが、実は成功への第一歩なんです。
サラリーマン大家がカモになる失敗理由
なぜ「サラリーマン大家はカモだ」と言われてしまうんでしょうか。
それは多くの場合、十分な勉強をしないで、不動産会社の営業トークだけを信じて始めてしまうからなんですね 。
私が見てきた失敗しやすいパターンは、だいたい決まっています。
- 営業トークを鵜呑みにする
「節税になりますよ」「将来の年金代わりに」という言葉だけを信じて、リスクの説明を真剣に聞かない 。 - リスクを過小評価する
特に「空室リスク」ですね。購入前に提示されるシミュレーションは、常に満室であることが前提の「楽観的な数字」であることが多いです 。入居者がいなければ、収入はゼロです。 - 「利回り」だけで判断する
広告に載っている「表面利回り」という数字は、経費が一切含まれていません 。実際の「実質利回り」や、手元に残る現金「キャッシュフロー」で見ないと、実は赤字だった…なんてことも。 - 資金計画が甘すぎる
「自己資金ゼロでもOK」「フルローン・オーバーローンで始められます」という甘い言葉には注意が必要です 。借入が多すぎると、少し空室が出ただけ、金利が少し上がっただけですぐに返済が苦しくなります 。
そして、物件を購入したあとに失敗したと気づく事例が以下となります。
購入後に失敗したと気づく事例
- 目先の高利回りに釣られて地方の物件を買ったが、まったく入居者が決まらず、売ることもできずにローン返済だけが残った。
- 管理費が安いという理由だけで管理会社を選んだら、管理がずさんで退去が続出。結局、多額の修繕費を請求された。
- 「なんとかなるだろう」と返済期間を短くしすぎて、月々の返済額が家賃収入を圧迫。空室が出た瞬間に破綻した。
結局のところ、他人任せにせず、自分で判断できるだけの知識を身につけることが、「カモ」にならないための最大の防御策なんです。
なぜサラリーマン大家は「カモにされやすい」のでしょうか?以下の記事では、サラリーマンが陥りがちな失敗の具体的な分岐点と、それを防ぐための実践的な対策をさらに詳しく解説しています。
始める前に知るべき2つの収益源
不動産投資の利益には、大きく分けて2つの種類があります。
これを知らないと、自分が何のために投資するのかがブレてしまいます。
① インカムゲイン(運用益)
これは、物件を保有している間に継続的に得られる収益、つまり「家賃収入」のことです。
不動産投資の基本であり、毎月のキャッシュフローを生み出す源泉ですね。
安定した不労所得を目指すなら、こちらがメインになります。
② キャピタルゲイン(売却益)
これは、物件を購入した価格よりも高い価格で売却したときに得られる、「売買差益」のことです。
バブル期はこれが主流でしたが、今の日本では、購入時より高く売るのはなかなか難しいのが現実。
基本的にはインカムゲインを狙いつつ、将来的に価値が下がりにくい物件を選んで、売却時も損をしない(あわよくば利益を出す)という考え方が主流です 。
初心者のうちは、まず「インカムゲイン」を安定して得られることを目標にするのが堅実かと思います。
初心者におすすめの勉強法
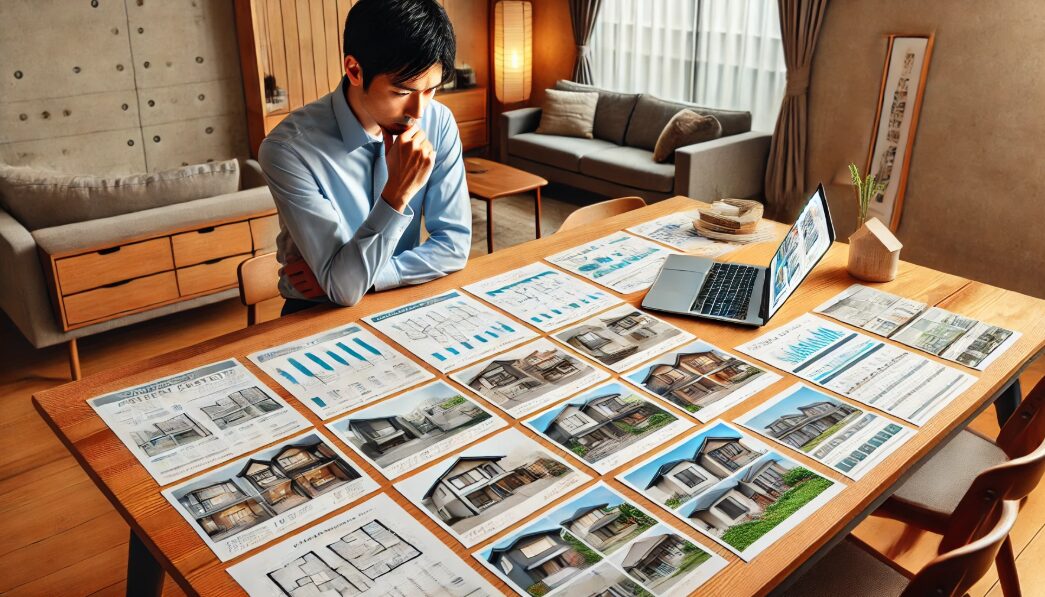
では、「カモ」にされないためにはどう勉強すればいいか。
私もいろいろ試しましたが、遠回りのようで一番の近道は、ステップを踏んで知識を習得することでした 。
step
1基礎知識の習得(ネット・書籍)
まずは、この記事で触れているような「利回り」「キャッシュフロー」「リスク」「ローン」といった基本的な用語を理解することからですね 。
今はネットや投資家さんのブログでもリアルな情報が得られますし 、体系的に学ぶなら書籍を数冊読んでみるのがおすすめです。
step
2実地での情報収集(現地調査)
机上の勉強と同時に、気になる物件があったら実際にその地域を歩いてみることです 。
駅からの実際の距離、スーパーやコンビニの有無、夜道の明るさ、ゴミ捨て場の管理状態など、資料だけでは分からない「一次情報」がめちゃくちゃ大事です。
step
3セミナーでの実践的知識の習得
不動産会社が主催するセミナーも有効です 。
最新の市場動向や金融機関の情報を知ることができます。
ただし、これには注意も必要です。
セミナー選びの注意点
セミナーは勉強の場であると同時に、不動産会社にとっては「営業の場」でもあります。
高額なセミナーや、特定の物件の購入をやたらと急かしてくるようなセミナーは要注意です。
まずは無料〜低額で、自分の知識レベルに合ったもの、特定の物件種別(区分・一棟など)に偏らない基礎的な内容のものを選ぶのが良いかと思います。
step
4実際の物件選びを通じた学習
紹介された物件やネットで見つけた物件で、自分なりに収支シミュレーションをしてみること 。
学んだ知識を使って「この家賃設定は妥当か?」「経費を引いたらキャッシュフローは残るか?」と計算してみるのが、一番実践的な勉強になります。
小さく始める資金計画と初期費用

不動産投資は「小さく始める」のが鉄則です。
いきなり多額の借金をして一棟アパート…というのは、初心者にはリスクが高すぎます。
まずは比較的少額から始められる「区分マンション投資」(マンションの1室を買う)から検討するのが一般的ですね 。
では、どれくらいお金が必要なのか。
よく言われる目安は「物件価格の15%~30%」です 。
例えば3,000万円の物件なら、450万~900万円くらいですね。
この初期費用は、大きく2つに分かれます。
- 頭金(物件価格の10%~20%)
物件価格の一部として先に支払うお金です。頭金が多いほど借入額が減るので、月々の返済が楽になり、ローンの審査も通りやすくなります。 - 諸費用(物件価格の5%~10%)
物件本体の価格とは別に、手続きにかかる費用です。これは基本的に現金で用意する必要があるので、非常に重要です。
購入時にかかる「諸費用」の主な内訳
| 費用項目 | 概要 | 目安(3,000万円の物件の場合) |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う成功報酬 | 約100万円(物件価格×3%+6万+税)(宅地建物取引業法に基づく上限) |
| 登記費用 | 物件を自分の名義にするための税金(登録免許税)や司法書士への報酬 | 約30万~50万円 |
| ローン関連費用 | 金融機関に支払う事務手数料や保証料 | 約50万~100万円(金融機関による) |
| 各種税金 | 契約書に貼る印紙税、不動産取得税(購入から数ヶ月後) | 約15万~30万円 |
| 火災・地震保険料 | ローンを組む際に必須。数年分を一括払いすることが多い。 | 約5万~50万円(構造・補償による) |
※上記はあくまで一般的な目安です。
物件の種類や条件によって大きく変動します。
最近は「フルローン(物件価格の100%融資)」や「オーバーローン(諸費用まで融資)」を謳う広告もありますが 、借入額が物件の価値を上回る状態(=買った瞬間に含み損)になるため、金利も高くなりがちで、非常にリスクが高いです 。
初心者は特に、しっかり自己資金を用意する前提で計画を立てるべきだと私は思います。
「自己資金は具体的にいくら貯めればいいの?」「フルローンのリスクって本当は?」など、お金に関する疑問は尽きませんよね。
以下の記事で、必要な自己資金のシミュレーションや、資金ゼロで始めるリスクについて詳しく解説しています。
あわせて読みたい
年収と不動産投資ローンの関係
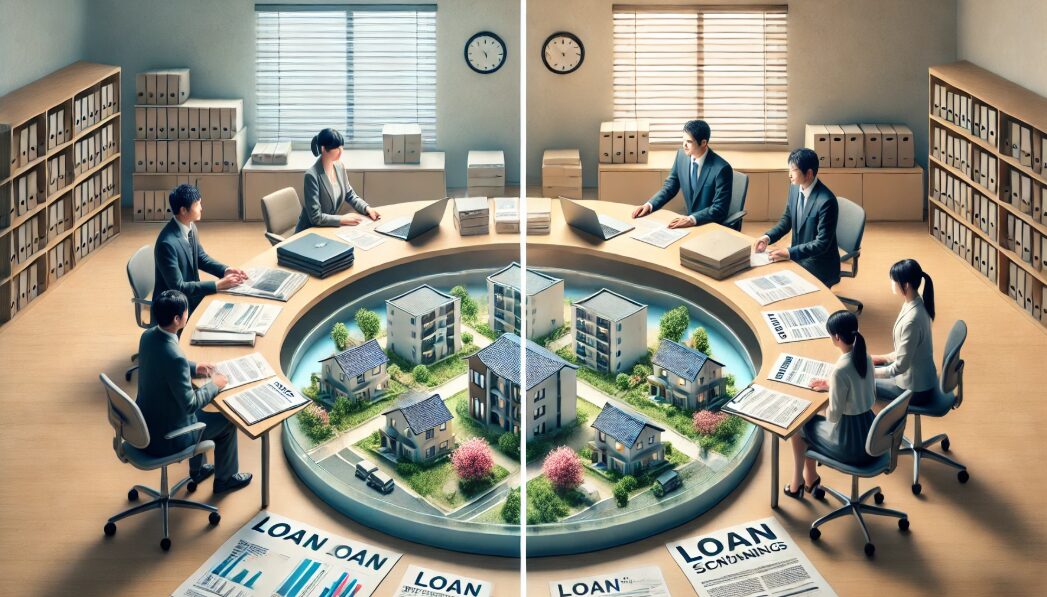
サラリーマンが不動産投資を始める最大のメリットは、「信用力(属性)」を使ってローンを組めることです。
金融機関が「この人になら貸せる」と判断する基準として、「年収」は非常に重要な要素になります 。
よく言われる目安は、「年収700万円以上」です 。
このラインを超えると、低金利・長期といった良い条件で融資を受けられる金融機関の選択肢が広がる傾向にあります。
「じゃあ、それ以下だと無理なの?」と思うかもですが、そんなことはありません。
年収500万円以下の場合の選択肢
- 日本政策金融公庫などを検討する
一般的な銀行より審査のハードルが低いとされる場合があります。 - 自己資金を多く用意する
物件価格の20%以上など、自己資金比率を高めることで、借入額を減らし審査に通りやすくします。 - コンパクトな物件を選ぶ
新築の区分マンションや中古戸建てなど、取得価格自体を抑えることで、必要な借入額を少なくします。
ただし、審査は年収だけで決まるわけではありません。
「勤務先(上場企業か、公務員か)」「勤続年数(最低2~3年が目安)」「他の借入状況(住宅ローンやカードローンなど)」「物件そのものの担保価値」といった要素を総合的に判断されます 。
金利相場も金融機関によってかなり幅があります。
| 金融機関 | 金利相場(目安) | 特徴 |
| 都市銀行・信託銀行 | 年1%台~ | 低金利だが審査が最も厳しい。 |
| 地方銀行 | 年2%前後~ | エリアや属性によって差が激しい。 |
| ネット銀行 | 年1%~4%台 | 利便性が高いが、審査は独自基準。 |
| ノンバンク | 年3%~5%台 | 審査が柔軟で早いが、高金利。 |
どの金融機関が使えるかは、提携している不動産会社によっても変わってくるので、この点もパートナー選びで重要になりますね。
失敗しない不動産投資 始め方の全手順

さて、基礎知識やお金の話がわかってきたところで、いよいよ具体的な「始め方」の流れです。
私がいろんな情報を見て「これなら堅実だ」と思ったステップを紹介します 。
大事なのは「順番」です。
流れ①:投資目的と物件の種類
まず、「何のために不動産投資をやるのか」をハッキリさせることがスタートです 。
- 「老後の年金代わりに、毎月10万円のキャッシュフローが欲しい」
- 「給与以外の収入の柱を作りたい」
- 「(高所得者の場合)節税対策としてやりたい」
目的によって、選ぶべき物件がまったく変わってきます 。
次に、主な物件の種類を知っておきましょう。
| 物件種別 | 特徴 | メリット | デメリット |
| 区分マンション | マンションの1室。 | ・比較的少額から始められる ・管理の手間が少ない ・売りやすい(流動性が高い) | ・空室になると収入ゼロ ・利回りが低い傾向 ・経営の自由度が低い |
| 一棟アパート・マンション | 建物まるごと。 | ・空室リスクを分散できる ・高利回りが期待できる ・経営の自由度が高い | ・初期費用が非常に高額 ・管理の手間が大きい ・売りにくい(流動性が低い) |
| 戸建て投資 | 一軒家。 | ・ファミリー層など長期入居が期待できる ・土地ごと所有できる | ・区分同様、空室で収入ゼロ ・修繕リスクが集中する |
初心者はまず「小さく始める」という観点から、「都心のワンルーム(区分マンション)」を勧められることが多いですね 。
都心なら賃貸需要が安定していて、区分の最大の弱点である空室リスクを減らせる、というロジックです。
流れ②:新築と中古の徹底比較
次に悩むのが「新築か、中古か」です。
これも目的によって一長一短があります。
新築物件は、金融機関の評価が高く、ローンが非常に組みやすいのが最大のメリットです 。
設備も新しいので当面は修繕費がかからず 、家賃も高く設定できます。
ただ、価格に「新築プレミアム」が上乗せされているため割高で、利回りは低くなります 。
中古物件は、価格がこなれているため高利回りが期待できます 。
特に古い木造物件などは減価償却費を大きく計上できるため、節税効果が高いのも特徴です 。
しかし、金融機関の担保評価が低く、ローンが厳しくなる(期間が短い、金利が高い)こと 、そして即座に修繕リスクが発生するのがデメリットです 。
【新築 vs 中古】徹底比較表
| 項目 | 新築物件 | 中古物件 |
| 物件価格 | 高い(新築プレミアム) | 安い(市場価格) |
| 利回り | 低い | 高い |
| 融資の受けやすさ | 容易(担保価値高) | 困難(特に築古) |
| 修繕リスク | 低い(当面発生しない) | 高い(購入直後から発生) |
| 節税効果 | 低い(減価償却が長期) | 高い(特に築古) |
| 資産価値の下落 | 急(購入直後に下落) | 緩(下落済み) |
どちらが良いとは一概に言えません 。
長期で安定収入を得たい、手間をかけたくない初心者の方は「新築」 、節税目的や高利回りを狙いたい人は「中古」が選択肢になるかと思います。
流れ③:信頼できる不動産会社の選び方
ここが最重要ステップかもしれません。
初心者の場合、アクセスできる情報の「質」と「量」は、すべてパートナーとなる不動産会社にかかっています 。
私が思う「信頼できる会社」の見極めポイントは、以下の通りです。
信頼できる不動産会社 5つの特徴
- デメリットも隠さず説明する 「この物件は駅から遠いのが難点です」「このエリアは空室率が少し高めです」など、マイナス面を正直に話してくれる会社は信頼できます。
- こちらの話を丁寧にヒアリングする
こちらの目的や予算を無視して、自社の売りたい物件だけを押し付けてこないか。 - レスポンスが迅速かつ丁寧
メールや電話の対応が早いのは、顧客を大事にしている証拠です。 - 契約や申込を急かさない
「今決めないと無くなりますよ!」と過度に煽ってくる営業マンは注意が必要です。 - 実績が豊富である
自分が検討したい物件タイプやエリアでの取引実績が豊富かどうかも確認したいですね。
逆に、避けるべき会社の特徴もあります。
注意!避けるべき不動産会社の特徴
- 国土交通省の検索システムで、過去に行政処分歴がある。
- 事務所が乱雑で、書類が山積みになっている。
- 広告のキャッチコピーが「必ず儲かる」など、誇張しすぎている。
- 電話や訪問で、強引に契約を迫ってくる。
面倒でも、必ず複数の会社(最低2~3社)と面談して比較することを強くおすすめします 。
「信頼できる会社」の選び方は分かりましたが、
具体的にどこを比較すれば良い?
会社選びは、不動産投資の成否を分ける最も重要なステップです。
以下の記事では、当サイトが厳選した「初心者に本当におすすめできる不動産投資会社」を、強みや実績、サポート体制の面から徹底的に比較しています。
不動産投資会社おすすめランキングを見る
流れ④:空室・災害リスクの対策
物件購入はゴールではなくスタートです。
購入後、必ず向き合うことになる2大リスクへの対策を考えておきましょう。
空室リスク対策
家賃収入が途絶える、不動産投資で最も怖いリスクです 。
もちろん、一番の対策は「賃貸需要の高い立地の物件を選ぶこと」 ですが、それ以外にもオーナーとしてできる対策はあります。
- 募集内容の改善と露出拡大: 管理会社任せにせず、写真やアピール文句が魅力的かチェックする。
- 清掃の徹底: 内見時の印象は非常に大事です。共用部が汚いと、それだけで敬遠されます。
- 人気設備の導入: 費用対効果が高い「無料Wi-Fi」「宅配ボックス」「モニター付きインターホン」などを導入する。
安易な「家賃の値下げ」は最終手段です 。
一度下げると、物件全体の収益性を恒久的に悪化させてしまうので、慎重になるべきです。
災害リスク対策
日本で不動産を持つ以上、地震、火災、水害のリスクは避けられません 。
- 物件選び(耐震性)
必ず「新耐震基準」(1981年6月1日以降の建築確認)を満たした物件を選びましょう 。旧耐震基準の物件は、熊本地震での倒壊率が新耐震の約4倍だったというデータもあります(出典:国土交通省「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書」) 。 - 物件選び(立地)
購入前に、自治体の「ハザードマップ」を必ず確認し、洪水や土砂災害のリスクが高いエリアでないかチェックします 。 - 保険への加入
必須の対策です。- 火災保険:ローンを組む際にほぼ必須で加入します 。
- 地震保険:地震を原因とする火災や津波は、火災保険では補償されません 。地震保険は火災保険とセットで加入する必要があります 。
- 水災保険:ハザードマップでリスクがある地域なら、火災保険の特約で付帯を検討します 。
流れ⑤:キャッシュフローの計算方法
「利回り」という言葉に踊らされてはいけません。
不動産投資の成否は、最終的に「手元にいくら現金が残るか=キャッシュフロー(CF)」で決まります 。
計算式はシンプルです。
キャッシュフロー = 家賃収入 −(ローン返済額 + 運用経費 + 税金)
利回りが高くても、ローン返済額が大きすぎたり、経費がかさんだりすれば、キャッシュフローはマイナス(=持ち出し)になってしまいます。
特に見落としがちなのが「運用経費(ランニングコスト)」です。
これは家賃収入の20%~30%程度かかると言われています 。
主な運用経費(ランニングコスト)一覧
- 税金
固定資産税、都市計画税(毎年) - 管理・維持費
管理会社への管理委託費(家賃の5%程度が目安)、修繕積立金(区分マンションの場合)、共用部の光熱費 - 入居者対応費
入居者募集の広告料(空室発生時)、退去時の原状回復費用 - その他
火災保険料の更新、給湯器やエアコンなどの突発的な設備交換費用
これらの経費を引いた「実質利回り」 で計算し、さらにそこからローン返済を引いても手元にお金が残るか、厳しくシミュレーションすることが重要です。
「マンションオーナーは儲からない」という話を聞いたことはありませんか?キャッシュフロー計算を学んだ今だからこそ知っておきたい、オーナーが儲からなくなる理由とその構造、失敗を回避する戦略を徹底解説します。
豆知識:団体信用生命保険(団信)は入るべき?
ローンを組む際、「団信」への加入を求められることが多いです 。
これは、もし契約者が死亡・高度障害になった場合、ローン残高がゼロになるという生命保険の一種です 。
メリット: 家族に「借金のない収益不動産」を残せるため、「生命保険代わり」になるとよく言われます 。
デメリット: 必須ではない金融機関もあります 。
保険料は金利に年0.2%~0.3%程度上乗せされるのが一般的なので 、その分、月々の返済額は高くなります。
すでに十分な生命保険に入っている人は、あえて加入しない選択肢もありますね。
結論:正しい不動産投資 始め方
いろいろと解説してきましたが、結論として「不動産投資 始め方」で最も大事なのは、「やめとけ」と言われる理由(リスク)を直視し、それらを潰す準備をすることだと私は思います。
不動産投資は、短期で儲けるギャンブルではなく、「ミドルリスク・ミドルリターン」の長期的な資産形成です 。
成功している人は、例外なく「明確な目的を持ち」「積極的に勉強し」「長期的な視点」を持っています 。
この記事で紹介した「正しい手順」—つまり、しっかり勉強して 、無理のない資金計画を立て 、信頼できるパートナー(不動産会社)を見つける — を踏まえれば、サラリーマン大家が「カモ」になる確率は格段に減らせるはずです。
「始め方」を学んだあなたの、次の一歩は?
この記事で、不動産投資の「始め方」や「流れ」は理解できたかと思います。
しかし、本当の勝負はここからです。
不動産投資で失敗しないために最も重要なのは、営業マンの言葉を鵜呑みにせず、あなた自身が「正しい知識」を身につけること。
そのための最短・最良のステップが、「無料の投資セミナー」に参加して、プロの情報を直接インプットすることです。
以下の記事では、私が実際に調査した「怪しいセミナー」の見抜き方や、初心者でも安心して参加できる「優良セミナー」を厳選してランキング形式で紹介しています。
賢く情報収集を始める
投資の最終判断はご自身の責任で
この記事は、私個人の視点で学んだことや一般的な情報をまとめたものです。
不動産投資は大きな金額が動くため、実際の物件購入やローン契約にあたっては、必ず信頼できる不動産会社やファイナンシャルプランナー、税理士などの専門家にご相談の上、ご自身の責任において最終的な判断を行ってくださいね。
あわせて読みたい「不動産投資」関連記事
- 中古マンションを買って貸す投資で儲ける!始め方と売却戦略
- アパート大家になるには?始め方や必要な資金、儲かるコツを解説
- サラリーマン大家業は儲からない?副業成功の秘訣を全解説
- 不動産収入が副業にならない5つの理由と確定申告のコツ
- なぜ不動産がゴールなのか?私が実践する「ハイブリッド投資戦略」の全貌
