
最近、老後資金の話題になると必ずと言っていいほど「NISAとiDeCoはセットでやるべき」という話が出ますよね。
でも実際に自分で調べてみると「NISAとiDeCoは併用できないケースがある」なんて噂を耳にして、急に不安になっていませんか。
特に将来のために積立NISAとiDeCoを併用して満額まで投資しようと意気込んでいる人ほど、本当に自分ができるのか心配になるものです。
さらに積立NISAとiDeCoは同じ口座で管理できるのかという素朴な疑問や、そもそもiDeCoとNISAを併用するメリットとデメリットを正しく理解できているか不安になることもあるでしょう。
私自身も最初は制度の複雑さに頭を抱えた経験があるので、その気持ちは痛いほどよくわかります。
この記事では複雑な制度の仕組みを整理して、あなたにとって無理のない最適な資産形成の形を見つけるお手伝いをします。
NISAとiDeCoは併用できない?満額積立の罠と最適解を解説
この記事のポイント
- NISAとiDeCoの併用に関する誤解と正しいルールがわかります
- 自分の職業や状況に合わせた最適な使い分け判断ができるようになります
- 無理に満額拠出を目指さずとも資産形成を成功させるコツが掴めます
- 2024年の制度改正による変更点と手続きの簡素化について理解できます
資産形成の正解は「フル活用」という常識の罠

投資の世界に足を踏み入れると、どこを見ても「NISAとiDeCoは両方やって当たり前」「非課税枠は使い切らないと損」という言葉が飛び交っていますよね。
確かに、理論上はそれが最強の資産形成術であることは間違いありません。
しかし、いきなりその「正解」を目指そうとすると、思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあるんです。
ここでは、あえてその「常識」を疑ってみることから始めてみましょう。
積立NISAとiDeCoの併用で満額拠出する戦略の難易度
「よし、老後のためにNISAもiDeCoも限度額いっぱいまでやるぞ!」と意気込むのは素晴らしいことです。
でも、積立NISAとiDeCoの併用で満額拠出する戦略は、想像以上に家計への負担が大きいんですよね。
新NISAの「つみたて投資枠」だけでも月10万円、そこにiDeCoの掛金(例えば会社員なら月2.3万円など)が乗っかってくると、毎月の手取りから12万円以上が投資に消える計算になります。
これ、よほど収入に余裕があるか、生活費を極限まで切り詰めないと続けられないレベルです。
私が大家業を始めた頃もそうでしたが、手元の現金(キャッシュ)が少なくなると、急な出費やライフイベントの時に身動きが取れなくなってしまいます。
「将来のために」と頑張った結果、今の生活が苦しくなっては本末転倒ですよね。
まずは「満額やらなきゃ」というプレッシャーを捨てて、「自分ができる範囲」を見極めることがスタートラインです。
満額積立に固執して今の生活を犠牲にする必要はありません。NISAで資産の土台を作った後、不動産などの「安定収入」へシフトする出口戦略を知っておくと、今の積立額に対する考え方がガラッと変わりますよ。
iDeCoとNISA併用のメリット・デメリット
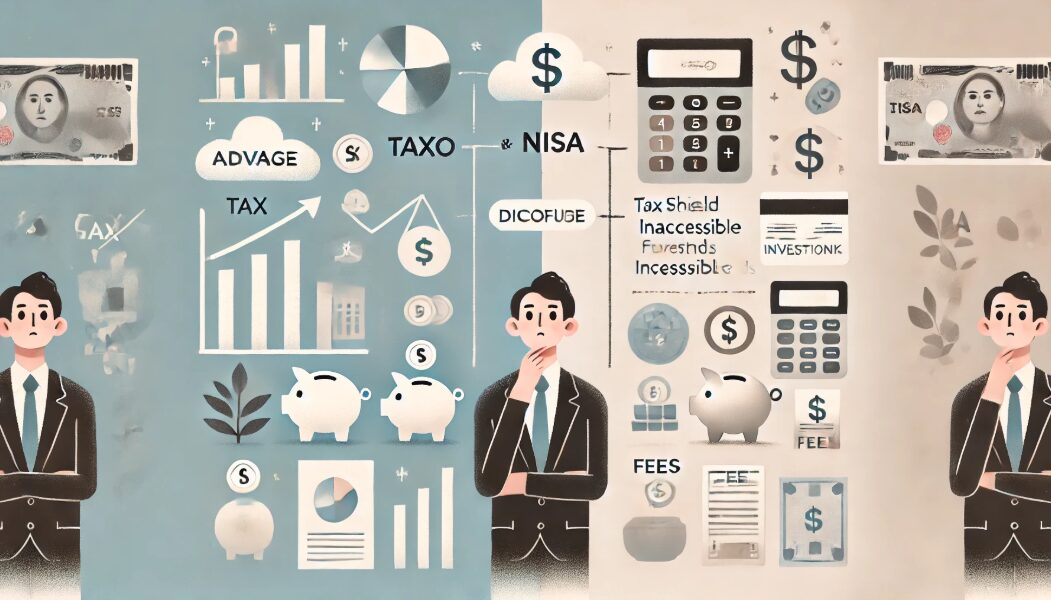
では、無理のない範囲で考えるとして、そもそもiDeCoとNISA併用のメリット・デメリットはどうなっているのでしょうか。
ここを整理しておかないと、自分にとっての「最適解」が見えてきません。
併用のメリット
- 圧倒的な節税効果
iDeCoで所得税・住民税を減らしつつ、NISAで運用益を非課税にする「ダブルの節税」が可能になります - 時間分散の効果
両制度とも積立が基本なので、長期的なリスク分散が自然とできます - 強制的な貯蓄
特にiDeCoは引き出せないので、意志が弱い人でも確実に老後資金が貯まります
併用のデメリット
- 資金拘束のリスク
iDeCoに入れたお金は60歳まで一切触れません。NISAは引き出せますが、併用で手元資金が減るとリスクが高まります - 管理の手間
口座が分かれるため、資産状況の把握やリバランス(配分調整)が少し面倒になります - 手数料コスト
NISAは無料のところが多いですが、iDeCoは加入時や毎月の手数料がかかる場合があります
こうして見ると、メリットは強力ですが、デメリットも無視できませんよね。
特に「資金拘束」は、これから結婚や住宅購入を控えている世代にとっては大きな壁になります。
「どっちもやる」のが正義ではなく、「自分のライフステージに合わせて組み合わせる」のが正解なんです。
NISA・iDeCoの「満額」に疲れていませんか?
「老後のために今の生活を切り詰めるのは本末転倒」とお伝えしました。
実は、NISAの枠を埋め切らなくても、会社員の信用力を活かして資産を加速させる「二階建て」の仕組みがあるのをご存知ですか?
無理な節約生活から脱出し、最短で経済的自由を目指すための「凡人のための戦略」を公開します。
NISAとiDeCoは併用できない?誤解と真実
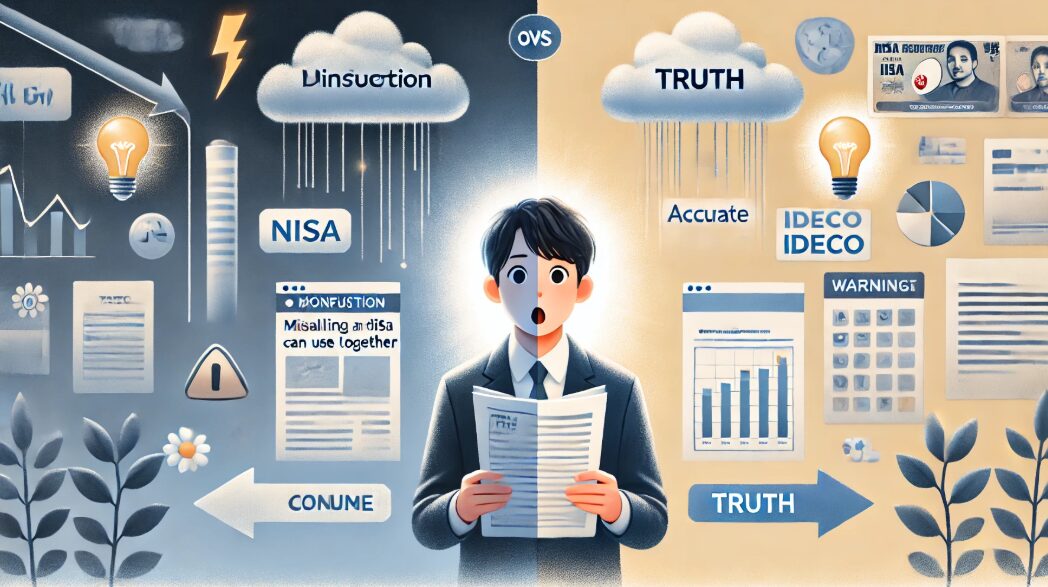
さて、ここからが本題です。
ネットで検索していると「NISAとiDeCoは併用できない」という言葉が出てきてドキッとしたことはありませんか?
結論から言うと、制度自体は「併用可能」です。
ですが、実は「併用できない状況」や「実質的に併用が難しいケース」が存在するのも事実なんですよね。
このあたりの誤解と真実を、私の経験も交えてクリアにしていきましょう。
マッチング拠出利用の会社員は併用不可の可能性
会社員の方で一番気をつけなければならないのが、お勤め先の企業年金制度との兼ね合いです。
特に「マッチング拠出(企業型DCの加入者掛金拠出)」という制度を利用している場合は要注意です。
これは、会社が出してくれる掛金に上乗せして、自分でも給料から掛金を出す仕組みのことですね。
実は、この「マッチング拠出」を利用している場合、iDeCoには加入できません。
(参照:iDeCo公式サイト「iDeCoの仕組み」)
つまり、「企業型DC(マッチング拠出あり)」と「NISA」の併用はOKですが、「マッチング拠出」と「iDeCo」の併用はNG、ということになります。
「えっ、じゃあ自分はどうすれば?」と思いますよね。
基本的には、マッチング拠出をやめてiDeCoに加入するか、そのままマッチング拠出を利用するか選ぶことになりますが、手数料や管理の面でマッチング拠出の方が有利なケースが多いです。
まずは会社の総務や人事に、「うちはiDeCoに入れる制度設計ですか?」と聞いてみるのが確実ですよ。
公務員の併用は可能だが限度額に注意が必要

公務員の方も、もちろんNISAとiDeCoの併用は可能です。
ただ、気をつけてほしいのが「限度額の低さ」です。
公務員の場合、iDeCoの掛金上限は月額1.2万円(年間14.4万円)と、他の職業に比べてかなり低く設定されています。
「NISAもiDeCoもガッツリやりたい!」と思っても、iDeCo側で投資できる金額が限られてしまうんですね。
そのため、公務員の方はiDeCoで所得控除のメリットを最大限取りつつ、メインの資産形成は枠の大きい新NISAで行うという戦略が一般的です。
iDeCoが少ないからといって悲観する必要はありません。
むしろ安定した退職金が見込める公務員だからこそ、iDeCoはおまけ程度に考えて、NISAでリスクを取った運用ができるとも言えますからね。
専業主婦の併用はやめたほうがいいケースとは
次に、専業主婦(第3号被保険者)の方の場合です。
ここが一番、「併用はやめたほうがいい」と言われることが多いポイントかもしれません。
なぜなら、iDeCo最大のメリットである「所得控除(節税)」が、収入のない専業主婦には適用されないからです。
旦那さんの扶養に入っていて自分に所得税・住民税がかかっていない場合、iDeCoで掛金を払っても、税金は安くなりません。
それなのに、iDeCoには口座管理手数料がかかりますし、60歳までの資金ロックも発生します。
つまり、節税メリットがないのにコストと制限だけ背負うことになりかねないんです。
もちろん、「運用益非課税」のメリットはありますが、それはNISAでも同じこと。
手数料無料でいつでも引き出せるNISAの方が、専業主婦の方にとっては圧倒的に使い勝手が良いケースが多いですね。
パートなどで一定の収入があり、税金を払っている場合はiDeCoの検討余地ありですが、そうでなければNISA一本に絞るのが賢明かもしれません。
2024年改正で併用の計算方法が変わる影響
2024年12月から、確定拠出年金(DC)制度に大きな見直しが入るのをご存じでしょうか。
これまで会社の確定給付企業年金(DB)などに加入していると、iDeCoの拠出枠が一律で小さくなってしまうケースが多く、制度としての不公平さが指摘されていました。
しかし今回の改正では、「企業型DC」「DB(確定給付企業年金等)」「iDeCo」を合わせた拠出枠の計算方法が大きく変わり、より実態に即した形で枠が配分されるようになります。
DB加入者でもiDeCoの上限が引き上がる可能性
特に大きな変更点が、DBに加入している会社員のiDeCo上限額です。
従来は一律で月1.2万円までと制限されていましたが、改正後は「DBの掛金相当額」に応じたより柔軟な枠となります。
そのため、DBの給付水準が高くない企業に勤務している人ほど、iDeCo枠が拡大する可能性があります。
人によっては、iDeCoの上限が月2万円まで広がるケースもあるため、「自分はDB加入だからiDeCoは少額しかできない」という従来の常識は通用しなくなります。
企業年金が手厚い人は逆に枠が縮小する可能性も
一方で、企業型DCやDBなどの企業年金がもともと手厚い場合には、改正によってiDeCo枠が縮小する可能性があります。
今回の改正は「公平性の確保」が目的であり、他制度の掛金が多いほど、iDeCoとして使える枠が小さくなる仕組みだからです。
つまり、今後は「企業型DC+DB+iDeCo」の合計が月5.5万円以内に収まるように調整されることになります。
併用しやすくなる方向の制度改正
とはいえ、全体の方向性としては確実に「併用しやすくなる」流れです。
従来は一律でiDeCoの枠が制限されていたDB加入者でも、今回の見直しによって自身の企業年金の実態に応じたより現実的な枠を使えるようになります。
自分の制度がどうなっているのか、そしてどれだけiDeCoが使えるのかを改めて確認しておく価値は大いにあります。
今回の変更は厚生労働省が公開している「確定拠出年金制度の改正について」にも明記されています。(出典:厚生労働省「確定拠出年金制度の改正について」 )
手続きの壁だった事業主証明書の廃止と簡素化

そして、今回の改正で個人的に一番うれしいのが「手続きの簡素化」です。
これまで会社員や公務員がiDeCoを始めようとすると、必ず会社に「事業主証明書」を発行してもらう必要がありました。
「総務にお願いするのが面倒」「投資を始めたことを会社に知られたくない」と感じて、iDeCoを諦めていた人も多かったはずです。
2024年12月から原則不要に
しかし2024年12月からは、この事業主証明書が原則として不要になります。
マイナンバーを活用した企業年金プラットフォームの導入により、国が企業年金情報を連携できるようになるため、加入時に会社へ依頼する必要がなくなる仕組みです。
これにより、NISAとiDeCoを併用したい人にとって、手続き面の心理的なハードルは一気に下がることになります。
ただし例外もあるため要確認
なお、給与からの天引き(事業主払込)でiDeCo掛金を支払う場合には、引き続き会社の確認が必要となるケースもあります。
「完全にゼロになる」というわけではなく、あくまで加入時の事業主証明書が原則不要になるという点は押さえておきましょう。
いずれにせよ、従来より圧倒的に始めやすくなることは間違いありません。
NISAとiDeCoの併用ができないと判断する前に
ここまで読んで、「やっぱり自分には併用はハードルが高いかも…」と思った方もいるかもしれません。
でも、諦めるのはまだ早いです。
「完璧な併用」を目指さなくても、ちょっとした工夫や考え方の転換で、いいとこ取りは十分可能です。
最後に、よくある疑問や悩みを解消して、あなたなりの「最適解」を見つけていきましょう。
積立NISAとiDeCoは同じ口座で管理できるか

積立NISAとiDeCoは同じ口座(証券会社)で管理するのが鉄則です。
厳密には、NISA口座とiDeCo口座は別の契約になるので「一つの口座」ではありませんが、同じ証券会社の管理画面(アプリやウェブサイト)でまとめて見れるようにすることは可能です。
例えば、楽天証券やSBI証券などで両方開設すれば、ログインした後に資産推移を合算して表示してくれます。
これが別々の金融機関だと、いちいち違うサイトにログインして、電卓を叩いて…なんてことになり、管理が面倒で挫折する原因になります。
「NISAはA証券、iDeCoはB銀行」みたいにバラバラにするメリットはほとんどありません。
これから始めるなら、「管理画面を一つにする」ために同じネット証券で申し込むことを強くおすすめします。
これだけで、精神的なハードルがグッと下がりますよ。
では、どこの証券会社ならNISAとiDeCoを使いやすく管理できるのか?ポイント還元や操作性を含め、あなたに最適な金融機関をランキング形式で比較しました。
併用と単独利用のどっちを優先すべきかの基準
「資金的に両方は厳しい…どっちから始めるべき?」という悩みに対する私なりの基準をお伝えします。
迷ったら以下のフローチャートで考えてみてください。
優先順位の考え方
- 直近(5〜10年以内)に使う予定のお金ですか?
YESなら → NISA優先(いつでも引き出せるから) - 所得税・住民税をそこそこ払っていますか?
YESなら → iDeCo優先(節税効果が即金で効くから) - 貯金が苦手でつい使ってしまいますか?
YESなら → iDeCo優先(強制的にロックされるから)
基本的には、「いつでも現金化できる安心感」があるNISAから始めて、余裕が出てきたらiDeCoで節税を狙うという順番が王道です。
無理してiDeCoにお金を入れすぎて、急な出費で借金することになったら意味がないですからね。
優先順位が決まったら、次は具体的な金額のシミュレーションです。まずは100万円を目標に、NISAを活用して最終的に1000万円、そして不動産へと資産を拡大していく現実的な手順も押さえておきましょう。
老後資金はiDeCoとNISAのどっちがいいか
「老後資金」という目的に絞って言えば、やはりiDeCoの方に軍配が上がります。
理由はシンプルで、「所得控除」という確定したリターンがあるからです。
NISAは運用がうまくいけば非課税ですが、元本割れしたら節税メリットはありません。
一方、iDeCoは掛金を払うだけで税金が安くなるので、運用成績がトントンでも「節税分だけプラス」になります。
この「勝てる確率の高さ」はiDeCoならではの強みです。
ただし、しつこいようですが「60歳まで引き出せない」という条件付き。
なので、老後資金の「土台」をiDeCoで固めて、その上にNISAで「上積み」を作っていくイメージが理想的ですね。
積立NISAとiDeCoの併用で満額拠出する戦略

もしあなたが、「どうしても満額拠出を目指したい!」というガッツのある方なら、戦略が必要です。
全てを毎月の給料から出そうとせず、ボーナスや貯金の取り崩しを活用するのがコツです。
iDeCoは毎月定額払いが基本ですが、年単位での拠出(年払い)に変更することも可能です(※金融機関によります)。
また、新NISAのつみたて投資枠は、ボーナス設定などで増額もできます。
毎月の生活費を圧迫しないように、「ボーナスが出た時だけNISAを増やす」とか、「手元の預金からNISA口座に移す」といった柔軟な運用を心がけましょう。
満額はあくまで「上限」であって「ノルマ」ではありません。
生活防衛資金(生活費の半年分〜1年分)を確保した上で、余剰資金を入れるという鉄則だけは守ってくださいね。
受取時の税金で損しないための出口戦略
最後に、少し先の話ですが「出口(受け取り)」についても触れておきます。
NISAは受け取り時も非課税なので何も考えなくてOKです。
問題はiDeCoです。
iDeCoは受け取る時に「雑所得(公的年金等)」や「退職所得」として課税される可能性があります。
特に、会社の退職金とiDeCoの一時金を同じタイミングで受け取ると、税金の控除枠を超えてしまい、思わぬ税金がかかることがあります。
これを防ぐためには、「受け取り時期をずらす」(例:iDeCoを60歳で受け取り、退職金を65歳にするなど)といった出口戦略が必要になります。
今はまだ詳しくわからなくても大丈夫。
「iDeCoは受け取る時にちょっと工夫が必要なんだな」と頭の片隅に置いておくだけで、将来の失敗を防げますよ。
NISAとiDeCoは併用できないという不安の解消
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
「NISAとiDeCoは併用できない」という言葉の裏には、様々な条件や誤解があることがわかっていただけたかと思います。
制度として併用できないのは一部のケースだけで、基本的にはあなたの意思次第で自由に組み合わせが可能です。
大切なのは、制度に振り回されるのではなく、自分の人生設計に合わせて制度を使い倒すことです。
まずはNISAで少額から始めてみるもよし、節税狙いでiDeCoの資料請求をするもよし。
小さな一歩が、将来の大きな安心に繋がっていきます。
ぜひ、あなたに合ったペースで資産形成を楽しんでくださいね。
制度を理解したあなたが、次に知るべき『最適解』
NISAとiDeCoはあくまで「守り」の資産形成です。
しかし、それだけで「攻め」の資産形成を実現するには、莫大な入金力と時間が必要です。
もしあなたが、入金力に自信がない「普通の会社員」だとしても、戦略次第で資産形成のスピードは何倍にも加速できます。私が実践し、多くの会社員が成功している「NISAを土台にしたハイブリッド戦略」の全貌を、ぜひ一度覗いてみてください。
免責事項
本記事は、執筆時点での法令や制度に基づいて作成しておりますが、制度改正等により内容が変更となる可能性があります。
また、投資には元本割れのリスクが伴います。資産運用の最終的な判断は、ご自身の責任において行っていただくようお願いいたします。
具体的な税務処理や個別の制度加入可否については、税理士や勤務先、または各金融機関の公式サイト等で最新の情報を必ずご確認ください。
あわせて読みたい関連記事
