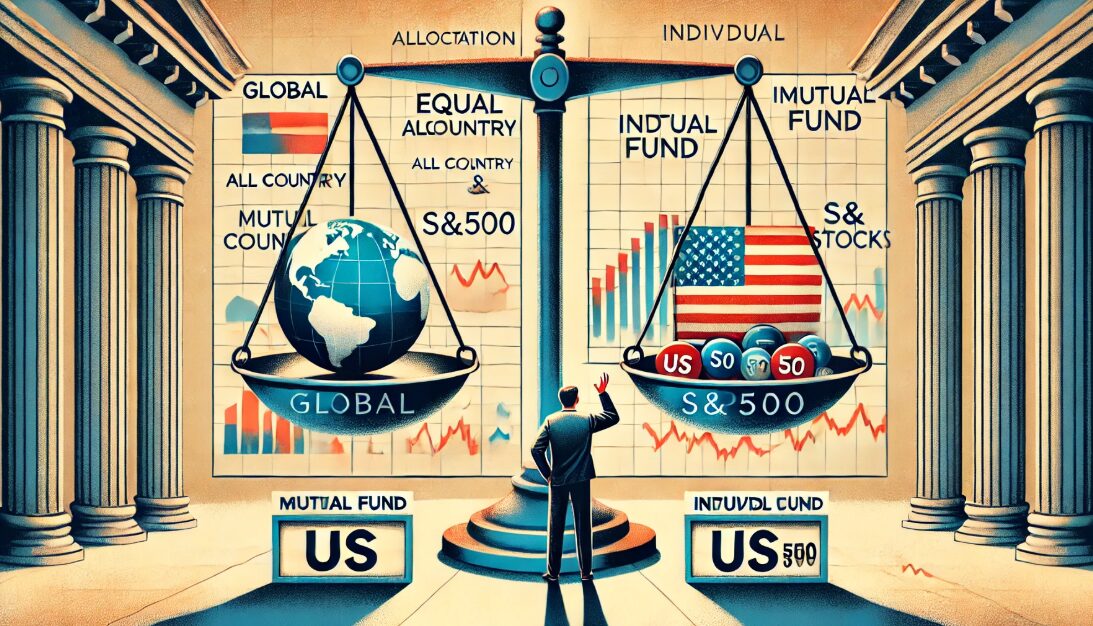
新NISAを始めようと決意したものの、「何を買えばいいの?」という最初の壁に直面していませんか。
積立nisaと個別株、そして投資信託は併用できるのか、どれがいいのかという根本的な選択から、積立NISAにおける分散投資として銘柄をいくつ買うべきか、その組み合わせはどうするかまで、悩みは尽きないかもしれません。
巷では個別株はやめとけという声も聞く一方で、NISAで個別株をやるメリットも気になるところです。また、もし個別株を買った場合、ほったらかしでも良いのでしょうか。
さらに、投資信託に目を向けると、オールカントリーとS&P500は両方買っても大丈夫なのか、その組み合わせのデメリットはないのか、という疑問が浮かびます。
例えば、オールカントリーとS&P500を半々で持つ戦略や、オールカントリーとS&P500の30年にわたるチャート比較で見た過去リターンも知りたい、と考える方も多いでしょう。
この記事では、これらの複雑な疑問に一つひとつ丁寧にお答えし、あなたのNISAでの第一歩を力強く後押しします。
- 投資信託と個別株の基本的な違いと、どちらが初心者に向いているか
- NISAの「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を活かしたポートフォリオの組み方
- 人気のオルカンとS&P500の組み合わせ戦略、メリットやデメリット
- 過去データに基づいた客観的なパフォーマンス比較と、個別株の管理方法
積立nisa個別株どっち?オールカントリーとS&P500を半々で持つ意味
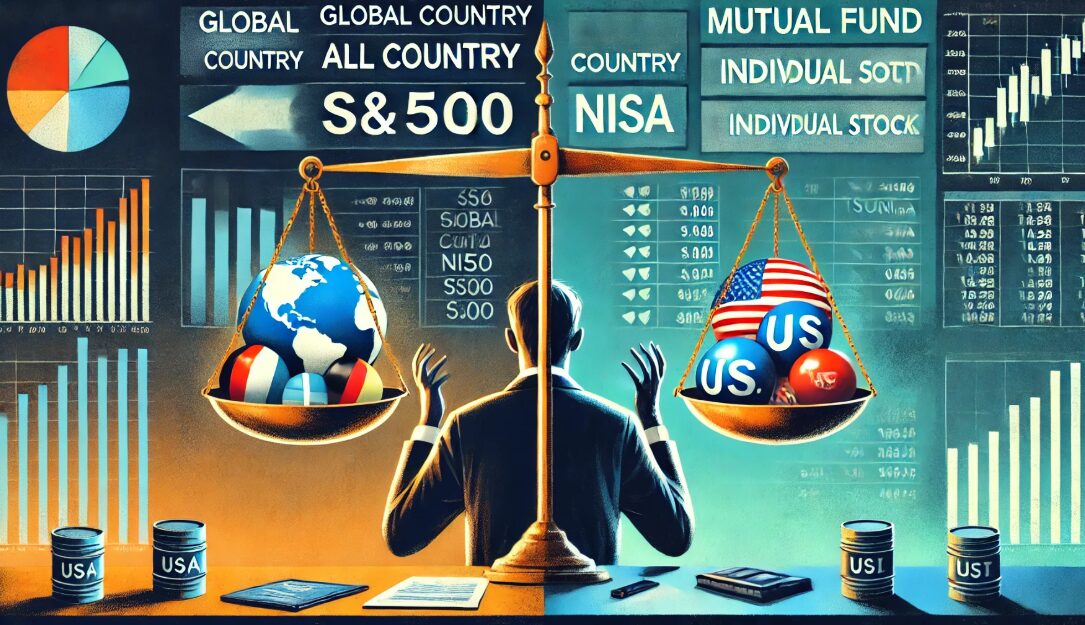
記事のポイント
- 投資信託と個別株の基本的な違いとは?
- 積立nisaで個別株と投資信託は併用できる?
- NISAで個別株をやるメリットと注意点
- なぜ個別株はやめとけと言われるのか?
- NISAで買った個別株はほったらかしでも平気?
- 積立NISAの分散投資、銘柄をいくつ買う?
投資信託と個別株の基本的な違いとは?

NISAで投資を始めるにあたり、まず理解しておきたいのが「投資信託」と「個別株」の基本的な違いです。この二つは、資産を増やすための手段という点は共通していますが、その仕組みや特性は大きく異なります。
最も大きな違いは、誰が運用を行うかという点です。 個別株投資は、あなたが自分でトヨタ自動車やソフトバンクといった特定の企業を選び、その会社の株式を直接購入します。
いつ買い、いつ売るかといった判断もすべて自分自身で行う必要があります。
一方、投資信託は「運用のプロにお任せする」仕組みです。
多くの投資家から集めた資金を一つの大きなファンドとしてまとめ、ファンドマネージャーと呼ばれる専門家が、あらかじめ定められた方針に基づいて複数の株式や債券などに分散して投資・運用を行います。
この違いから、投資対象やリスクの大きさも変わってきます。
個別株は特定の企業に集中投資するため、その企業の業績が良ければ大きなリターン(ハイリターン)を期待できる一方、業績が悪化すれば株価が大きく下落するリスク(ハイリスク)も伴います。
これに対して投資信託は、一つの商品で数十から数千もの銘柄に分散投資されているため、一つの企業の不調が全体の資産に与える影響は限定的で、リスクを抑えた運用がしやすいと考えられます。
| 比較点 | 投資信託 | 個別株 |
| 運用主体 | 運用のプロ(ファンドマネージャー) | 投資家自身 |
| 投資対象 | 複数の株式や債券などに分散 | 特定の企業 |
| リスク | 分散によりリスクは低減されやすい | 集中投資のためリスクは高め |
| リターン | 相対的に安定的(ミドルリターン) | 企業の成長次第で大きなリターンも(ハイリターン) |
| 必要知識 | 銘柄選びの手間や専門知識は比較的少ない | 企業分析などの深い知識や情報収集が必要 |
積立nisaで個別株と投資信託は併用できる?
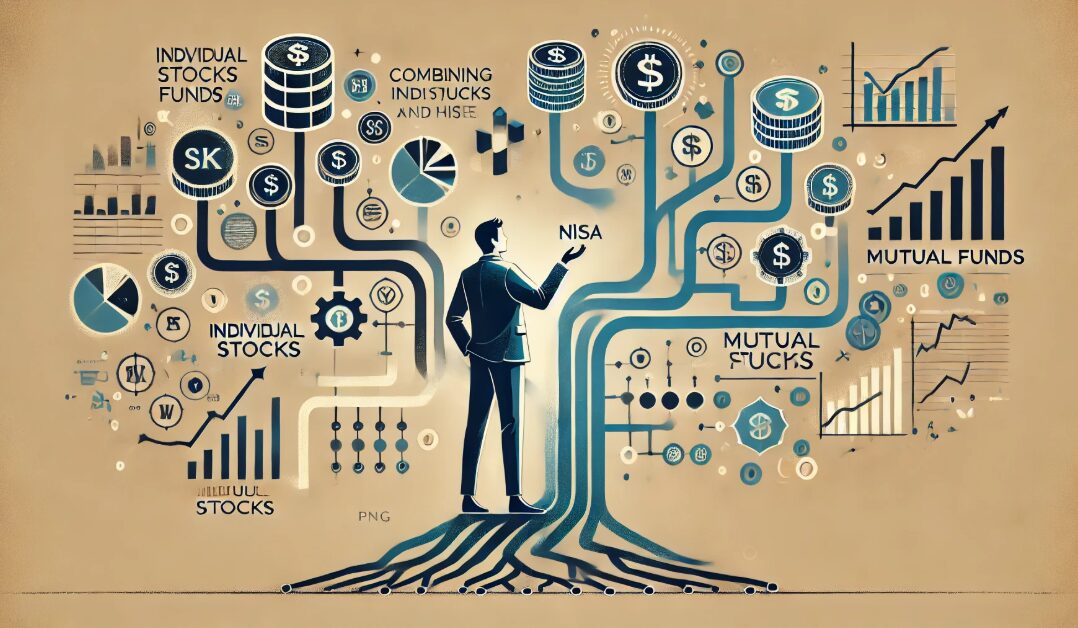
はい、2024年から始まった新NISAでは、個別株と投資信託を非常に柔軟に併用することが可能です。
これは、新NISAが持つ「つみたて投資枠」と「成長投資枠」という2つの枠を、同時に利用できるようになったことによる大きなメリットです。
それぞれの枠の特性を理解することで、自分に合った併用戦略を立てることができます。
- つみたて投資枠
年間120万円まで投資できるこの枠は、主に長期・積立・分散投資に適した投資信託が対象です。
金融庁が定めた基準をクリアした、比較的リスクの低い商品が揃っています。したがって、資産形成の土台として、ここでコツコツと投資信託を積み立てるのが基本戦略となります。 - 成長投資枠
年間240万円まで投資できるこちらの枠は、つみたて投資枠の対象商品に加えて、個別株や、より幅広い種類の投資信託、ETF(上場投資信託)などを購入できます。
資産形成の土台にプラスアルファの要素として、ここで個別株に挑戦したり、特定のテーマを持つ投資信託を加えたりといった応用戦略が可能になります。
例えば、「つみたて投資枠で全世界株式のインデックスファンドを毎月5万円積み立てつつ、成長投資枠で応援したい企業の個別株や、配当金狙いの高配当株を年に数回購入する」といった使い方ができます。
このように、新NISAでは安定的な資産形成を目指す「守り」の投資(投資信託の積立)と、より高いリターンを狙う「攻め」の投資(個別株)を、一つの制度の中で両立させることが可能です。
どちらか一方を選ぶ必要はなく、ご自身の目標やリスク許容度に合わせて、最適なバランスで組み合わせられるのが新NISAの大きな魅力です。
NISAで個別株をやるメリットと注意点
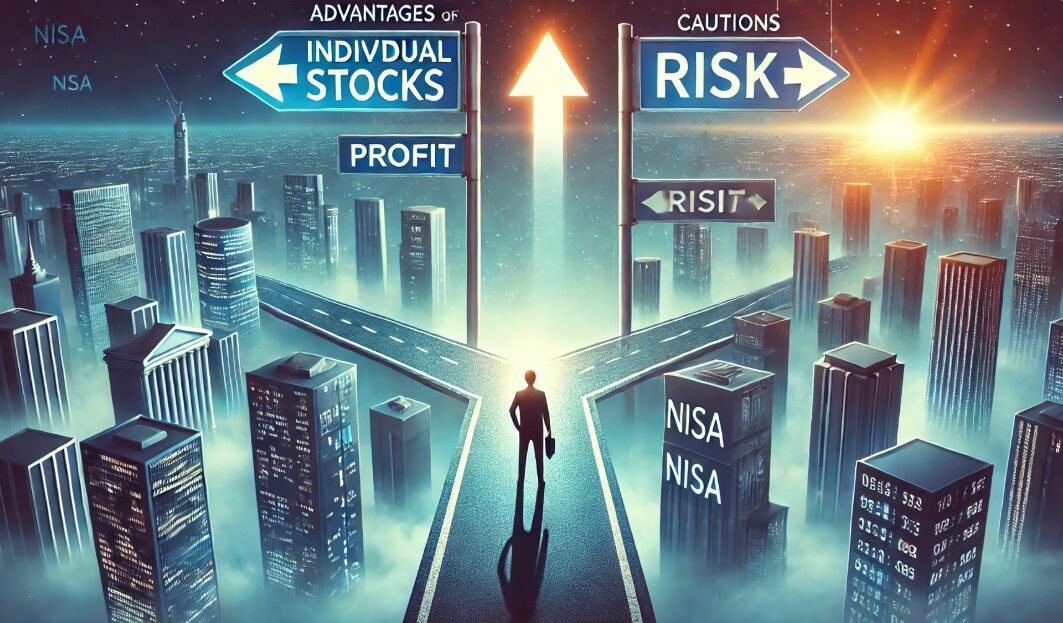
投資信託が初心者にとって王道である一方、NISAで個別株に投資することにも独自のメリットが存在します。これを理解することで、より多角的な資産形成を目指せます。
NISAで個別株をやる最大のメリットは、大きな値上がり益(キャピタルゲイン)を非課税で得られる可能性があることです。
応援したい企業や成長を期待する企業の株価が数倍に成長した場合、その利益がまるごと手元に残るのは非常に魅力的です。
また、企業によっては配当金や株主優待といった形で、株主に利益を還元しています。NISA口座で受け取る配当金も非課税になりますし、株主優待は生活を豊かにする楽しみの一つにもなり得ます。
さらに、個別株投資は、経済や社会の動きをより身近に感じるきっかけにもなります。
自分が株主となった企業のニュースや業績に関心を持つようになり、自然と金融リテラシーが高まっていくという学びの側面も大きなメリットと言えるでしょう。
一方で、注意点も存在します。前述の通り、個別株は投資信託に比べてリスクが高くなります。
投資した一社の業績が悪化したり、不祥事が起きたりすると、株価が大きく下落し、資産価値が半分以下になる可能性もゼロではありません。
また、数千社ある上場企業の中から将来性のある一社を見つけ出すには、財務諸表を読み解く知識や、業界動向を分析する時間と労力が必要です。
購入後も、定期的に業績をチェックし、適切なタイミングで売却を判断する必要があるため、投資信託のような「ほったらかし」が難しい側面があります。
これらのことから、NISAで個別株に挑戦する場合は、まず少額から始める、資産全体の一部に留める、そして何よりも自分自身で企業についてしっかり調べるという姿勢が大切になります。
なぜ個別株はやめとけと言われるのか?
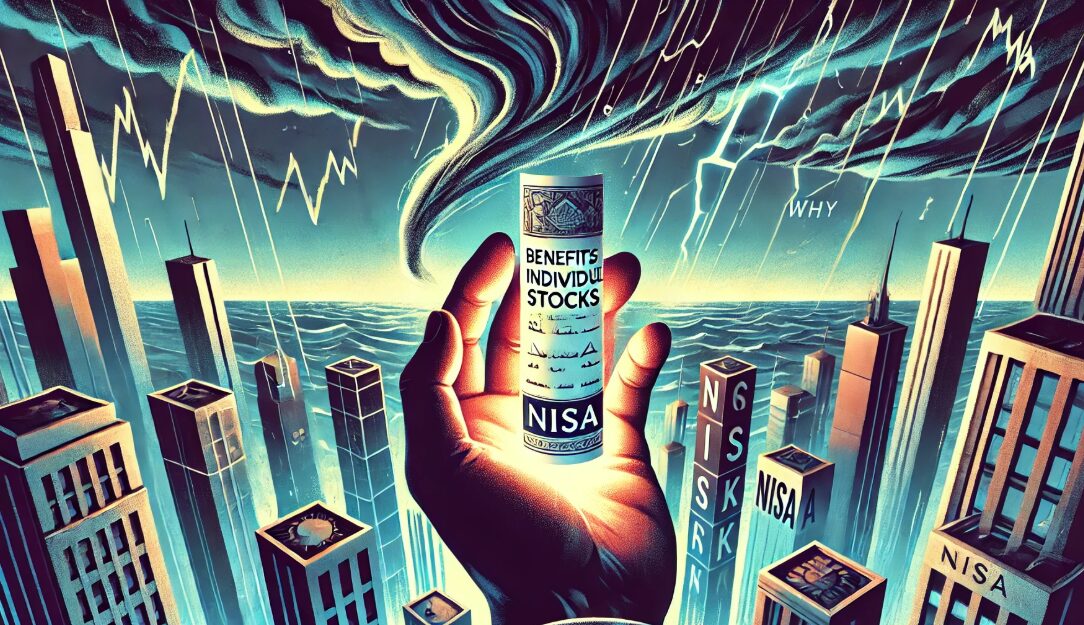
「初心者は個別株はやめとけ」という意見をよく耳にしますが、これには明確な理由がいくつか存在します。
感情論ではなく、多くの過去のデータや経験則に基づいた合理的なアドバイスと捉えることができます。
最大の理由は、市場平均(インデックス)に勝ち続けることの難しさにあります。
S&P500や全世界株式といったインデックスファンドは、市場全体の平均的なリターンを目指すものです。
これに対し個別株投資は、その平均を上回る成績(アウトパフォーム)を目指す行為ですが、これを長期的に達成できる投資家は、プロを含めてもごく一部であるというデータが数多く存在します。
つまり、多くの時間と労力をかけて銘柄を選んでも、結果的にインデックスファンドに劣る可能性が高いのです。
もう一つの理由は、銘柄選びと管理の難しさです。
日本だけでも約4,000社の上場企業があり、その中から将来にわたって成長し続ける一握りの企業を見つけ出すのは至難の業です。また、時代と共に市場を牽引する企業は大きく入れ替わります。
2000年時点での世界の時価総額トップ10企業のうち、20年以上経った今もトップ10に残っているのはごくわずかです。
成長し続ける企業に乗り換え続ける「銘柄のメンテナンス」を個人が何十年も行うのは、非常に困難であると言わざるを得ません。
さらに、一つの銘柄に集中投資することは、分散が効かないことによるリスクを伴います。その企業が倒産すれば、投資した資産価値はゼロになる可能性もあります。
これらの理由から、「まずは市場全体に分散投資できるインデックスファンドで資産形成の土台を築くべきであり、専門的な知識や多大な労力が必要な個別株投資に初心者が手を出すのは慎重になるべきだ」という意味合いで、「個別株はやめとけ」と言われることが多いのです。
NISAで買った個別株はほったらかしでも平気?

投資信託、特にインデックスファンドの場合は、定期的なリバランス(資産配分の調整)が自動的に行われるため、「ほったらかし投資」が有効な戦略とされています。
では、NISAで買った個別株も同じように「ほったらかし」で良いのでしょうか。
この問いに対する答えは、「基本的には難しいが、銘柄の特性による」と言えます。
多くの個別株の場合、ほったらかしは推奨されません。
その理由は、企業を取り巻く環境が常に変化し続けるからです。競合の出現、新しい技術の登場、経営方針の転換、景気の変動など、株価に影響を与える要因は無数にあります。
昨日まで優良企業だった会社が、数年後には競争力を失っているということも珍しくありません。
そのため、定期的に企業の業績(決算短信など)をチェックし、成長が続いているか、当初の投資シナリオに変化はないかを確認し続ける必要があります。
もし業績が悪化したり、成長が鈍化したりした場合には、売却を検討する必要も出てきます。
ただし、例外的に「ほったらかし」に近い運用が可能な個別株も存在します。
例えば、数十年にわたり圧倒的な競争優位性を持ち、景気の変動に左右されにくい安定したビジネスモデルを確立している巨大企業や、生活に不可欠なサービスを提供しているインフラ企業などが挙げられます。
このような企業の株は、長期的な成長や安定した配当を期待して、頻繁な売買をせずに持ち続けるという戦略も考えられます。
とはいえ、そのような企業であっても未来は不確実です。
したがって、NISAで個別株を保有する場合は、完全に放置するのではなく、少なくとも年に数回は企業の状況を確認する習慣をつけることが、大切な資産を守る上で賢明な姿勢と言えるでしょう。
積立NISAの分散投資、銘柄をいくつ買う?

「分散投資のために、銘柄はいくつ買えばいいですか?」というのも、NISAを始める方が抱く典型的な疑問です。たくさんの銘柄に分けた方がリスクが下がるように感じますが、必ずしもそうとは限りません。
まず結論から言うと、初心者であれば、無理に複数の銘柄を組み合わせる必要はなく、質の高い投資信託を1本だけ選ぶことから始めるのが最もシンプルで効果的な戦略です。
なぜなら、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」のような全世界株式インデックスファンドは、それ自体が究極の分散投資を実現しているからです。
この1本を購入するだけで、世界中の先進国から新興国まで、数千社もの企業に自動的に資産を分散させることができます。
地域や業種をまたいで広く分散されているため、これ以上自分で銘柄を組み合わせて分散効果を高めようとする必要性は低いのです。
では、複数銘柄を組み合わせるのはどのような場合でしょうか。
これは、自分の考えに基づいて特定の地域や資産への投資比率を高めたい、という意図がある場合です。
例えば、「全世界株式をベースに、特に成長が期待できる新興国の比率をもう少し高めたい」と考えた場合、全世界株式ファンドに加えて、新興国株式ファンドを少しだけ買い足す、といった組み合わせが考えられます。
しかし、注意点もあります。例えば、「全世界株式ファンド」と「S&P500(米国株式)ファンド」を組み合わせると、全世界株式ファンドの中にもともと約6割含まれている米国株の比率がさらに高まり、意図せず米国への集中投資になってしまう可能性があります。
したがって、初心者のうちは、まず優れた投資信託を1本選び、長期で積み立てることを基本としましょう。
投資に慣れてきて、自分なりの投資戦略が描けるようになってから、2〜3銘柄程度の組み合わせを検討するのが良いでしょう。
闇雲に銘柄数を増やすことは、管理の手間が増えるだけで、必ずしも分散効果を高めるわけではないことを覚えておくことが大切です。
オールカントリーS&P500を半々で買う。積立nisa個別株はどっちがいい?

- インデックス投資の王道2銘柄を比較
- オルカンとS&P500両方買う組み合わせとデメリット
- オールカントリーとS&P500を半々で持つ戦略
- オルカンとS&P500の30年チャート比較
- 積立nisa個別株どっち、オルカンS&P500半々の総括
インデックス投資の王道2銘柄を比較
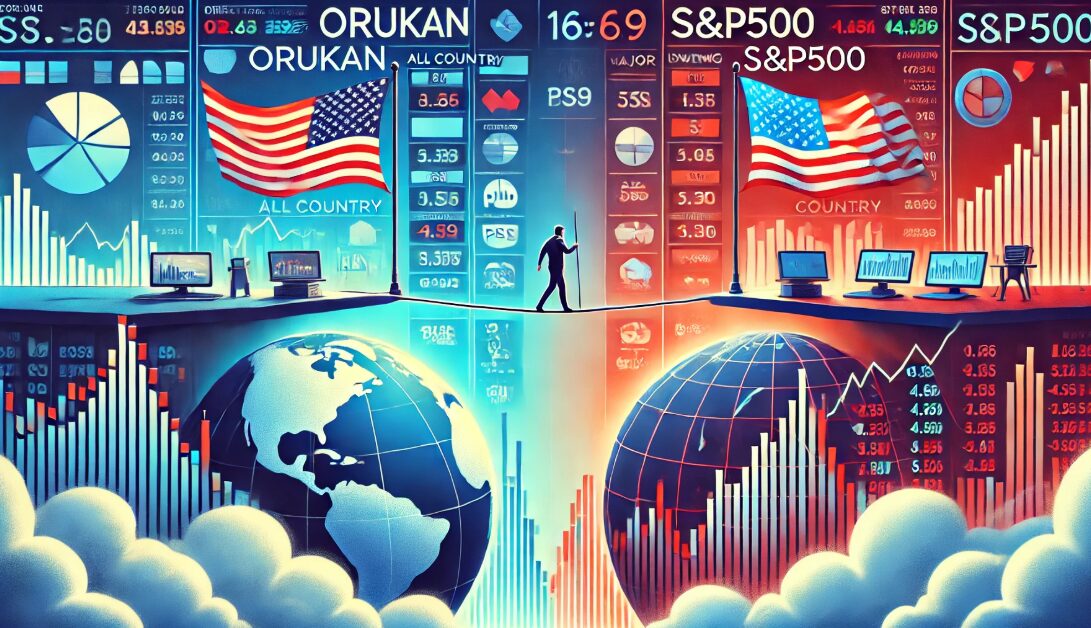
投資信託の中でも、特にNISAのつみたて投資枠で絶大な人気を誇るのが、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」(通称:オルカン)と、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」です。
この2つは、インデックス投資の王道とも言える存在ですが、その投資対象と哲学には明確な違いがあります。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
オルカンは、その名の通り、日本を含む世界中の先進国および新興国の株式市場全体に投資する投資信託です。
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスという指数に連動することを目指しており、この1本で世界経済の成長をまるごと享受しようというコンセプトです。
最大の特長は、徹底した「地域分散」がなされている点です。投資先の国は約50カ国、銘柄数は数千に及びます。
これにより、特定の国や地域の経済が不調に陥ったとしても、他の地域の成長がカバーしてくれる効果が期待でき、リスクを抑えた安定的な運用を目指せます。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
一方、S&P500は、米国の代表的な企業約500社に集中して投資する投資信託です。
Apple、Microsoft、Amazonといった、世界をリードする巨大IT企業をはじめ、各業界のトップ企業で構成されており、米国経済の成長そのものに賭ける、というコンセプトになります。
過去数十年、米国経済は世界経済を力強く牽引してきました。そのため、S&P500はオルカンを上回る高いリターンを記録してきた歴史があります。
「これからも米国の成長は続くだろう」と考える投資家にとっては、非常に魅力的な選択肢です。
要するに、「世界全体に広く網を張り、安定的に成長の果実を得たい」と考えるならオルカン、「世界の中心である米国の成長力を信じ、より高いリターンを狙いたい」と考えるならS&P500が、それぞれ適していると言えるでしょう。
オールカントリーとS&P500は両方買っても大丈夫?組み合わせとデメリット
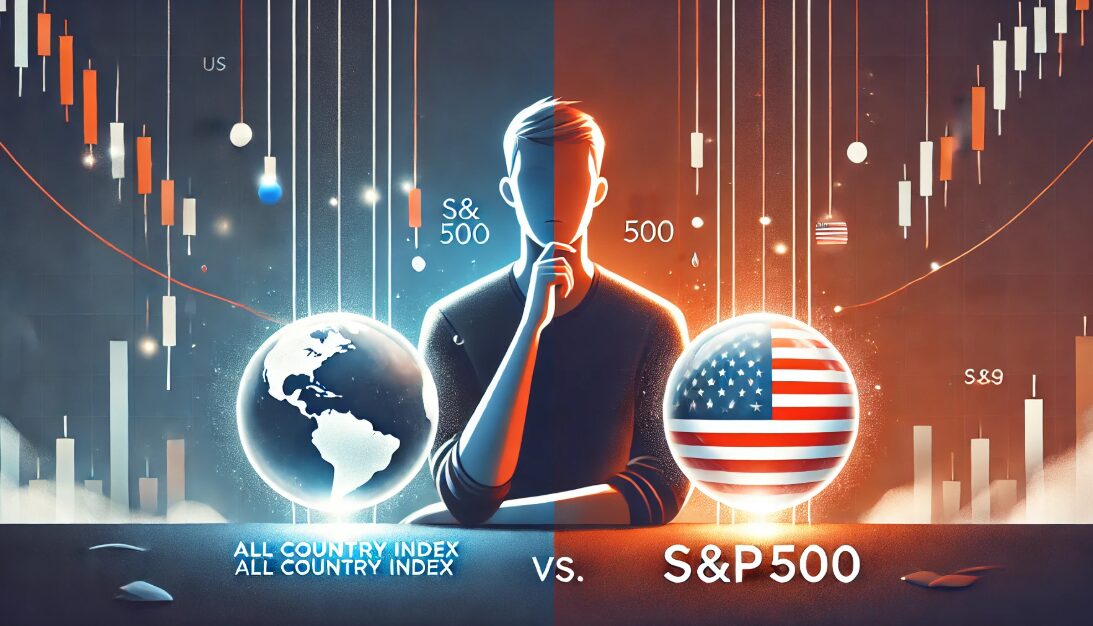
「オルカンとS&P500、どちらか一つに絞れないなら、両方買ってしまえばいいのでは?」と考える方は少なくありません。
実際に、この2つのファンドを組み合わせて保有すること自体は、全く問題ありません。
しかし、その組み合わせがもたらす効果とデメリットを正しく理解しておくことが大切です。
この組み合わせの最大のメリットは、自分好みのポートフォリオを構築できる点にあります。
「全世界に分散投資しつつも、特に成長が期待できる米国の比率をもう少し高めたい」という意図を実現できます。
例えば、オルカンとS&P500を8:2の割合で保有すれば、ポートフォリオ全体の米国比率を、オルカン単体で持つよりも高めることが可能です。
一方で、デメリットも存在します。最も注意すべき点は、思った以上に分散効果が高まらないことです。
オルカンの構成比率を見ると、実はその約60%は米国株式で占められています。つまり、オルカン自体がすでに「S&P500を多く含んだファンド」なのです。
そこにさらにS&P500を追加するということは、意図せず米国株式への集中度を高めてしまう結果につながります。
例えば、オルカンとS&P500を半々で持つと、ポートフォリオ全体の約80%が米国株式ということになり、「全世界分散」という当初の目的からは少しずれてしまう可能性があります。
リスク分散を最大の目的とするならば、この組み合わせが最適とは言えないかもしれません。
また、保有するファンドが2本になることで、管理がわずかに煩雑になるという点も、小さなデメリットとして挙げられます。
したがって、オルカンとS&P500を両方買う戦略は、「米国の成長を信じ、より積極的にリターンを狙いたい」という明確な意図がある場合には有効ですが、「リスク分散のため」と考えている場合は、その効果が限定的であることを理解しておく必要があります。
オールカントリーとS&P500を半々で持つ戦略

オルカンとS&P500を「半々(50%:50%)」で組み合わせる戦略は、両方のファンドに魅力を感じ、どちらか一方に絞りきれない投資家にとって、一つの具体的な解決策となります。
この戦略がどのような結果をもたらすかを考えてみましょう。
この戦略の最大の特徴は、オルカン単体よりも米国への投資比率を高め、S&P500単体よりも世界への分散を効かせるという、両者の中間的なポートフォリオになる点です。
具体的に見ていくと、前述の通りオルカンの約60%は米国株です。一方、S&P500はもちろん100%が米国株です。
この2つを半々で保有すると、ポートフォリオ全体に占める米国株の割合は、(60% × 0.5) + (100% × 0.5) = 30% + 50% = **約80%**となります。
残りの約20%が日本を含む米国以外の先進国や新興国への投資となります。
これは、「米国の力強い成長を信じているが、万が一米国経済が長期的に停滞した場合に備えて、他の地域の成長も取りこぼしたくない」と考える投資家にとっては、合理的な配分と言えます。
期待できるリターンも、リスク(価格変動の大きさ)も、オルカンとS&P500のちょうど中間程度になるイメージです。
ただし、注意点として、これはS&P500単体で保有するよりは分散が効いていますが、オルカン単体で保有する場合に比べると、米国市場への依存度がかなり高まります。
そのため、米国市場が不調に陥った場合、オルカン単体よりも大きな影響を受ける可能性があります。
要するに、オルカンとS&P500を半々で持つ戦略は、全世界分散の安定感と米国集中の成長力を「良いとこ取り」しようとする試みですが、その反面、どちらのメリットも中途半端になる可能性があることを理解した上で選択することが求められます。
オルカンとS&P500の30年チャート比較
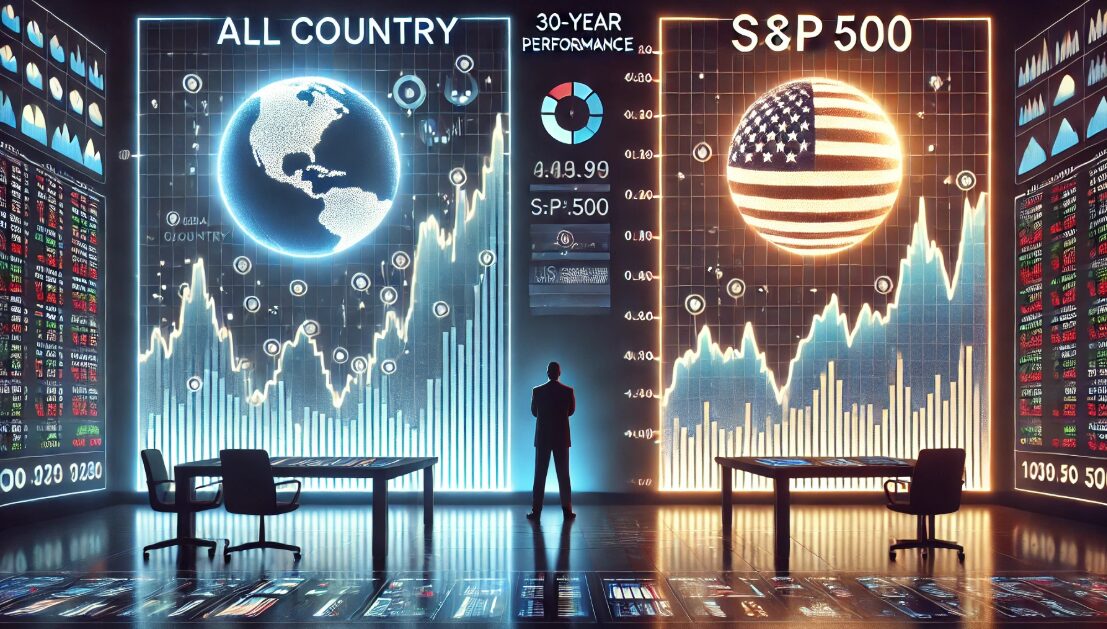
投資信託を選ぶ上で、過去のパフォーマンスが将来を保証するわけではありませんが、長期的にどのような値動きをしてきたかを知ることは、非常に重要な判断材料となります。
ここでは、オルカンとS&P500の連動対象である株価指数の、過去30年以上にわたる長期的なリターンを比較してみましょう。
一般的に、過去30年という長い期間で見ると、S&P500(米国株式)が全世界株式(オルカンの指数)を一貫して上回る高いパフォーマンスを示してきました。
特に、2010年代以降のITバブルや近年のハイテク企業の躍進により、米国市場は他の地域を圧倒する成長を遂げ、その差は顕著になっています。
しかし、歴史をさらに遡ると、常に米国が優位だったわけではありません。
例えば、2000年代前半のITバブル崩壊後や、新興国が著しい成長を見せた時期など、全世界株式がS&P500を上回るパフォーマンスを示した期間も存在します。
また、暴落時の動きも重要です。リーマンショックやコロナショックといった世界的な金融危機では、どちらの指数も大幅に下落しました。
オルカンは全世界に分散しているとはいえ、その半分以上を米国が占めるため、米国市場の暴落から逃れることはできず、S&P500と非常に似た値動きをする傾向があります。
これらの歴史から読み取れるのは、以下の2点です。
- リターン重視ならS&P500に軍配
過去の実績だけを見れば、より高いリターンを求めるならS&P500が魅力的に映ります。 - 未来は不確実
過去30年が米国優位の時代だったからといって、未来の30年も同じとは限りません。
今後、米国以外の国や地域が台頭する可能性を考慮するなら、オルカンで広く分散しておくことの価値が高まります。
結局のところ、チャート比較はあくまで過去の事実です。
このデータを基に、あなたが未来の世界経済をどう予測し、どちらのシナリオに賭けたいかを考えることが、銘柄選択の鍵となります。
積立nisa個別株どっち、オルカンS&P500半々の総括
この記事では、NISAで「何を買うか」という疑問に対し、投資の基本的な選択肢から具体的な戦略までを解説してきました。
最後に、あなたが最適な一歩を踏み出すための要点をまとめます。
- 投資信託はプロに任せる分散投資、個別株は自分で選ぶ集中投資
- 新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能
- 併用すれば、投資信託の積立と個別株投資を両立できる
- 個別株は大きなリターンが魅力だが、銘柄選びが難しくリスクも高い
- 初心者は、1本で世界に分散できる投資信託から始めるのが王道
- 銘柄数は、まず1本からで十分な分散効果が期待できる
- オルカンは世界分散で安定的、S&P500は米国集中で高リターンを狙う
- オルカンとS&P500を両方買うと、米国への集中度が高まる
- 半々戦略は、オルカンとS&P500の中間的なリスク・リターンを目指すもの
- 過去30年のリターンではS&P500が優位だが、未来は不確実
- 個別株の「ほったらかし」は基本的に難しく、定期的な見直しが必要
- 自分の投資目的とリスク許容度を明確にすることが最も大切
- 「守り」の資産形成か、「攻め」のリターン追求かを考える
迷ったら、最も分散が効いているオルカン1本から始めるのが無難です。
慣れてきたら、サテライトとしてS&P500や個別株を加えても良い考えです。
