
「投資しないとやばい」という言葉を耳にして、漠然とした不安を感じていませんか。
日本における投資しない人の割合は依然として高く、そもそも、なぜ投資をやらないのかという疑問を持つ方も多いでしょう。
確かに、投資しないメリットや、性格的に投資しない方がいい人がいるのも事実です。
しかし、何もしない投資しない生き方や投資しない人生を選んだ結果、将来の投資しない人の末路として、インフレや経済の変化によって生まれる投資しない人との格差に直面するかもしれません。
一方で、ほったらかし投資は危険ではないか、あるいは本当に株だけで生きていけるのか、といった具体的な疑念や、そもそも投資をしないリスクとは何か、という根本的な問いもあるはずです。
この記事では、そうしたあなたの不安や疑問に一つひとつ丁寧にお答えしていきます。
この記事は、そもそも【必見】「本当に投資しない方がいい人の特徴」とそれでも始めるべき理由とは何か、という大きなテーマを解説した特集の一部です。
記事のポイント
- 投資をしないことの具体的なリスクがわかる
- 投資をすべきでない人の特徴が明確になる
- 初心者でも始めやすい投資のコツが学べる
- 将来に向けた資産形成の必要性が理解できる
なぜ「投資しないとやばい」と言われるのか

- 日本における投資しない人の割合
- そもそも、なぜ投資をやらないのか
- 意外と知らない投資しないメリット
- 根本的に投資しない方がいい人の特徴
- 時間と共に広がる投資しない人との格差
- 物価上昇?投資をしないリスクとは
- 貯金だけの「投資しない生き方」の現実
- 「投資しない人生」という選択肢
- 「ほったらかし投資は危険」は本当か
- 最終的に株だけで生きていけるのか
- 投資しない人の末路と「投資しないとやばい」訳
日本における投資しない人の割合

結論から言うと、日本の個人金融資産に占める投資の割合は、欧米諸国と比較して著しく低いのが現状です。
日本銀行調査統計局の「資金循環の日米欧比較」によると、日本の家計金融資産のうち「現金・預金」が50%以上を占めています。
これは、資産の半分以上を、ほとんど増えることのない銀行口座に置いていることを意味します。
一方で、アメリカでは「株式・投資信託」の合計が50%を超えており、資産の大部分を積極的に運用に回していることがわかります。
この差が、過去20年間で日本の家計資産が約1.4倍しか増えなかったのに対し、アメリカでは約3.4倍に増加した大きな要因の一つと言えるでしょう。
日米の家計金融資産構成の比較
このデータは、日本人といかに「貯蓄志向」が強いかを明確に示しています。
もちろん、近年はNISAの拡充などもあり投資を始める人は増えていますが、まだ「貯蓄から投資へ」の移行は道半ばです。
| 資産項目 | 日本 🇯🇵 | アメリカ 🇺🇸 |
| 現金・預金 | 50.9% | 11.7% |
| 投資信託・株式等 | 19.6% | 53.3% |
| 保険・年金 | 24.6% | 27.7% |
(参照:日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較」)
このように、データ上でも日本人がいかに投資に対して消極的かが分かります。
多くの人が同じように投資をしていないから安心、というわけではなく、むしろ世界的に見れば資産を増やす機会を逃している可能性が高いのです。
そもそも、なぜ投資をやらないのか
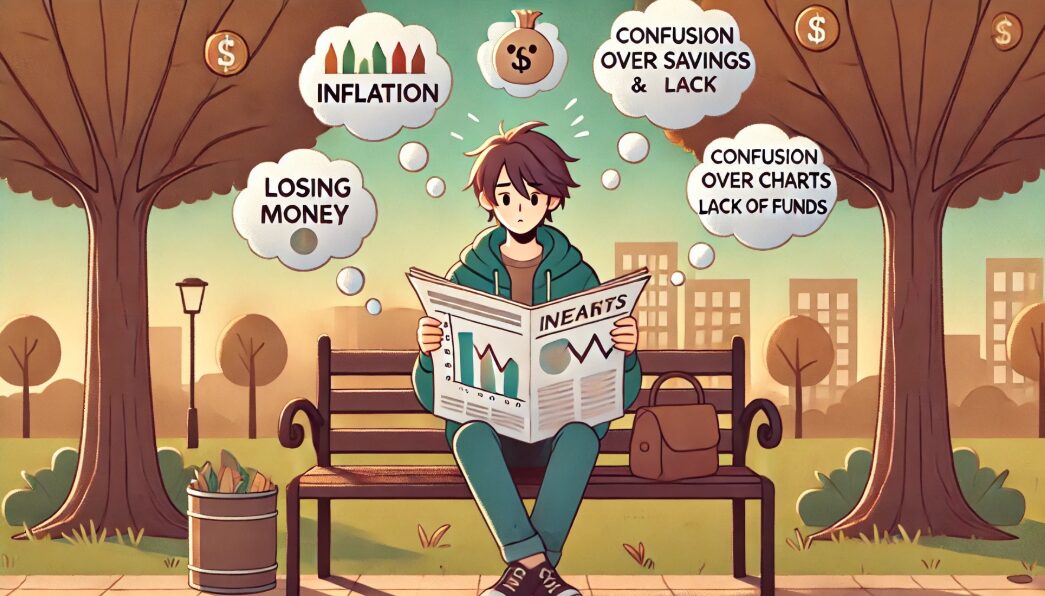
日本人が投資に踏み出せない理由は、主に3つの心理的な壁があると考えられます。
金融庁の調査によれば、投資未経験者が資産運用を行わない理由として最も多いのが「余裕資金がないから」。
次いで「資産運用に関する知識がないから」、そして「購入・保有することに不安を感じるから(損をするのが怖い)」という回答が続いています。
これは、多くの人が投資に対して次のようなイメージを持っていることの表れです。
投資に対する一般的なイメージ
- まとまったお金がないと始められない
- 専門的な知識が必要で難しそう
- ギャンブルのようで、元本割れのリスクが怖い
特に日本では、長らく「お金の話はタブー」とされてきた文化的背景や、学校教育で金融に関する実践的な知識を学ぶ機会が少なかったことも影響しています。
このため、「貯金は善、投資は悪」といった古い価値観が根強く残り、リスクを必要以上に恐れてしまう傾向があるのです。
しかし、実際には月々1,000円程度の少額から始められる積立投資も多く、基本的な知識さえ身につければ、リスクを管理しながら資産形成を目指すことは十分に可能です。
多くの日本人が投資を避けてきた歴史的背景と、今その意識が急速に変わりつつある理由については、以下の記事で詳しく解説しています。
意外と知らない投資しないメリット

一方で、あえて投資をしない選択にもメリットは存在します。
投資が推奨される風潮の中では見過ごされがちですが、これらの点を理解しておくことも大切です。
最も大きなメリットは、精神的な平穏を保てることでしょう。
投資は、日々の価格変動が避けられません。経済ニュースを見るたびに自分の資産額が上下することに、ストレスを感じる人は少なくありません。
投資をしなければ、そのような価格変動リスクや元本割れの心配から解放されます。
また、時間的な節約もメリットの一つです。
どの金融商品を選ぶか、いつ売買するかなどを判断するためには、情報収集や学習に多くの時間を費やす必要があります。
投資をしなければ、その時間を趣味や自己研鑽、家族と過ごす時間など、他の有意義な活動に充てることができます。
注意点:機会損失とのトレードオフ
投資をしないメリットは、資産が増える可能性を放棄する「機会損失」と引き換えに得られるものです。
精神的な安定や時間の節約は重要ですが、将来のインフレなどでお金の価値が目減りするリスクがあることも忘れてはなりません。
このように、投資をしない選択は短期的な安心感をもたらしてくれます。
ご自身のライフプランや価値観と照らし合わせて、これらのメリットが将来のデメリットを上回るかを考えることが重要になります。
根本的に投資しない方がいい人の特徴

全ての人に投資が向いているわけではありません。
場合によっては、投資を始めることでかえって資産を減らしてしまう可能性もあります。
ここでは、一般的に「投資しない方がいい」と言われる人の特徴を4つ紹介します。
ご自身が当てはまらないか、一度チェックしてみてください。
もしこれらの特徴に当てはまる場合は、すぐに投資を始めるのではなく、まず家計の見直しや知識の習得から始めることをお勧めします。
1. そもそも余剰資金がない人
投資は、当面使う予定のない「余剰資金」で行うのが大原則です。
生活費や、近い将来に使う予定が決まっているお金(教育費や住宅購入の頭金など)を投資に回してしまうと、価格が下落した際に生活が立ち行かなくなる恐れがあります。
まずは、生活費の3ヶ月〜1年分程度の「生活防衛資金」を確保することが最優先です。
2. 短期的な利益を期待している人
「すぐに大儲けしたい」という考えで投資を始めると、ハイリスクな短期売買に手を出しがちです。
これはもはや投資ではなく投機(ギャンブル)に近く、大きな損失を被る可能性が非常に高くなります。
資産運用は、長期的な視点でコツコツと資産を育てていくものだと理解しておく必要があります。
3. 勉強や情報収集が面倒な人
最低限の知識なしに投資を始めるのは、地図を持たずに航海に出るようなものです。
金融商品の特徴やリスク、手数料などを理解せずに始めると、言われるがままに不利益な商品を買ってしまったり、詐欺に遭ったりする危険性もあります。
自分で学び、判断する姿勢が不可欠です。
4. 他人の意見に流されやすい人
SNSや知人の「儲かった話」を鵜呑みにして、自分で調べもせずに同じ金融商品に飛びつくのは非常に危険です。
投資は自己責任が原則です。他人の成功例が自分にも当てはまるとは限りません。
なぜその商品が良いのかを自分で納得できるまで調べ、冷静に判断する力が必要です。
時間と共に広がる投資しない人との格差

インフレ、つまりモノの値段が上がり続ける経済状況下では、投資をする人としない人の間には、時間と共に着実に資産の格差が生まれていきます。
なぜなら、現金の価値はインフレによって目減りする一方、株式や不動産といった資産の価値は、インフレに伴って上昇する傾向があるからです。
これを「インフレヘッジ」と呼びます。
例えば、年間2%のインフレが続いたとしましょう。
銀行預金の金利がほぼ0%の現在、預貯金の実質的な価値は毎年2%ずつ減っていきます。
100万円を預けていても、10年後にはその購買力は約82万円まで落ち込んでしまう計算です。
一方で、株式などに投資し、年率3%のリターンを得られた場合、資産はインフレに負けることなく、むしろ着実に増えていきます。
複利効果が格差を加速させる
さらに、投資には「複利効果」という強力な味方がいます。
これは、運用で得た利益を再投資することで、利益が利益を生む「雪だるま式」に資産が増えていく効果のことです。
投資を早く始めるほど、この複利効果を長く享受でき、投資をしていない人との資産差は指数関数的に開いていくのです。
つまり、現代社会において投資をしないという選択は、現状維持どころか、実質的に資産を減らし、周りからどんどん遅れていってしまう可能性をはらんでいると言えるでしょう。
「具体的にどれくらいの金額差が生まれるのか?」と気になった方は、数千万円単位で開く生涯賃金と資産の現実をご確認ください。
資産を守るためにも「投資しないとやばい」理由
- 日本における投資しない人の割合
- そもそも、なぜ投資をやらないのか
- 意外と知らない投資しないメリット
- 根本的に投資しない方がいい人の特徴
- 時間と共に広がる投資しない人との格差
- 物価上昇?投資をしないリスクとは
- 貯金だけの「投資しない生き方」の現実
- 「投資しない人生」という選択肢
- 「ほったらかし投資は危険」は本当か
- 最終的に株だけで生きていけるのか
- 投資しない人の末路と「投資しないとやばい」訳
物価上昇?投資をしないリスクとは

「投資はリスクがあるから怖い」と考える人は多いですが、実は「投資をしないこと」にも大きなリスクが潜んでいます。
特に現在の日本のような物価上昇(インフレ)の局面では、そのリスクはより顕著になります。
投資をしない最大のリスクは、前述の通り「資産価値の目減り」です。
私たちが日々使っている「円」の価値は一定ではありません。モノの値段が上がれば、相対的にお金の価値は下がります。
例えば、昔は100円で買えたジュースが今は150円になっているように、同じ100円で買えるモノが減っていくのです。
超低金利時代の銀行預金では、このインフレのペースに資産を増やすことが追いつかず、大切に貯めたお金の購買力は年々失われていきます。
もう一つのリスク「機会損失」
投資をしないことのもう一つのリスクは「機会損失」です。
これは、投資をしていれば得られたはずの利益を得られない、という損失を指します。
特に、NISA(少額投資非課税制度)のように、国が税制優遇で後押ししている制度を使わないのは、非常にもったいない選択と言えます。
複利効果と非課税メリットを活かせば、将来的に大きな資産を築ける可能性を自ら手放していることになるのです。
このように、何もしないで銀行にお金を預けておくだけの「無行動」も、実は資産を危険に晒す一つのリスクなのだと認識することが重要です。
貯金だけの「投資しない生き方」の現実

それでは、貯金だけで「投資しない生き方」を続けた場合、私たちの将来にはどのような現実が待っているのでしょうか。
まず考えられるのは、老後資金が不足する可能性です。
人生100年時代と言われ、退職後の人生はますます長くなっています。
しかし、公的年金制度の先行きは不透明で、年金だけでゆとりある生活を送るのは難しいというのが現実的な見方です。
生命保険文化センターの調査では、夫婦2人で老後の最低日常生活費は月額約23.2万円、ゆとりある生活のためには約37.9万円が必要とされています。
この不足分を貯金だけで賄おうとすると、現役時代に相当な金額を貯蓄する必要があります。
しかし、日本の平均給与は過去20年以上ほとんど横ばいである一方、社会保険料や税金の負担は増え続けています。
このような状況で、給与からの貯蓄だけで十分な老後資金を準備するのは、多くの人にとって非常に困難な道のりです。
仮に退職金でまとまったお金が入ったとしても、インフレでその価値が目減りしていくことを考えると、貯金だけで老後の長い生活を乗り切るのは心許ないと言わざるを得ません。
計画的に資産運用を取り入れ、お金にも働いてもらう仕組みを作ることが、将来の安心につながるのです。
💡 老後2000万円問題、NISAだけで本当に足りますか?
「投資しないとやばい」のは事実ですが、実はNISAなどの積立投資だけでも、老後の安心を得るには不十分な場合があります。
会社員の信用力を活かし、NISAを土台にしながら最短で経済的自由を目指す「凡人のための資産形成ルート」を知っていますか?
知識ゼロからでも資産形成を加速させる、具体的なステップを確認してみませんか?
「投資しない人生」という選択肢

もちろん、「投資しない人生」を主体的に選ぶことも一つの生き方です。
価格変動のストレスを抱えず、確実な預貯金だけで生活を設計することに価値を見出す人もいるでしょう。
ただし、その選択をするのであれば、投資をしないことによるデメリットを正確に理解し、それに対する具体的な対策を講じる必要があります。
対策なしにただ投資を避けるだけでは、将来経済的に困窮するリスクを高めてしまいます。
投資をせずに資産を形成するための代替案としては、以下のようなものが考えられます。
投資以外の資産形成・防衛策
- 収入を増やす
本業での昇進やスキルアップ、あるいは副業を始めて収入源を増やす。 - 支出を減らす
家計を徹底的に見直し、固定費や変動費を削減して貯蓄率を最大限に高める。 - 自己投資
語学やプログラミングなど、将来の収入アップにつながるスキル習得にお金と時間を使う。
言ってしまえば、これらは投資の有無にかかわらず重要なことですが、「投資しない人生」を選ぶのであれば、より一層の努力が求められます。
自分の労働力や節約努力だけで、インフレや経済成長の恩恵を受ける投資マネーと渡り合っていく覚悟が必要になるのです。
それを理解した上で、自分にとって最適な道を選択することが大切です。
「ほったらかし投資は危険」は本当か

投資に興味を持った方が次に行き当たるのが「ほったらかし投資」という言葉です。
手間がかからず初心者向きと言われる一方で、「本当に放置していて大丈夫なのか?危険ではないのか?」という不安の声も聞かれます。
結論として、「ほったらかし投資」は正しい方法を理解して実践すれば、非常に有効でリスクを抑えた資産形成術です。
しかし、やり方を間違えれば危険なものにもなり得ます。
危険な「ほったらかし投資」とは、主に次のようなケースです。
危険な「ほったらかし」の例
- 内容をよく理解せず、手数料の高い金融商品を放置している。
- 特定の国や特定の業界の株式など、値動きの激しい商品に集中投資して放置している。
- ライフプランが変化したにもかかわらず、リスク許容度を見直さずに放置している。
一方で、安全性を高める「正しいほったらかし投資」のポイントは、「長期・積立・分散」の3原則を守ることに尽きます。
具体的には、全世界株式や米国株式のインデックスファンドのような、手数料が安く、広範囲に分散された商品を、毎月決まった額でコツコツと買い続ける方法が王道です。
この方法であれば、最初に設定さえ済ませてしまえば、日々の値動きに一喜一憂する必要はありません。
むしろ、何もしないで放置し続けることが成功の鍵となります。
短期的な価格下落は、安く買えるチャンスと捉え、冷静に積立を継続することが重要です。
つまり、「ほったらかし投資」は危険なのではなく、「無知なまま放置すること」が危険なのです。
最終的に株だけで生きていけるのか
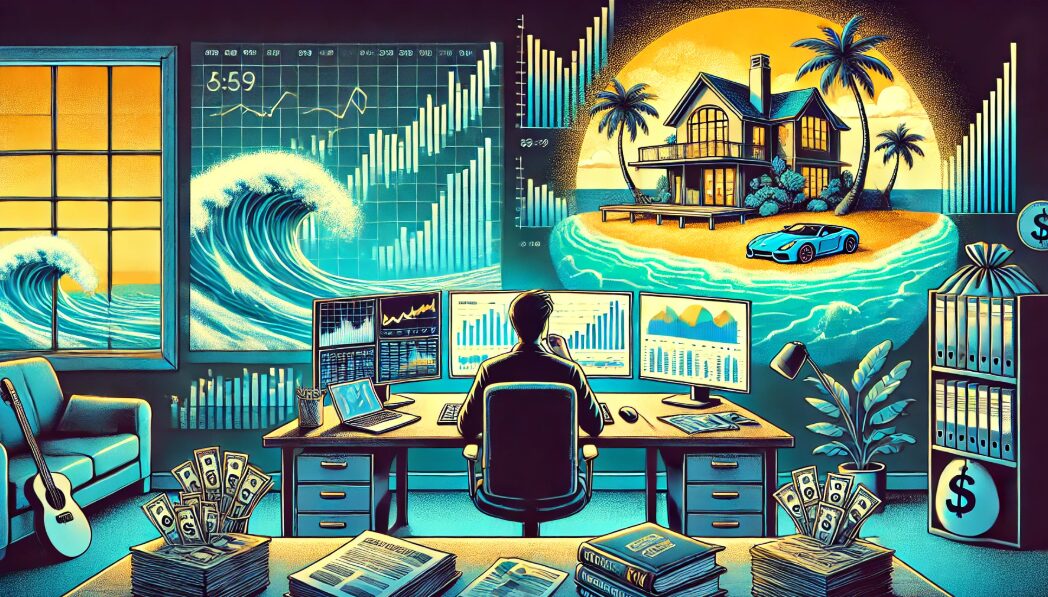
投資の話が盛り上がると、最終的なゴールとして「株の利益だけで生活する(FIRE)」という夢を思い描く人もいるかもしれません。
結論から言うと、株だけで生活することは理論上は可能ですが、実現するためのハードルは極めて高いと言わざるを得ません。
多くの人が想像する以上に、莫大な元手資金と、相場の変動に耐えうる強靭な精神力が必要になります。
一つの目安として、配当金だけで生活する場合を考えてみましょう。
年間の生活費が300万円必要だとします。株式の配当利回りを平均3%と仮定すると、必要な元手は1億円(300万円 ÷ 3%)にもなります。
ここから約20%の税金が引かれることを考えれば、実際にはさらに多くの資金が必要です。
デイトレードのような短期売買で日々利益を出す方法もありますが、これはプロの世界であり、安定して勝ち続けることは至難の業です。
収入が不安定になるリスクや、社会との繋がりが希薄になるデメリットも考慮しなければなりません。
このため、ほとんどの人にとって現実的な目標は、専業投資家になることではなく、仕事を続けながら安定収入を確保しつつ、投資によって資産を増やしていく「兼業投資家」を目指すことでしょう。
投資はあくまで、人生を豊かにするための「手段」の一つと捉えるのが賢明です。
まとめ:投資しない人の末路と「投資しないとやばい」訳
この記事では、「投資しないとやばい」という言葉の背景にある経済的な現実から、投資をしないメリットやリスク、そして様々な生き方の選択肢について詳しく解説してきました。
ここまでお読みいただいたあなたは、もはや何もしないでいることのリスクを十分に理解し、ご自身の将来について真剣に考え始めていることでしょう。
最後に、本記事の重要なポイントを改めて振り返ります。
- 日本の家計資産は預貯金に偏っており世界的に資産が増えにくい
- インフレ下では預貯金の実質的な価値は年々目減りしていく
- 何もしない「無行動」自体が資産を減らすリスクとなる時代である
- 投資する人としない人の資産格差は複利効果によって時間と共に拡大する
- 給与が増えにくい現代において貯金だけで十分な老後資金を準備するのは困難
- 多くの人が資金や知識の不足、損失への恐怖から投資をためらっている
- 余剰資金がなく短期利益を求める人は投資で失敗しやすい
- 投資しない人生を選ぶなら副業や徹底した節約など代替策が不可欠
- 「ほったらかし投資」は長期・積立・分散の原則を守れば危険性は低い
- 株だけで生活することは可能だが莫大な資金が必要で多くの人には非現実的
- NISAなど国が後押しする非課税制度を活用しないのは大きな機会損失
- 資産を守り、育てるための手段として投資の重要性が増している
- お金に働いてもらう仕組みを作ることが将来の経済的な自由に繋がる
- 大切なのは、まず少額からでも一歩を踏み出して投資に慣れること
これらの事実を踏まえると、将来の安心と豊かさをその手に掴むために、資産運用という選択肢を真剣に検討する重要性がお分かりいただけたのではないでしょうか。
もちろん、投資に元本割れのリスクは伴います。
しかし、そのリスクは正しい知識を身につけ、長期的な視点で少額から始めることで十分にコントロール可能です。
今はインターネット証券を使えば、自宅からでも簡単に、そして月々1,000円といった少額からでも資産運用をスタートできる時代です。
「もっと早く始めておけばよかった…」と数年後に後悔する前に、まずはNISA口座の開設を調べてみる、一冊本を読んでみるなど、今日からできる小さな一歩を踏み出してみませんか。
「よし、まずは少額からやってみよう」と思われた方は、スマホで完結する失敗しない始め方をチェックしておきましょう。
あなたの未来を大きく変えるための行動は、今この瞬間から始められるのです。
より広い視点から【必見】『投資しない方がいい人の特徴と、それでも始めるべき理由』について体系的に理解したい方は、ぜひこの記事も合わせてご覧ください。
あなたの「将来の不安」を「確実な資産」に変えるロードマップ
「投資しないとやばい」と気づいた今が、人生を変える最大のチャンスです。
しかし、ただ闇雲に株を買うだけでは、本当の経済的自由には届きません。まずはNISAで土台を作り、その上で安定した収益源を築く「正しい順序」があります。
凡人が経済的自由を手にするための、具体的な戦略を今すぐご確認ください。
あわせて読みたい関連記事
