
「日本で投資をしていない人はどのくらいの割合なのだろう?」と疑問に感じていませんか。
周囲でNISAなどの話題を耳にする機会が増え、自分の現状と世の中の動向が気になっている方も多いかもしれません。
この記事では、まず日本における投資している人の割合を、年代別のデータも交えて具体的に解説します。
同時に、NISAが何人に1人くらいの割合で利用されているのか、その実態にも迫ります。
しかし、依然として多くの人が投資に踏み出せない現実があり、そこには日本人が投資しない理由や、なぜ投資をしないのかという根深い背景が存在します。
中には、投資しないほうがいいという考えを持つ方もいるでしょう。
一方で、投資しない生き方を続けることで、将来的に投資しない人の末路として語られるような資産格差の問題に直面する可能性も指摘されています。
インフレが進む現代において、投資しないとやばいという声も聞かれます。
実際に投資で儲かってる人の割合はどの程度なのか、この記事を通じて、客観的なデータに基づいた日本の投資事情を深く理解し、ご自身の資産形成について考えるきっかけを提供します。
この記事は、そもそも「本当に投資しない方がいい人の特徴」とは何か、という大きなテーマを解説した特集の一部です。
記事のポイント
- 日本における投資をしている人・していない人の具体的な割合
- 多くの日本人が投資を始められない理由とその文化的背景
- 投資をしない場合に考えられるインフレなどの将来的なリスク
- 資産格差の時代で損をしないための資産形成のヒント
日本の投資しない人の割合とその背景
この章では、現在の日本で投資を行っている人がどれくらいの割合なのか、そして、なぜ多くの人が投資に踏み出せないでいるのか、その背景にある具体的な理由をデータと共に掘り下げていきます。
- 日本の投資しない人の割合とその背景
- 日本で投資している人の割合とは?
- 年代別で見る投資している人の割合
- NISAは何人に1人が利用している?
- なぜ投資をしないのかという疑問
- 日本人が投資しない理由を解説
- 投資しないほうがいいという意見も
- 投資しない人の割合から考える未来
- 投資で儲かってる人の割合は本当?
- このまま投資しないとやばいのか
- 投資しない人の末路と広がる格差
- 「投資しない生き方」のリスク
- まとめ:投資しない人の割合と今後
日本で投資している人の割合とは?

現在、日本で何らかの有価証券(株式、投資信託など)を保有している人の割合は、決して高いとは言えない状況です。
※日本証券業協会が2024年に実施した調査によると、有価証券の保有率は24.1%でした。
これは、約4人に1人が投資を行っている計算になりますが、裏を返せば、国民の約75%は投資をしていないという現実を示しています。
この状況は、他の先進国と比較するとより鮮明になります。
日本銀行調査統計局が発表したデータを見ると、家計の金融資産構成には大きな違いが見られます。
※引用:日本証券業協会
【日米欧の家計金融資産構成比較】
| 項目 | 日本 | 米国 | ユーロエリア |
| 現金・預金 | 50.9% | 11.7% | 34.1% |
| 株式・投資信託 | 19.6% | 53.3% | 32.1% |
| 保険・年金 | 24.6% | 27.7% | 28.7% |
| その他 | 4.9% | 7.3% | 5.1% |
(出典:日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較」(2024年8月)のデータを基に作成)
この表から分かるように、日本では金融資産の半分以上が「現金・預金」に集中しています。
一方で、米国では資産の半分以上が「株式・投資信託」で運用されており、資産形成に対する考え方が根本的に異なることがうかがえます。
このように、日本では依然として「貯蓄」を重視する傾向が強く、投資人口の割合は限定的であるのが現状です。
年代別で見る投資している人の割合

投資している人の割合は、年代によっても異なる傾向が見られます。
一般社団法人投資信託協会の2023年の調査によると、投資信託を積立投資で利用している割合は、20代と30代で80%を超えており、若年層で資産形成への関心が高まっていることが分かります。
これは、将来への不安やSNSなどを通じた情報収集の容易さが背景にあると考えられます。
一方で、金融庁のNISA口座開設状況を見ると、口座数自体は40代、50代といったミドル世代が最も多くなっています。
この世代は、子育てが一段落し、老後資金を意識し始める時期であるため、まとまった資金を投資に回しやすい環境にあることが理由として挙げられます。
しかし、高齢者層に目を向けると、一般的に投資への浸透率は低い傾向にあります。
長年のデフレ経験から「現金が最も安全」という意識が根強く残っていることや、リスクを取ることへの抵抗感が強いことが影響しています。
これらのことから、若年層を中心に投資への意識は変化しつつあるものの、世代間でのギャップは依然として大きいと言えます。
NISAは何人に1人が利用している?

2024年から新NISA(少額投資非課税制度)が始まり、投資への関心は一層高まっています。では、実際にNISAはどの程度普及しているのでしょうか。
金融庁が公表した2024年3月末時点のデータによると、NISA口座の総数は約2,322万口座に達しました。
日本の18歳以上の人口が約1億469万人(2023年1月時点)であることを踏まえると、単純計算で約4.6人に1人がNISA口座を開設していることになります。
(出典:金融庁「NISA口座の利用状況調査(令和6年3月末時点)」)
特に新NISAが開始されてからの3ヶ月間だけで口座数が約200万も増加しており、この制度が投資を始める大きなきっかけになっていることがうかがえます。
NISA口座数の推移
- 2023年12月末: 約2,124万口座
- 2024年3月末: 約2,322万口座 (3ヶ月で約200万口座増加)
非課税投資枠の大幅な拡大や制度の恒久化によって、これまで投資に踏み出せなかった層も、NISAをきっかけに資産運用をスタートさせていると考えられます。
この流れは今後も加速していくと予想されます。
なぜ投資をしないのかという疑問
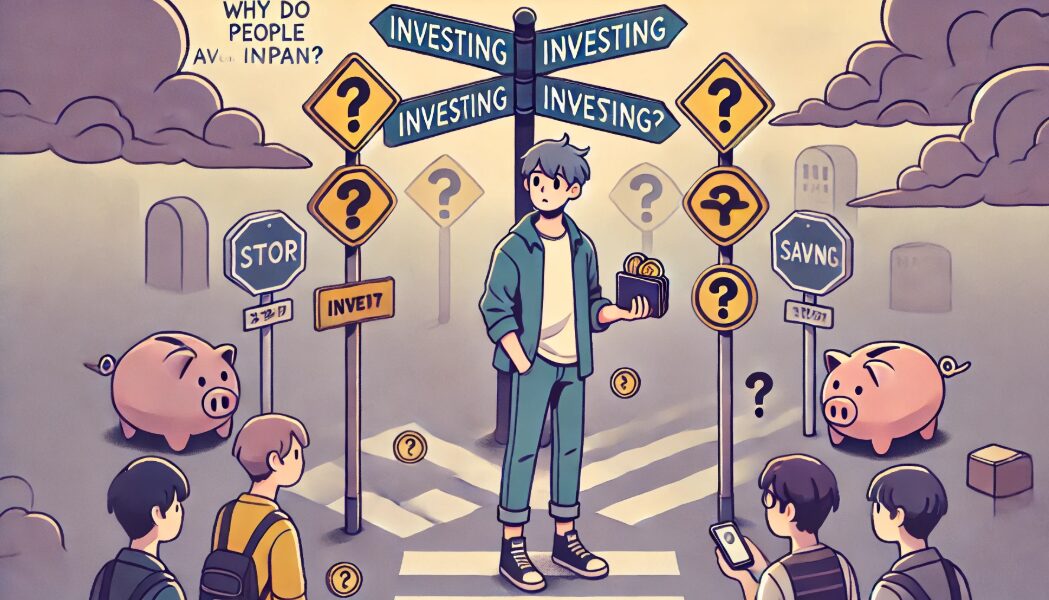
約4人に1人が投資をしている一方で、残りの多くの人々はなぜ投資をしないのでしょうか。その背景には、いくつかの共通した理由が存在します。
野村アセットマネジメント株式会社が実施した調査では、投資をしていない人に「どのような条件がそろったら投資を始めたいか」と尋ねたところ、興味深い結果が出ています。
投資を始めたい条件(投資未経験者への調査)
- どんなことがあっても投資はしない: 31%
- 絶対に損をしなければ: 29%
- 給料・所得が増えたら: 24%
最も多かった回答は「どんなことがあっても投資はしない」であり、約3割の人が投資に対して強い拒否感を持っていることが分かります。
また、「絶対に損をしなければ」という回答も多く、元本割れのリスクに対する強い不安が投資への大きな障壁となっているようです。
さらに、金融庁の別の調査では、資産運用をしない理由として「余裕資金がないから」が半数以上を占めています。
これらの結果から、多くの人が「投資は損をする可能性があり、まとまったお金がないと始められないもの」と考えていることが、投資に踏み出せない大きな理由であると分析できます。
日本人が投資しない理由を解説
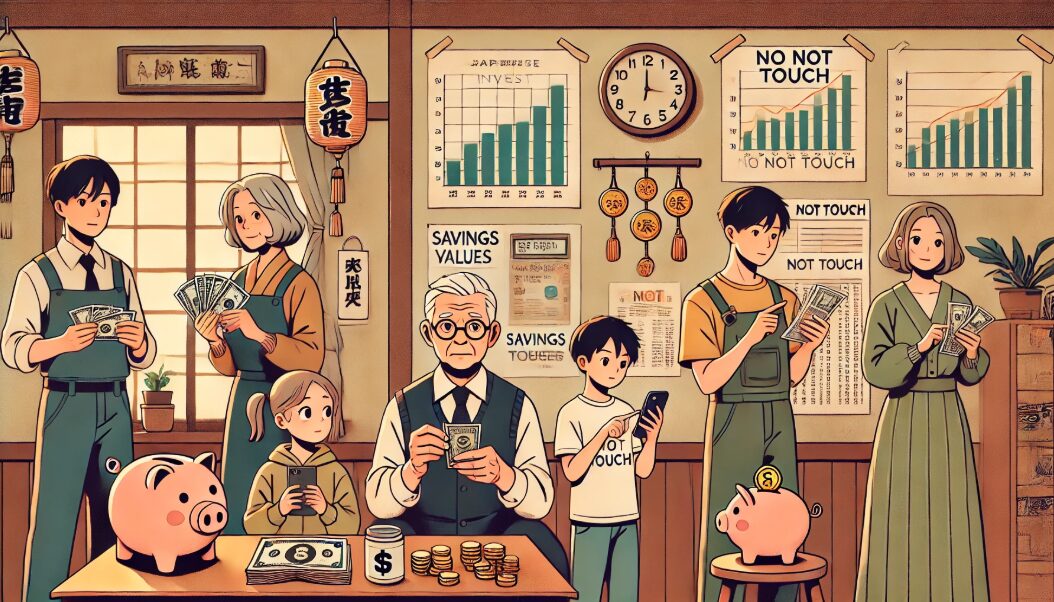
前述の「資金がない」「損が怖い」といった直接的な理由の裏には、日本人特有の文化的・社会的な背景が深く関わっています。
第一に、長年にわたる「貯蓄文化」の影響が挙げられます。
日本では古くから「汗水流して働き、コツコツ貯金すること」が美徳とされてきました。
また、バブル崩壊後の長いデフレ経済の中では、物価が上がらなかったため、現金の価値が目減りせず、預金だけでも資産の価値を維持できたのです。
この成功体験が、「投資=リスク、貯蓄=安心」という考え方を強固なものにしました。
第二に、金融教育の遅れです。欧米では家庭や学校で幼い頃からお金や投資について学ぶ機会が一般的ですが、日本では2022年度から高校で「資産形成」の授業が導入されたばかりです。
多くの大人が金融リテラシーを学ぶ機会がないまま社会に出ており、「投資はギャンブル」といった誤ったイメージを払拭できずにいます。
第三に、「お金の話はタブー」という社会的な風潮も無視できません。
親しい間柄でも資産や投資に関する話題を避ける傾向があり、情報交換が活発に行われないため、投資への心理的なハードルが高くなっているのです。
投資しないほうがいいという意見も
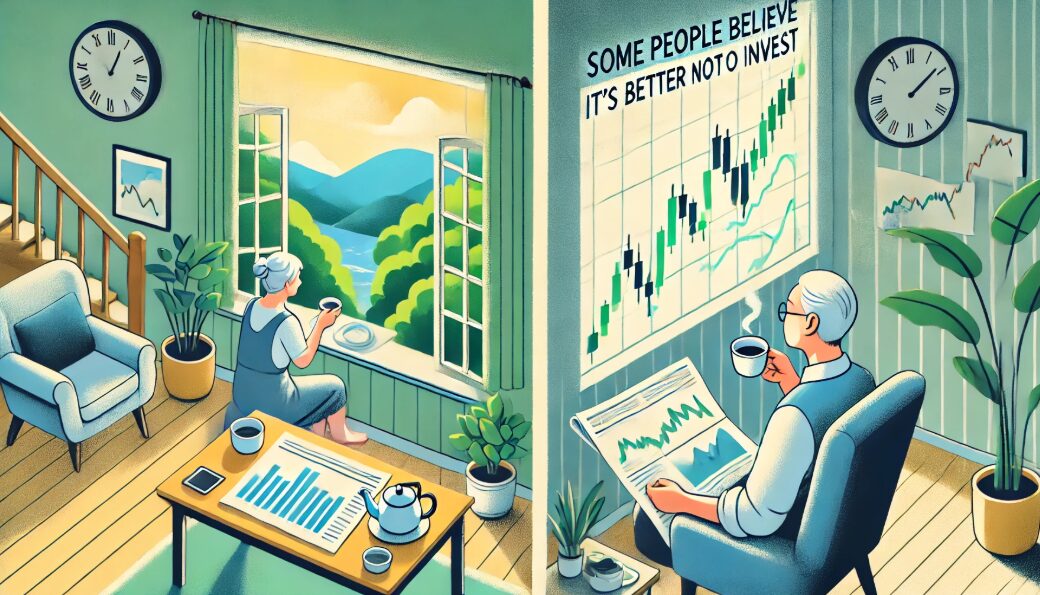
もちろん、全ての人にとって投資が最善の選択とは限りません。
投資をしないほうがいい、と考える意見にも耳を傾ける必要があります。
投資には、必ず元本割れのリスクが伴います。
どれだけ慎重に分散投資を行っても、経済危機や市場の暴落によって資産が購入時より減ってしまう可能性はゼロではありません。
この価格変動による精神的なストレスに耐えられない人や、短期的に使う予定のある資金しか持っていない人は、無理に投資を始めるべきではないかもしれません。
また、投資で成果を出すには、ある程度の勉強や情報収集が不可欠です。
どのような商品を選ぶべきか、市場が変動したときにどう対応すべきかなど、学び続ける姿勢が求められます。
このような時間や手間をかけることが難しいと感じる人にとっては、投資は負担になる可能性があります。
さらに、生活に最低限必要な資金(生活防衛資金)を確保できていない段階で投資を始めるのは危険です。
万が一の事態に備えるお金がないまま投資に回してしまうと、急な出費が必要になった際に、損失が出ているタイミングで売却せざるを得ない状況に陥ることもあります。
投資しない人の割合から考える未来
現在の投資しない人の割合を踏まえ、このまま資産運用をしないという選択を続けた場合、将来どのような影響が考えられるのでしょうか。
この章では、投資をする人としない人の間に生じる可能性のある差や、考えられるリスクについて解説します。
- 日本の投資しない人の割合とその背景
- 日本で投資している人の割合とは?
- 年代別で見る投資している人の割合
- NISAは何人に1人が利用している?
- なぜ投資をしないのかという疑問
- 日本人が投資しない理由を解説
- 投資しないほうがいいという意見も
- 投資しない人の割合から考える未来
- 投資で儲かってる人の割合は本当?
- このまま投資しないとやばいのか
- 投資しない人の末路と広がる格差
- 「投資しない生き方」のリスク
- まとめ:投資しない人の割合と今後
投資で儲かってる人の割合は本当?

「投資で儲かっている」と聞くと、一部の特別な才能を持った人だけの話のように感じるかもしれません。
しかし、実際のデータを見ると、市場環境によっては多くの人が利益を得ています。
例えば、オンライン株式スクール「株の学校ドットコム」が2024年6月に実施した調査によると、2024年上半期の株式投資において、88%の人が利益(含み益を含む)を出していると回答しました。
これは、日経平均株価が史上最高値を更新するなど、市場全体が好調だったことが大きく影響しています。
ただし、この数字はあくまで特定の期間を切り取ったものです。
金融庁が2020年に発表した別の調査では、投資信託で利益が出た人の割合は約3割でした。
一般的に、長期的に見て利益を出せる人の割合は2~3割程度とも言われています。
これらのデータから分かることは、投資の成果は相場の状況に大きく左右されるということです。
市場が好調な時期には多くの人が利益を得やすくなりますが、下落局面では損失を抱える人も増えます。
必勝法というものは存在せず、儲かっている人がいる一方で、損をしている人も必ず存在します。
大切なのは、短期的な成功や失敗に一喜一憂せず、長期的な視点でリスクを管理しながら資産形成に取り組む姿勢です。
このまま投資しないとやばいのか

「投資しないとやばい」という言葉を耳にすることが増えましたが、その背景には「インフレ」という、私たちの資産価値を静かに蝕む問題があります。
インフレとは、物やサービスの値段が上がり、相対的にお金の価値が下がることです。
例えば、これまで100円で買えたジュースが120円に値上がりした場合、同じものを買うためにより多くのお金が必要になり、100円というお金の価値は実質的に下がったことになります。
日本は長らくデフレ(物価が下がる状態)が続いていましたが、2022年以降はインフレ傾向に転じています。
もし年2%のインフレが続いた場合、銀行に預けているお金の価値はどうなるでしょうか。
年2%のインフレによる資産価値の目減りシミュレーション
| 経過年数 | 100万円の実質的な価値 |
| 現在 | 100万円 |
| 10年後 | 約82万円 |
| 20年後 | 約67万円 |
| 30年後 | 約55万円 |
現在の普通預金の金利はメガバンクでも年0.1%程度と非常に低いため、100万円を1年間預けても利息はわずか1,000円です。
物価上昇のペースに金利が全く追いついておらず、銀行に預けているだけでは、資産の額面は変わらなくても、その購買力(買えるモノの量)は年々減っていくことになります。
この「資産が実質的に目減りするリスク」こそが、「投資しないとやばい」と言われる最大の理由なのです。
投資しない人の末路と広がる格差
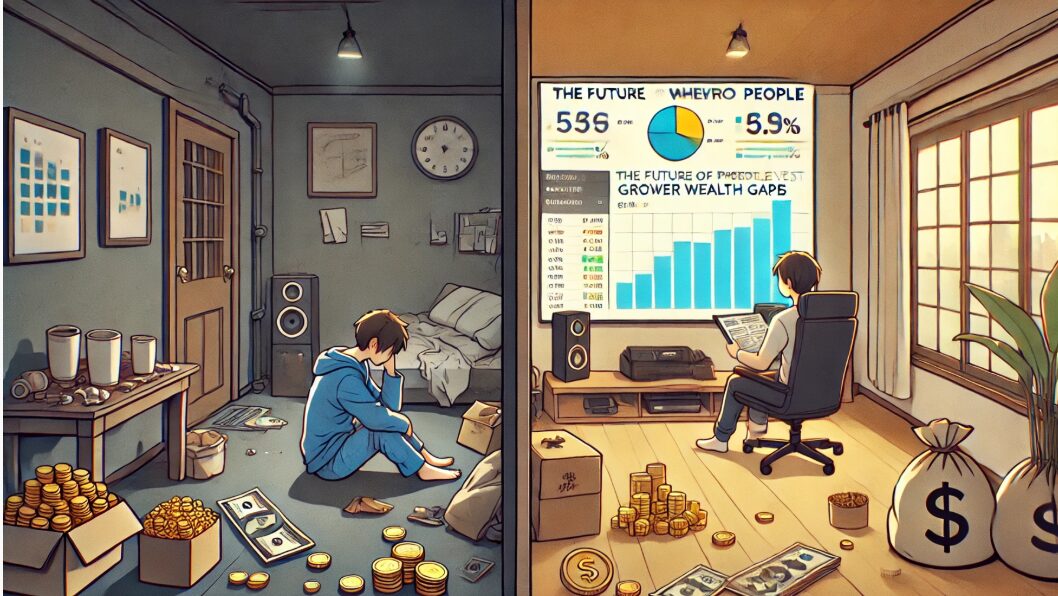
インフレが進む社会で投資をしないという選択は、将来的に大きな格差を生む可能性があります。
インフレ環境下では、企業は製品価格を上げることで収益を伸ばしやすくなり、それが株価の上昇につながる傾向があります。
また、不動産などの実物資産も、物価の上昇と共に価値が上がることが期待されます。
つまり、株式や不動産といった資産を持っている人は、インフレによって自身の資産価値を高めることができるのです。これをインフレヘッジと呼びます。
一方で、資産の大部分を現金や預金で保有している人は、前述の通り資産価値が実質的に目減りしていきます。
給与の上昇が物価上昇に追いつかなければ、生活はますます苦しくなるでしょう。
この状況は、言い換えれば「資産を運用する人」と「貯蓄しかしない人」の間で、富の移転が起こることを意味します。
何もしなければ、持っているお金の価値はインフレによって投資家や企業へと静かに移っていきます。
これが、投資をする人としない人の間で資産格差が拡大していくメカニズムです。
豊かな老後を送るためには、この構造を理解し、自ら資産を守り育てる行動を起こすことが求められます。
「投資しない生き方」のリスク
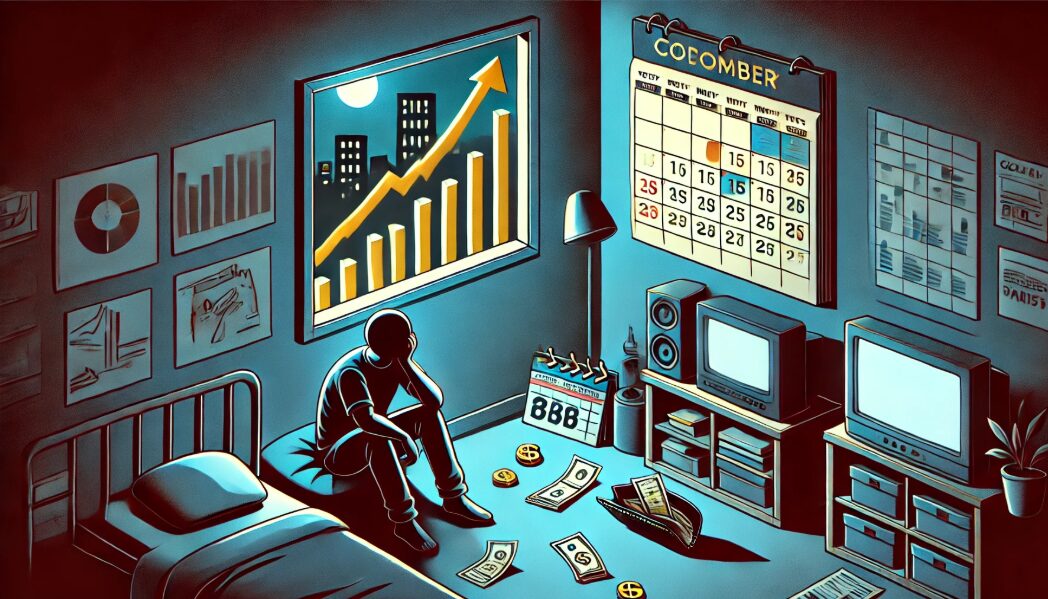
投資をしないという選択は、個人の価値観に基づくものであり、それ自体が間違いではありません。
しかし、その選択をする上では、付随するリスクを正しく理解しておく必要があります。
主なリスクは以下の3点です。
1. インフレによる資産価値の目減り
繰り返しになりますが、これが最大のリスクです。
物価上昇に対応できず、貯蓄の実質的な価値が下がり続けることで、将来の生活設計が大きく狂う可能性があります。
2. 公的年金の不確実性
日本の公的年金制度は、少子高齢化の進行により、将来的に給付水準が低下していくことが避けられない状況です。
現役世代の手取り収入に対する年金額の割合(所得代替率)は年々下がっており、「年金があるから大丈夫」という考えは過去のものとなりつつあります。
3. 終身雇用と退職金の崩壊
かつては多くの企業で保証されていた終身雇用や手厚い退職金も、現在では当たり前ではありません。
企業の業績や経済状況によっては、期待していた退職金が得られない可能性も十分にあります。
これらのリスクを総合的に考えると、「投資しない生き方」とは、将来の生活資金をインフレや社会構造の変化といった自分ではコントロールできない外部要因に委ねてしまう生き方とも言えます。
公的な保障に頼るだけでなく、自助努力によって資産を形成していく必要性は、年々高まっているのです。
まとめ:投資しない人の割合と今後
- 日本の投資人口は約4人に1人で欧米に比べて低い水準
- 家計金融資産の半分以上が現金・預金に集中している
- 若年層で投資への関心は高まっているが世代間ギャップは大きい
- 新NISAの開始により口座開設者は急増し約4.6人に1人が利用
- 投資をしない主な理由は「余裕資金がない」「損が怖い」「知識不足」
- 背景には長年の貯蓄文化や金融教育の遅れがある
- 投資には元本割れのリスクや精神的負担が伴うことも事実
- 市場環境によっては多くの投資家が利益を得ている
- インフレは現金や預金の価値を実質的に減らしていく
- 銀行預金の低金利では資産の目減りを防ぐことは困難
- 投資はインフレから資産価値を守る有効な手段となり得る
- 投資する人としない人の資産格差は今後拡大する可能性がある
- 公的年金や退職金だけに頼る将来設計は不確実性が高い
- 少額から始められる積立投資など初心者向けの方法も充実している
- 将来のために正しい知識を身につけ今から行動を始めることが大切
より広い視点から『投資しない方がいい人の特徴と、それでも始めるべき理由』について体系的に理解したい方は、ぜひこの記事も合わせてご覧ください。
